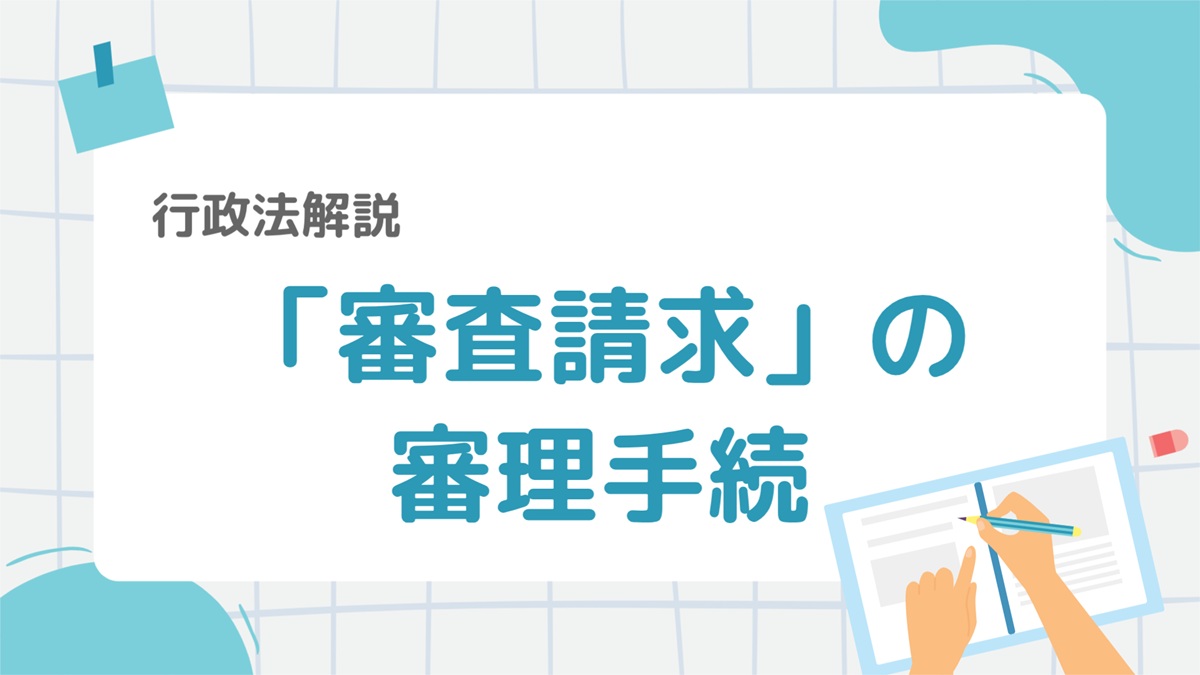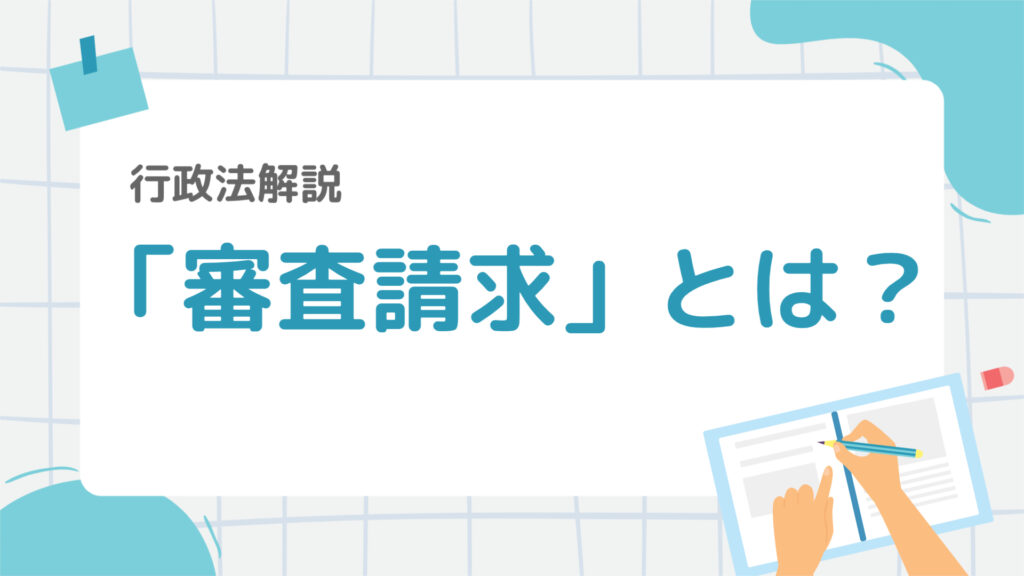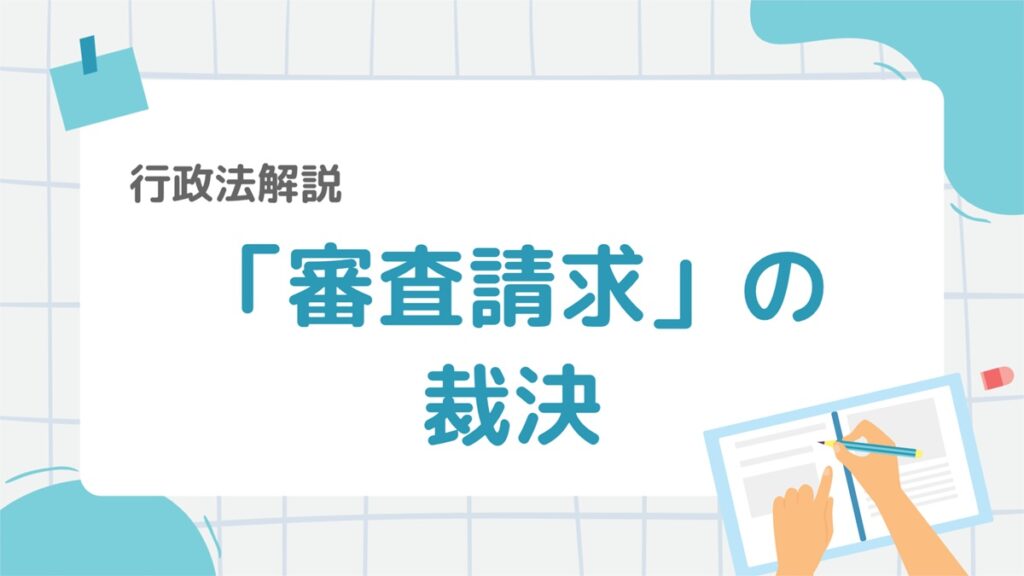- 審査請求の「審理手続」の流れがよく分からない…
- 書面審査や職権探知主義ってどういう意味?
- 行政書士試験で頻出の「審理員」や「参加人制度」などを理解したい!
- 条文ベースでは難しいので、やさしく解説してほしい!
🧭審査請求の審理手続とは?【全体の流れを解説】
①審理の主宰:審理員が中立の立場で進行
審理手続は、処分に関与していない審査庁の職員=審理員が主宰します。これは、公平な審理を確保するためです。1
審査庁は、原則として、その職員の中から審理員を指名しなければなりません(9条1項本文)。
②審理の準備:主張と反論をやり取り
審理員が指名されると、以下のようなやり取りが行われます。
- 📤 審理員は、直ちに、審理請求書(書面による審査請求の場合)or審査請求録取書の写し(口頭による審査請求の場合)を処分庁等に送付(29条1項本文)
- 📝 相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求める(29条2項)
- 📩 弁明書の提出があった後は、審査請求人へ送付(29条5項)
- ✍️ 審査請求人は、便面所に対する「反論書」を提出可能(30条1項前段)
- 📤 反論書は処分庁へ送付される(30条3項)。
このように、書面でのやり取りが中心となります。図に表すと次の通りです。
sequenceDiagram
actor 審査請求人
participant 審理員
participant 処分庁等
審査請求人->>審理員: ①審査請求書または審査請求録取書
審理員-->>処分庁等: ②審査請求書の写しを送付
審理員->>処分庁等: ③弁明書の提出を求める
処分庁等-->>審理員: ④弁明書の提出
審理員-->>審査請求人: ⑤弁明書を送付
審査請求人->>審理員: ⑥反論書を提出可能
審理員-->>処分庁等: ⑦反論書を送付③原則は書面審査!ただし口頭意見も可能
審理は原則として書面審査主義です。裁判のような口頭審理は行われません。
ただし、以下の場合には口頭で意見を述べる機会も認められます(31条1項)。
- 審査請求人または参加人から申立てがあったときで、
- 審理員が「困難である」と判断しない場合
👉申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない(31条1項)。23
④職権探知主義:審理員が自ら事実を調べる
審理手続では、訴訟と異なり、審理員が自ら必要な証拠などを集めることができます。これを職権探知主義といいます。
審理員は以下のことが可能です:
⑤参加人制度:利害関係人も参加できる
審理に関係する第三者(利害関係人)は、審理員の許可を得て「参加人」として手続に加わることができます(13条1項)。
✨審理手続の特則
- 審理手続の併合・分離
-
複数の審査請求がある場合、審理員はそれらを併合または分離すすることができます(39条)。
- 審理手続の承継
✅審理手続の終結とその後の流れ
- ①審理手続の終結
-
審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結します(41条1項)。
- ②審理員意見書
-
審理員は、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成し(42条1項)、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければなりません(42条2項)。
この意見書は、審査庁が公正な裁決を行うための重要な資料です。
- ③行政不服審査会等への諮問
-
審査庁は、原則として「行政不服審査会等」に諮問する必要があります(43条1項)。裁決の中立性と透明性を確保するために義務付けられています。
🔚審査請求の取下げ
審査請求人は、裁決が下される前であれば、いつでも審査請求を取り下げることができます(27条1項)。ただし、
- 書面によることが必要(27条2項)。
- 口頭では認められません(後日のトラブル防止のため)
📝まとめ|審理手続の全体像を押さえて得点源に!
審査請求の審理手続は、行政書士試験の中でも出題頻度が高く、正確な理解が求められるテーマです。ポイントを整理すると以下のとおりです。
✅審理手続の重要ポイント
- 審理員が主宰し、公正性を確保
- 書面審査主義が原則。ただし、口頭意見の申立ても可能
- 職権探知主義により、審理員が証拠収集等を主導
- 利害関係人は「参加人」として参加可能
- 包括承継は許可不要/特定承継は許可必要
- 手続が終わると、審理員意見書→行政不服審査会への諮問→裁決という流れ
- 審査請求の取下げは書面でOK(裁決前ならいつでも)
📌試験対策のコツ
- 条文番号やキーワード(審理員・弁明書・反論書・職権探知など)をセットで覚える
- 書面審査と口頭意見の違いを区別しておく
- 取下げや承継の条件は例外規定として要チェック
- 参考:審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、適当な方法により公にしておかなければならない(17条) ↩︎
- 参考:口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる(31条3項) ↩︎
- 参考:口頭意見陳述の規定は、再調査の請求にも準用される(61条) ↩︎
- 鑑定:特別な学識経験者に専門的知識またはそれを利用した判断の結果を報告させること ↩︎
- 検証:物・場所・人について、その存在や状態などを認識すること ↩︎
- 包括承継:すべての権利・義務を受け継ぐこと ↩︎
- 特定承継:ある特定の権利・義務を受け継ぐこと ↩︎