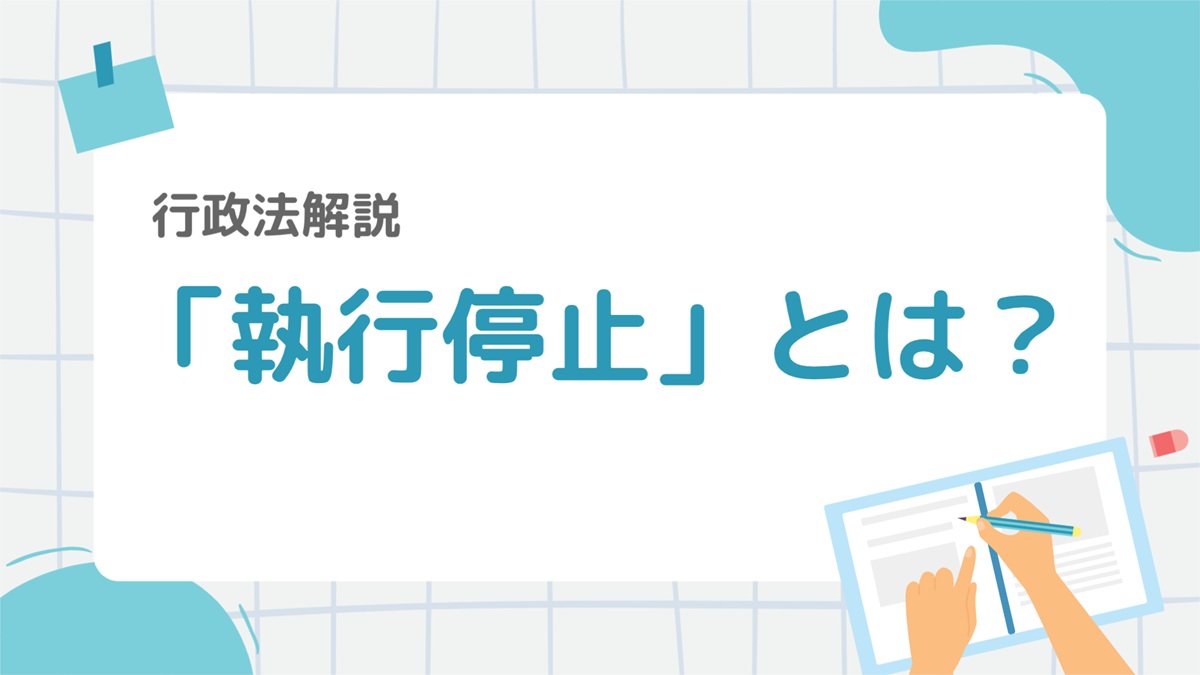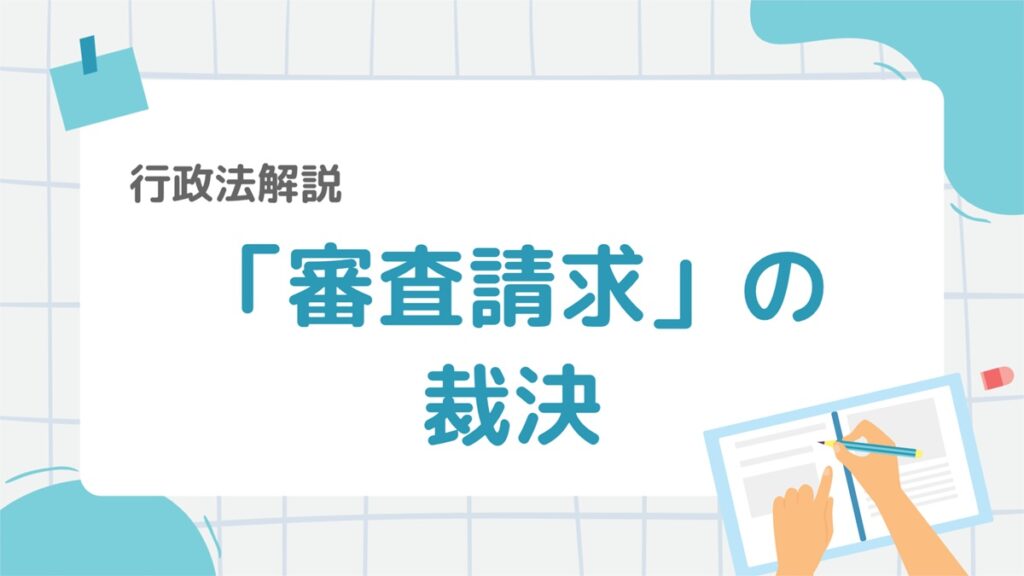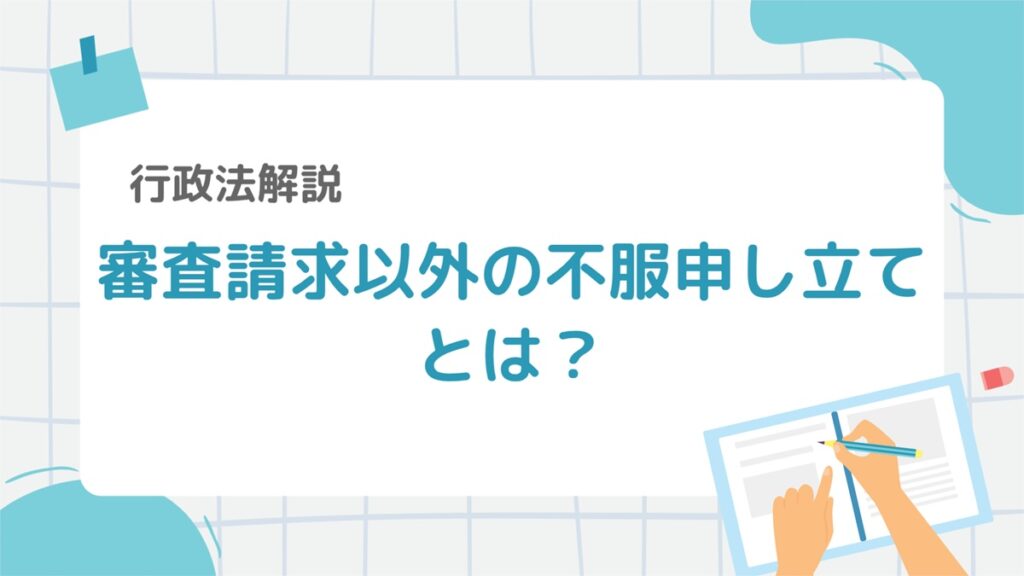🎯 この記事はこんな人におすすめ
- 「執行停止」と「執行不停止の原則」の違いが曖昧な方
- 義務的な執行停止と任意的な執行停止の違いを知りたい方
- 行政不服審査法と行政事件訴訟法での執行停止の違いを整理したい方
目次
✅ 執行停止とは?まずは「執行不停止の原則」から
行政不服審査法では、原則として審査請求が行われていても、処分の効力やその執行、手続きの進行は止まりません。これを 「執行不停止の原則」といいます(25条1項)。
これは、行政の円滑な運営を妨げないようにするためのルールです。
✅ なぜ「執行停止」が認められるのか?
この原則を貫いてしまうと、審査請求中に処分が進んでしまい、後で処分が違法だと認められても、元に戻せないという問題が生じます。
そのため、審査請求人の権利を保護するために、以下のような措置が認められています。
これが「執行停止」制度(25条2項~7項)です。
※ただし、処分の効力の停止は、執行や手続の停止で目的が達成できる場合は認められません(25条6項)。
✅ 執行停止の3つのパターンと具体例
| 意味 | 具体例 | |
| 処分の効力の停止 | 処分の効力を暫定的に停止し、処分がなかった状態を復元する | 懲戒免職処分の効力の停止 |
| 処分の執行の停止 | 処分により課された義務の履行を確保するための行政手段を停止する | 退去強制令書の発付処分における強制送還の停止 |
| 手続の続行の停止 | 処分の存在を前提としてなされる後続の手続(処分)を停止する | 事業認定後の収用裁決の停止 |
✅ 「任意的」か「義務的」か?執行停止の判断基準
行政不服審査法の執行停止には、執行停止をするかどうか審査庁の任意に委ねられている場合(任意的な執行停止)と、審査庁が必ず執行停止をしなければならない場合(義務的な執行停止)の2つがります。
■ 任意的な執行停止(25条2項・3項)
審査庁が次のような状況で、申立て or 職権により執行停止を判断できます。
| 審査庁が上級行政庁or処分庁 | 審査請求人の申立てまたは職権により、執行停止をすることができる(25条2項)1 |
| 審査庁がどちらでもない | 審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上で、執行停止をすることができる(25条3項) |
■ 義務的な執行停止(25条4項)
次のような状況では、審査庁は必ず執行停止をしなければなりません。
- 処分などにより重大な損害が生じるおそれがあり、それを避けるため緊急の必要があると認められる場合、執行停止をしなければならない(25条4項)
ただし、以下の場合には義務なし
- 公共の福祉に重大な影響を与える恐れがあるとき
- 本案2に理由がないとみえるとき
✅ 審査員による「執行停止すべき」意見(25条7項・40条)
審査員は、審査庁に対して「執行停止をすべき旨の意見書」を提出できます(40条)。
しかし、これはあくまで助言的な意見にすぎず、審査庁に執行停止の義務は課されません(速やかに執行停止をするかどうかを決定しなければならないとされているにすぎない)。
✅ 執行停止の取消し(26条)
審査庁は、執行停止した後でも、次のような理由があれば取消しが可能です(26条)。
- 公共の福祉に重大な悪影響があると明らかになった
- 事情が変更した場合 など
行政不服審査法と、行政事件訴訟法の執行停止の違いを簡単に比較
| 行政不服審査法 | 行政事件訴訟法 | ||
| 審査庁が「処分庁の上級行政庁」or「処分庁」 | 審査庁が「処分庁の上級行政庁」「処分庁」以外 | ||
| 職権による執行停止 | 〇可能 | ×不可 | ×不可 |
| 処分場の意見聴取 | ×不要 | 〇必要 | 〇必要 |
| 執行停止の義務 | 〇あり | 〇あり | ×なし |
| 行える措置 | 処分の効力・執行・手続の続行の停止以外の措置も可能 | 処分の効力・執行・手続の続行の停止以外の措置のみ | |
| 内閣総理大臣の異議 | ×不可 | 〇可能 | |
あわせて読みたい

アイキャッチ-300x169.jpg)
行政法16-5:執行停止(行訴法)とは?わかりやすく解説|要件・手続・内閣総理大臣の異議まで完全対応!
行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 この記事はこんな人におすすめ 「執行停止」の仕組みや流れをイメージで理解したい方 行政事件訴訟法の条文を読んでも、具体的にどう…
📝 まとめ
- 原則として、審査請求中も処分の効力や執行は止まらない(執行不停止の原則)
- 重大な損害を防ぐ必要があるときには、執行停止が認められる
- 任意的な執行停止と義務的な執行停止がある
- 行政事件訴訟法との違いもおさえておくと得点源に!