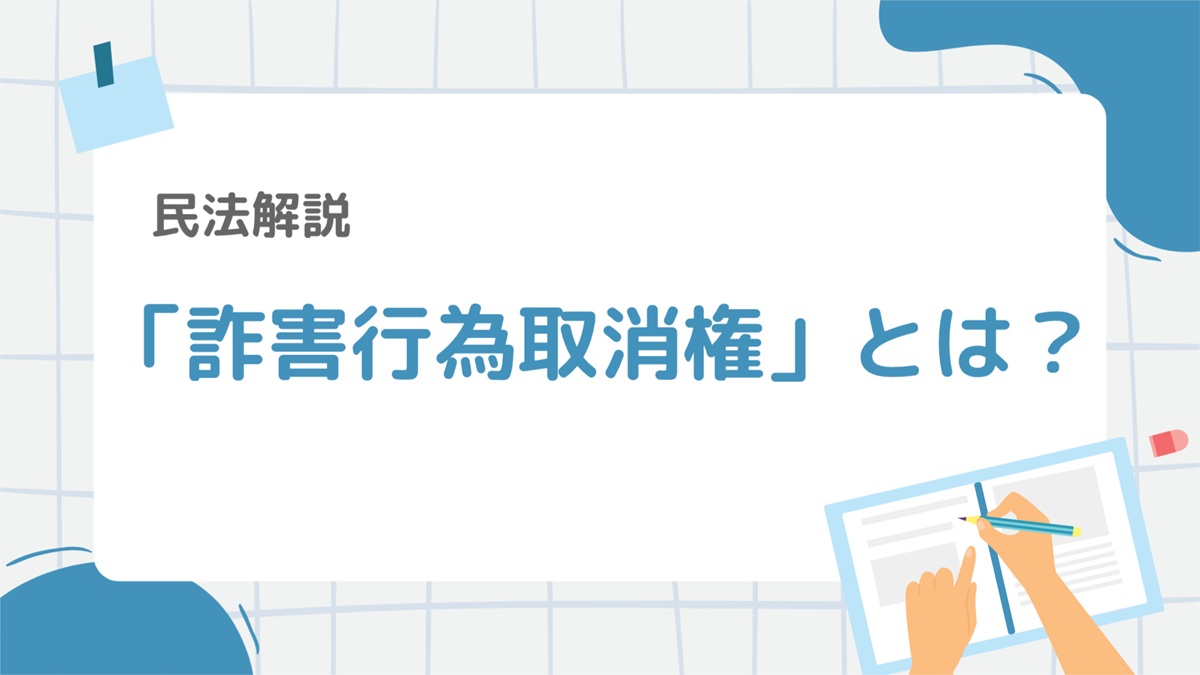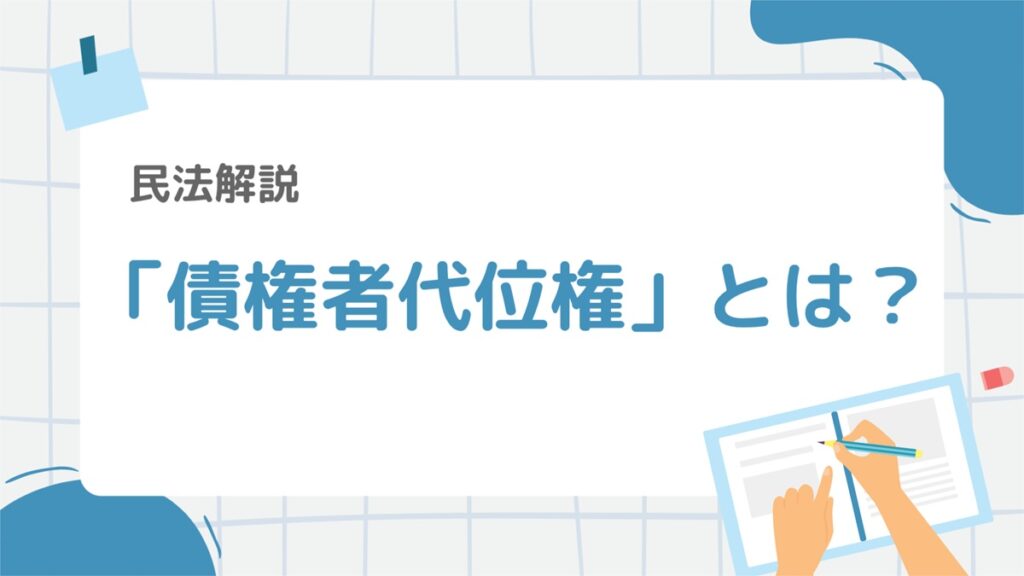- 詐害行為取消権が試験範囲に含まれている行政書士・司法書士・宅建などの受験生
- 民法の「債権総論」が苦手で、特に詐害行為取消権の要件がよくわからない方
- 判例や条文の要点もあわせて、効率的に理解したい方
詐害行為取消権とは?簡単に言うと…
詐害行為取消権(424条)は、債務者が自分の財産をわざと減らして(詐害行為)、債権者への支払いを逃れようとしたときに、その行為を取り消して財産を取り戻せるようにする制度です。
sequenceDiagram autonumber actor A actor B actor C A ->> B:被保全債権<br>100万円 B ->> C:贈与<br>100万円 note over B,C: 詐害行為 A -->> C:取消し
AさんはBさんに100万円を貸していました。しかしBさんは、Cさんにその100万円を贈与してしまい、自分の財産をなくして(無資力)しまいました。
このとき、AさんはBさんとCさんの間の贈与契約を「詐害行為」として裁判で取り消すことができます。
✅詐害行為取消権の目的
この制度の目的は、「債務者の責任財産(債務の支払いに使える財産)を守ること」です。
債務者が勝手に財産を減らしたら、債権者はお金を回収できません。それを防ぐための制度です。
詐害行為取消権の要件(使えるための条件)
詐害行為取消権を使うには、次の条件を満たす必要があります。
① 被保全債権が金銭債権であること(原則)
守りたい債権(被保全債権)は、原則として「金銭債権」でなければなりません。
ただし、特定物引渡請求権でも、債務者が目的物を処分してしまい、最終的に損害賠償になるような場合は、詐害行為取消の対象になります(最大判昭36.7.19)。
②被保全債権が詐害行為前に生じたものであること
詐害行為取消請求は、被保全債権が詐害行為が行われる「前」に成立したものである場合に限って認められます(424条3項)。1
したがって、詐害行為と主張される不動産の譲渡が債権成立前に行われた場合は、その登記が債権成立後にされたとしても、詐害行為取消請求をすることはできません。(最判昭55.1.24)。
③ 債権者を害する行為であること
詐害行為取消請求の対象となるのは、「債権者を害する」行為です(424条1項本文)。これは、債務者がその行為により無資力になることを意味します。
一部の債権者だけに担保を与える行為や、債務の消滅に関する行為は、原則として詐害行為に該当しませんが、債務者が支払不能の状態で、受益者と通謀し、他の債権者を害する意図をもって行われた場合には詐害行為に該当します(424条の3第1項)。2
④財産権を目的としない行為ではないこと
詐害行為取消請求の対象とは、「財産権を目的としない行為」に限られます(424条2項)。これは、詐害行為取消請求の目的が、債務者の責任財産の保全にあるためです。
たとえば、家族法上の行為が財産権を目的とするかどうかについて、次のような判断がされています。
■詐害行為取消請求の対象
- 対象となる
-
遺産分割協議(最判平11.6.11)
- 対象とならない
⑤債務者が「債権者を害することを知っていた」こと
詐害行為取消請求を行うには、債務者がその行為によって債権者を害することを知っていた必要があります(424条1項本文)。3
⑥受益者もその行為の時に「債権者を害すべき事実を知っていた」こと
詐害行為取消請求は、受益者がその行為の時に債権者を害する事実を知っていた場合に限って認められます(424条1項但書)。
⑦すべての転得者も、「債権者を害すべき事実を知っていた」こと
転得者4を相手とする場合、そのすべての転得者がそれぞれの転得時に債権者を害する事実を知っていたことが必要で、そのときに限り、詐害行為取消請求をすることができます(424条の5)。
詐害行為取消権の行使方法
詐害行為取消請求は、債権者代位権と違って、裁判所に対して請求します(424条1項本文)。
これは、他人間の法律行為を取消す重大な効果をもつため、第三者にも影響が及ぶことから、要件充足の有無について裁判所の判断が必要だからです。
出訴期間(いつまでに訴えればいい?)
このどちらか早い方までに訴えを起こさないと、取消請求はできなくなります。
誰を相手に訴えるのか?
詐害行為取消請求の訴えは、債務者ではなく、「受益者または転得者」を被告として提起する必要があります(424条の7第1項)。5
取り消しの効果
取消しの範囲
- 金銭の処分の場合
目的物が金銭のように可分のものである場合、自己の債権の額の限度においてのみ取り消すことができます(424条の8第1項) - 金銭以外の財産の処分の場合
処分の対象が不可分の一棟の建物などである場合は、その価額が債権額を超える場合であっても、債権者は、その行為の全部を取り消すことができます(最判昭30.10.11)
取消しの内容
債権者は原則として財産の返還を請求することができるが、返還が困難であるときは、その価額の償還を請求することができる(424条の6第1項・2項)。
債権者は原則として、財産の返還を請求することができますが、返還が困難な場合には、その価額の償還を請求することができます
取消しの効果
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者だけでなく、他のすべての債権者にも効力を生じます(425条)。
したがって、債権者が詐害行為として取消しを認められた場合でも、取り戻した財産について他の債権者に優先して弁済を受けることはできません。7
債権者代位権と詐害行為取消権の違い
| 債権者代位権 | 詐害行為取消権 | |
| 被保全債権 | ①原則として弁済期になること(423条2項) ②代位目的たる債権より前に成立したことは不要(最判昭33.7.15) | ①弁済期にあることは不要(大判大9.12.27) ②詐害行為の前に成立したこと(424条3項) |
| 行使方法 | 裁判外でも行使できる | 裁判上の行使(424条3項) |
| 期間制限 | なし | “債務者が債権者を害することを知って行為をしたこと”を知った時から2年、行為時から10年(426条) |
まとめ
詐害行為取消権は、債務者が故意に財産を減らして債権者に損害を与えるのを防ぐ大切な制度です。
民法の債権総論の中でも頻出テーマなので、条文や判例とあわせて確実に理解しておきましょう。
- 重要判例:詐害行為の前に債権が成立していれば、その後債権が譲渡されたとしても、譲受人は、詐害行為取消権を行使することができる(大判大12.7.10) ↩︎
- 重要判例:弁済につき詐害行為取消請求が認められた場合、取消請求権者からの返還請求に対して、自己の債権に係る按分額(弁済を受けた額を取消請求権者の債権額と自己の債権額とで按分した額)の支払いを拒むことはできない(最判昭46.11.19) ↩︎
- 重要判例:債務者・転得者の悪意については、債権者側に立証責任があるが(債務者の悪意につき大判昭13.3.11)、受益者の善意については、受益者側に立証責任がある(最判昭37.3.6) ↩︎
- 転得者:物や権利を譲り受けた者からさらに譲り受けた者のこと ↩︎
- 参考:債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起した時は、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない(424条の7第2項)。 ↩︎
- 重要判例:債権者が金銭の返還を受けた場合、取消債権者は、その金銭を他の債権者に分配する義務を負わない(最判昭37.10.9) ↩︎
- 重要判例:詐害行為取消請求は、すべての債権者の利益のために債務者の責任財産を保全する目的において行使されるべき権利であるから、債権者が複数存在するときであっても、取消債権者は、その有する債権額全額について取り消すことができる(大判昭8.2.3) ↩︎