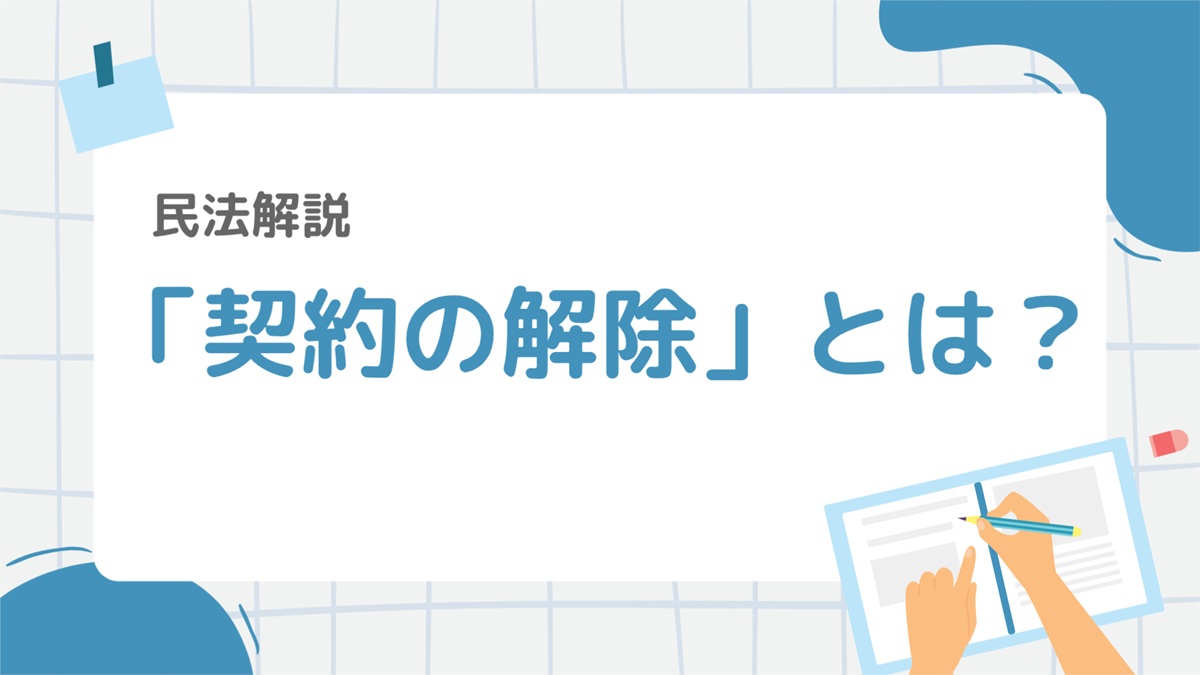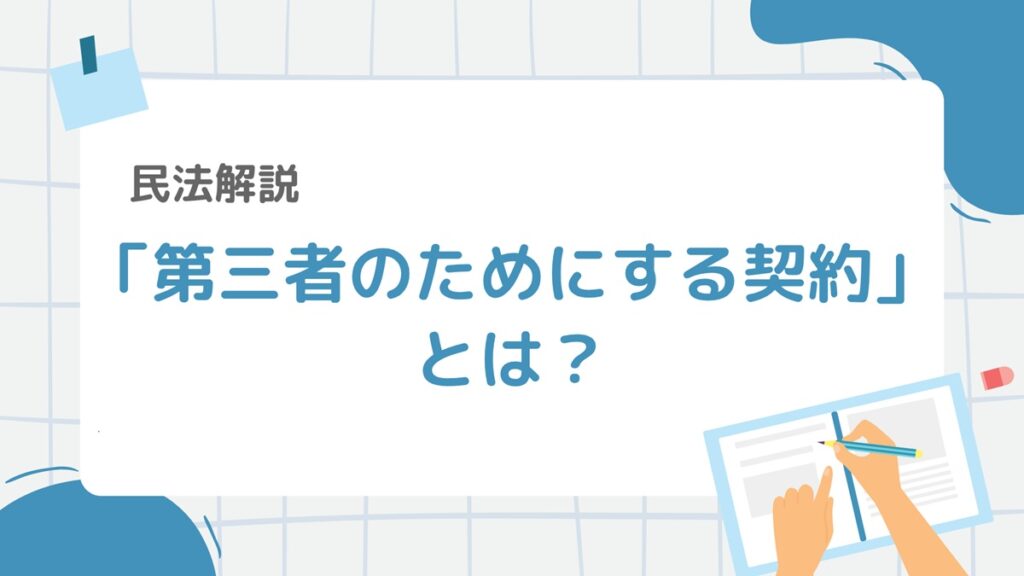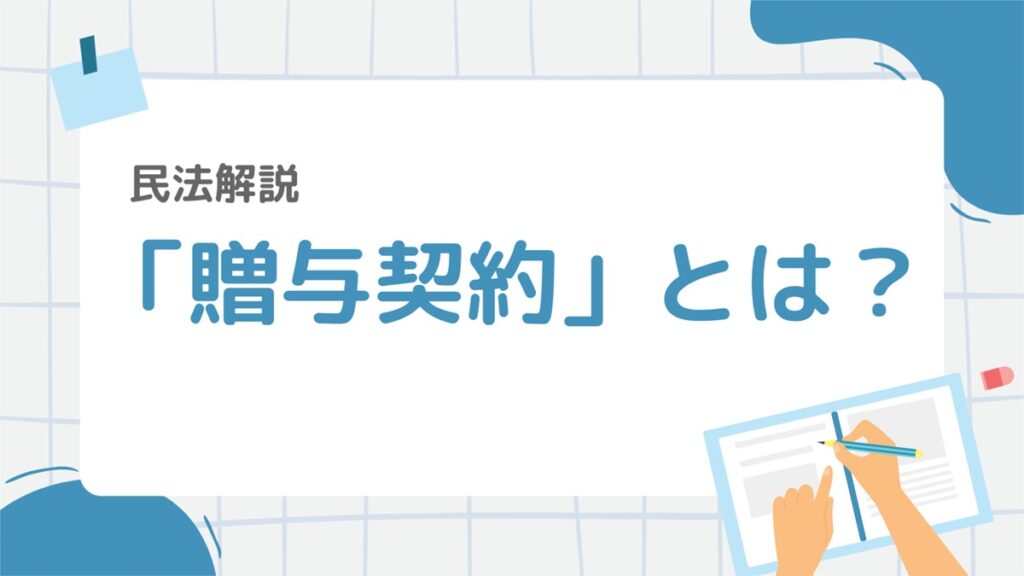- 契約を解除できる条件や方法を知りたい人
- 行政書士試験の民法(契約)分野をしっかり理解したい人
- 契約トラブルを未然に防ぎたいと考えている人
契約の解除とは?わかりやすく解説
契約の解除とは、契約が成立した後に一定の理由が生じた場合に、一方的な意思表示によって契約の効力を消滅させることをいいます。
これは、契約によって生じる不利益を救済するために認められている制度です。
解除の要件
契約を解除するためには、原則として「催告(さいこく)」という手続きが必要ですが、状況によっては催告なしでも解除できるケースもあります。
原則:催告による解除(民法541条本文)
まず、解除をするには、相手に「相当の期間を定めて履行を催告」する必要があります。
それでも相手が義務を果たさない場合に、はじめて契約を解除できるのが原則です(541条本文)1
🔵ただし注意点
催告後でも、債務不履行の内容がごく軽微なものであれば、解除できない場合もあります(541条但書)。
例外:催告なしで解除できる場合(無催告解除:民法542条)
次のような場合には、催告なしで即座に契約を解除することができます(542条)
- 債務が履行不能の場合2
- 債務者が債務の履行を拒絶する意思を明確にした場合
- 債務の一部が履行不能または債務者が債務の一部の履行を拒絶した場合において、残存部分のみでは契約をした目的を達成できないとき
- 特定の日時または一定の期間内において履行しなければ、契約をした目的を達成できないとき
- 債務者が債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかな場合
契約解除の手続
契約の解除は、相手方に対して解除する意思表示するだけで成立します(540条1項)。
また、一度行った解除の意思表示は、撤回できません(540条2項)。ので、慎重に判断しましょう。
さらに、契約当事者の一方が複数いる場合、解除は全員から、または全員に対してのみ行うことができます(544条1項)。そのため、解除権が当事者のうちの1人について消滅した場合、他の当事者についても消滅することになります(544条2項)。これを解除権の不可分性といいます。
契約解除の効果とは?
契約を解除すると、契約当事者は原状回復義務を負うことになります(545条1項本文)。34これは、契約がなかった状態に戻すため、受け取ったものを返還する義務です。
ただし、原状回復義務によって第三者の権利を害することはできないとされています(545条1項但書)。
たとえば、解除前に第三者が正当に権利を取得していた場合には、その権利を無視することはできません。
まとめ
契約の解除は、契約上のリスクを回避するためにとても重要な制度です。
解除できる条件や手続、効果をしっかり理解しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます!
- 重要判例:期間を定めずに催告をした場合でも、催告後相当な期間が経過した後に解除すれば、その解除は有効である(大判昭2.2.2) ↩︎
- 重要判例:履行不能が確実となった場合、弁済期前であっても、解除をすることができる(大判大15.11.25) ↩︎
- 重要判例:特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合における売主の原状回復義務についても、保証の責任を負う(最大判昭40.6.30) ↩︎
- 重要判例:売買契約が解除された場合、目的物の引渡しを受けていた買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間、目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負い、これは、全部他人物売買において、売主が目的物の所有権を取得して、買主に移転することができず、当該契約が解除された場合も同様である(最判昭51.2.13) ↩︎