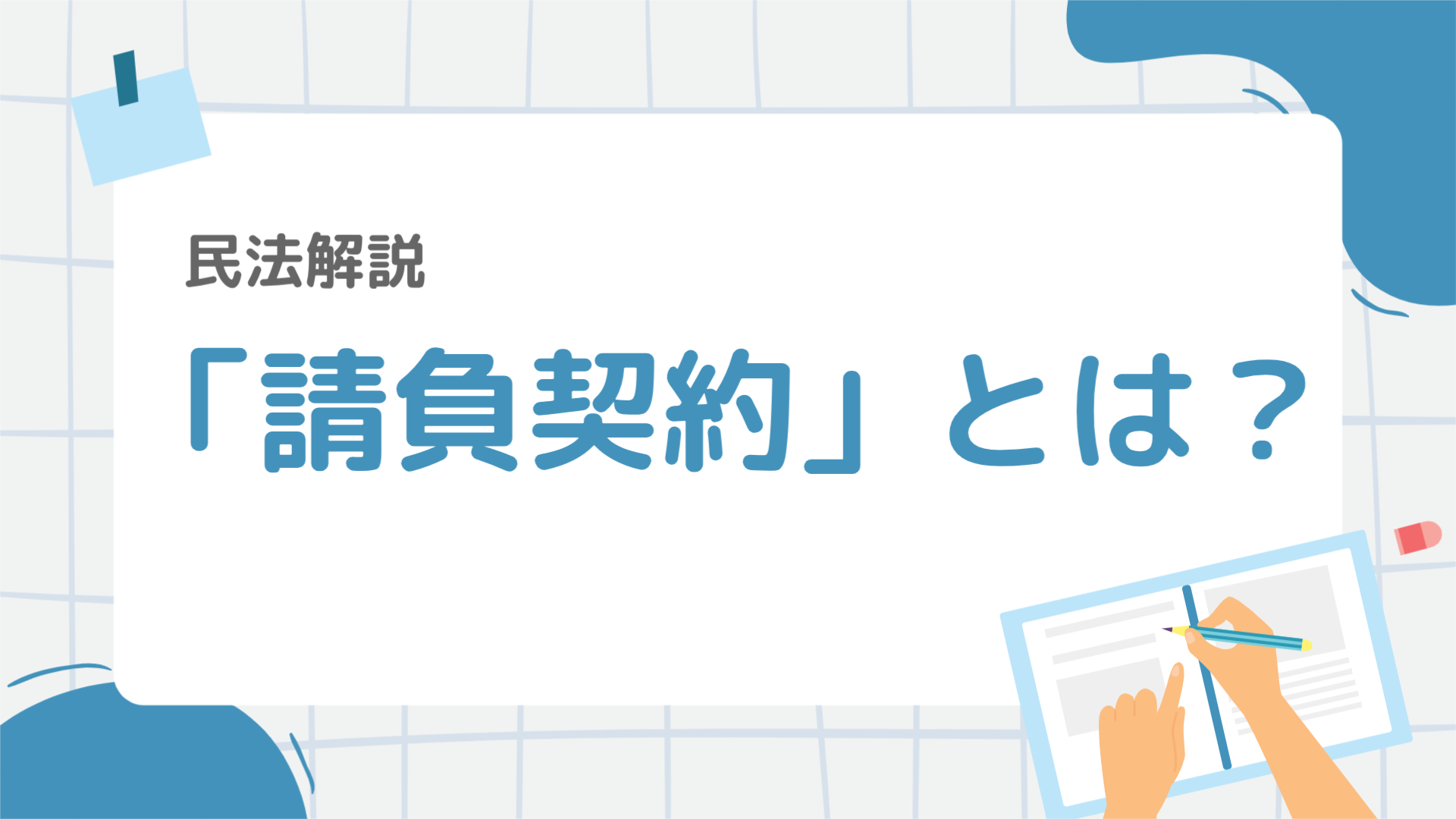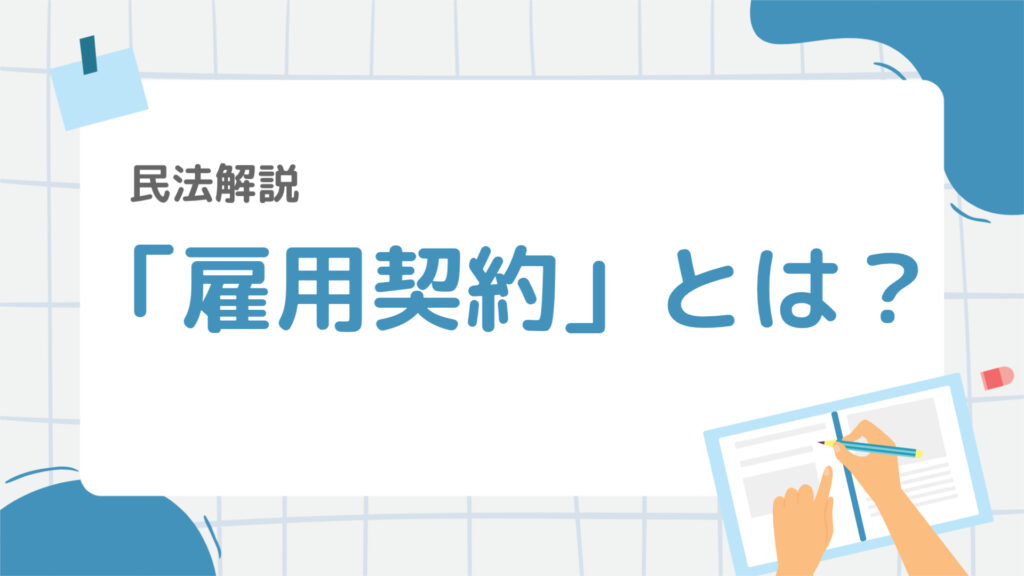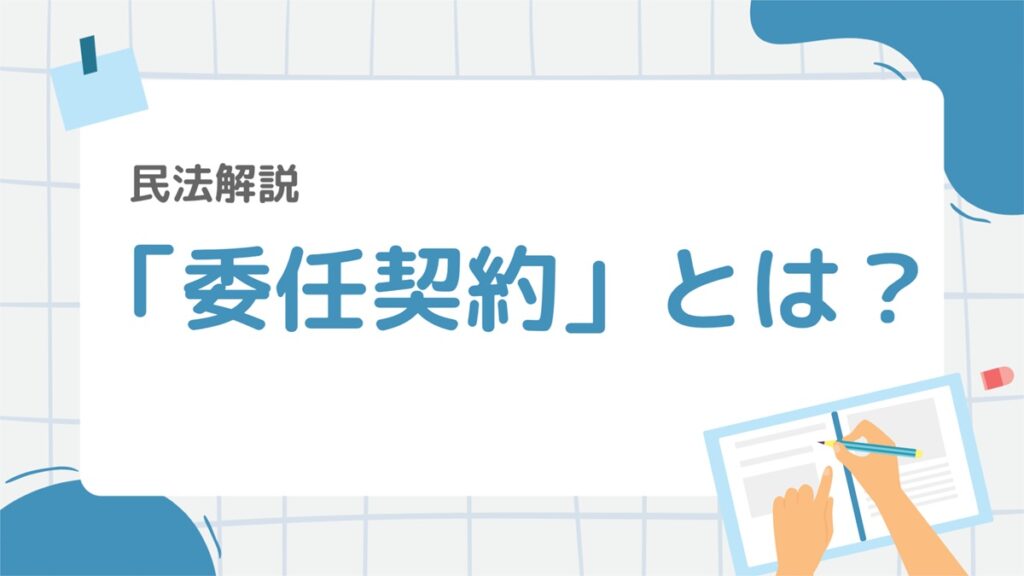請負契約とは?【民法第632条】
--- config: theme: neutral --- flowchart LR A_注文者 B_請負人 A_注文者 ------>|報酬| B_請負人 B_請負人 ------>|仕事の完成 + 引渡し| A_注文者
AはBに対して「代金2,000万円で自分が所有する土地に建物を建ててほしい」との申込みし、Bは「その仕事を請け負います」と、これを承諾した。
請負契約とは、「ある仕事を完成させること」を約束した請負人と、その成果に対して報酬を支払うことを約束した注文者との間で成立する契約です。
たとえば、建物の建築やウェブサイトの制作など、「成果物が存在するタイプの契約」がこれに当たります。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法632条
請負契約の特徴|雇用契約との違いは?
請負契約は、請負人が注文者から独立して仕事を完成させるという点で、雇用契約とは異なります。
雇用契約では、労働者が使用者の指揮命令のもとで労務を提供しますが、請負契約では、仕事の完成という「結果」に対して報酬が支払われるため、成果主義的な性質を持っています。
請負契約における報酬の支払い時期
請負契約の報酬は、仕事の目的物の引渡と同時に支払うわなければなりません(633条本文)。この契約では、目的物の引渡しと報酬の支払いの同時履行が原則です。12
下請負とは?
下請負とは、元の請負人が、自分が請け負った仕事の全部または一部を、さらに別の人(下請負人)に請け負わせることをいいます。
- 下請負が原則として認められるのは、特別なスキルや個人の能力に依存しない仕事の場合です。
- 下請負人は「元請負人の履行補助者」となるため、下請負人の過失による損害も元請負人が責任を負う点に注意しましょう。3
請負契約における目的物の所有権は誰のもの?
所有権の帰属は、材料を誰が提供したかで変わります。
- 注文者が材料の全部または主要部分を提供した場合
目的物の所有権は原始的に注文者に帰属する(大判昭7.5.9) - 請負人が材料の全部または主要部分を提供した場合
請負人の担保責任
売主と同様に、請負人にも担保責任が課されます。
具体的には、仕事の成果物に瑕疵(欠陥)があった場合などに、修補・損害賠償などの責任を負います。
※売主の担保責任の規定(562条~564条)は、請負契約にも適用される(559条)、つまり請負人は売主と同様の担保責任を負う。
請負契約の解除|注文者が解除できる場合
🔹仕事が未完成の間の解除【民法第641条】
注文者は、仕事が完成していない間であれば、損害を賠償することでいつでも契約を解除できます(641条)。5
これは、注文者にとって不要になった仕事を無理に続けさせられないようにするための制度です。
🔹注文者の破産による解除【民法第624条】
注文者が破産手続開始決定を受けた場合、以下のとおり契約解除が可能です。
まとめ
請負契約は、行政書士試験の民法分野でも頻出のテーマです。
雇用契約との違いや報酬・所有権の扱い、担保責任、解除の可否など、ポイントを押さえておきましょう!
- 重要判例:注文者は、契約内容の不適合の程度や各契約当事者の交渉態度等にかんがみ、信義則に反すると認められるときを除き、請負人から契約内容不適合を理由とする損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払いを拒むことが出来る(最判平9.2.14) ↩︎
- 注文者は、契約内容不適合を理由とする損害賠償請求権と報酬請求権を相殺することもできる(最判昭53.9.21) ↩︎
- 下請禁止特約がなされている場合でも、下請負が当然に無効となるわけではないが、下請負をすること自体が債務不履行となるから、元請負人は下請負をしたことにより生じたすべての事由について損害賠償責任を負う(大判明45.3.16) ↩︎
- 重要判例:建物建築工事の注文者と元請負人との間に、請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合、者請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別な合意があるなど、特段の事情の無い限り、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する(最判平5.10.19) ↩︎
- 参考:工事内容が可分な工事請負契約において、仕事の完成前に請負契約を解除する場合、請負人がすでにした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分は仕事の完成とみなされるから(634条前段2号)、未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎない。 ↩︎