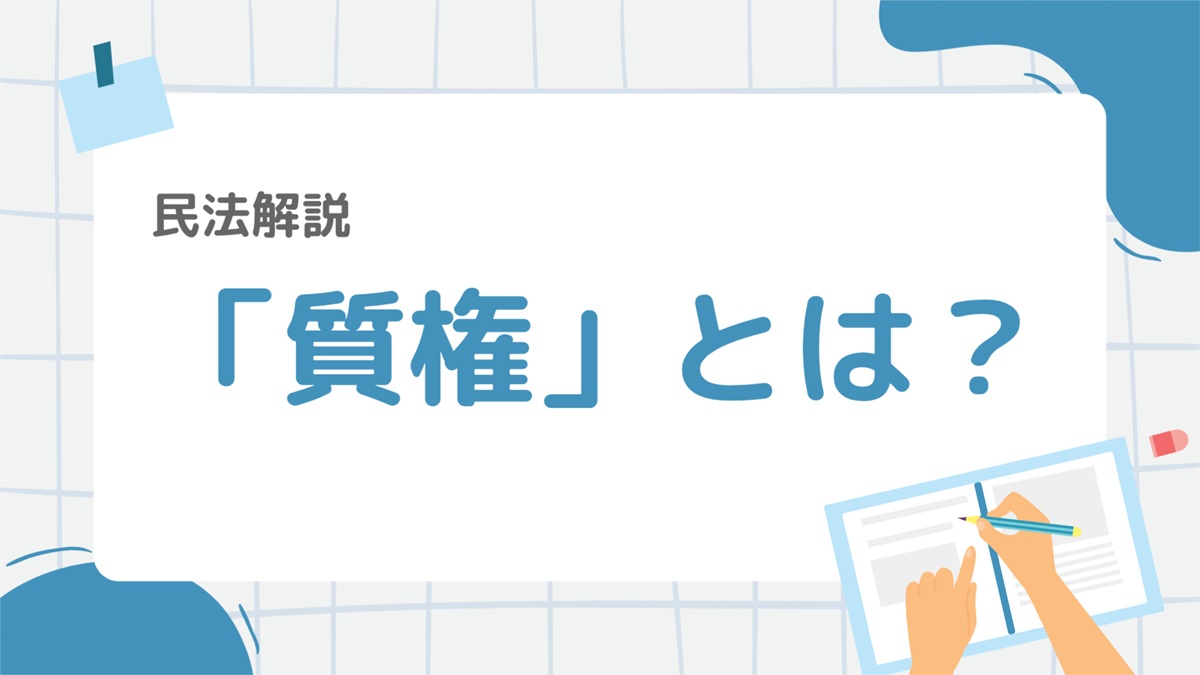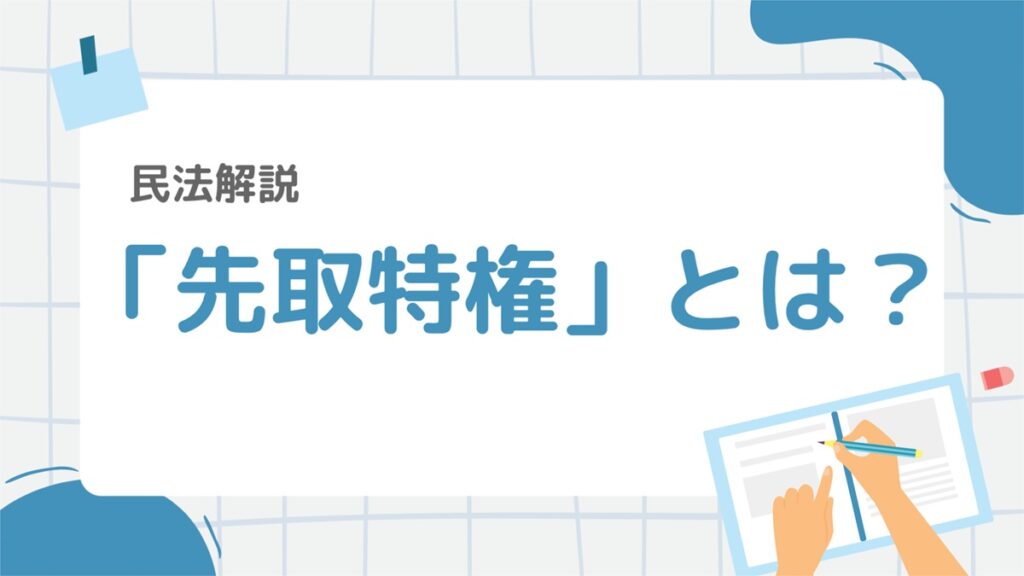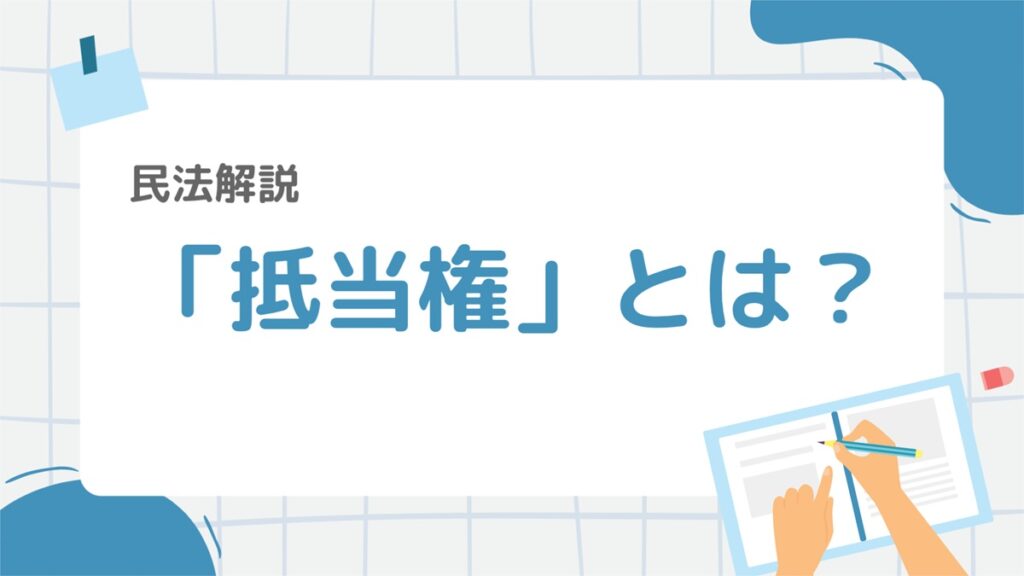- 「質権ってどんな権利?イメージがわかない」と感じている行政書士試験の受験生
- 担保物権の基本をしっかり理解したい初学者の方
- 民法の条文の意味を、噛み砕いて理解したい方
質権とは?

sequenceDiagram autonumber actor A_債務者_質権設定者 actor B_債権者_質権者 A_債務者_質権設定者 ->> B_債権者_質権者:質権設定契約 A_債務者_質権設定者 ->> B_債権者_質権者:時計の引渡し B_債権者_質権者 ->> A_債務者_質権設定者:貸金債権 B_債権者_質権者 --> A所有の時計:質権
Aは、Bからお金を借りる際、その貸金債権の担保として、自分の所有する時計に質権を設定する契約を結びました。そして、その契約に基づいて、Aは時計をBに引き渡しました。
質権とは、債権の担保として、債務者または第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる権利です(342条)。
もし弁済がされなかった場合、質権者はその物を競売(けいばい)にかけ、他の債権者よりも優先的に自分の貸したお金を回収することができます。
たとえば、友人にお金を貸す代わりに高価な腕時計を預かった場合、その腕時計が質物となり、これが質権のイメージです。
質権の種類は3つあります
質権には、目的物の種類によって、①動産質・②不動産質・③権利質1の3種類があります。
- 動産質…時計や宝石などの「動産」が対象
- 不動産質…土地や建物などの「不動産」が対象(現在ではほとんど使われません)
- 権利質…債権や株式など「権利」が対象
| 動産質 | 不動産質 | 権利質 | |
| 対抗要件 | 占有の継続2(352条) | 当期(177条) | 設定者からの通知または第三債務者の承諾(364条、467条) |
| 存続期間 | なし | 10年(360条) | なし |
| 使用収益権 | 原則無し(350条、298条2項) | あり(360条) | なし |
| 果実収取権 | 収取して他の債権者に優先して債権の弁済に充当可(350条、297条) | 当然に収取可 (356条) | – |
| 必要費償還請求権 | 全額請求可(350条、299条1項) | 原則請求不可 (357条) | – |
| 利息請求 | 可能 (346条) | 不可(358条、359条) | 可能 (346条) |
| 優先弁済 | 目的物の換価のほか、簡易な弁済充当が可能(354条) | 目的物の換価のみ可能 | 目的債権の換価のほか、直接取立て可能(366条1項) |
質権の設定方法|引き渡しが必要
質権は、債権者に目的物を引き渡すことで成立します(344条)。
ただし、債権者は質権設定者に代わりに質物を占有させることができません(345条)。そのため、占有改定はここで言う「引渡し」には該当しません。
質権の効力
どんな範囲まで守ってくれる?被担保債権の範囲
質権は、特別な取り決めがない限り、以下のような費用・損害も含めて担保してくれます(346条)。
- 元本
- 利息
- 違約金
- 質権の実行の費用
- 質物の保存の費用
- 債務の不履行または質物の隠れた瑕疵によって生じた損害賠償
つまり、単に元本だけでなく、回収にかかる関連費用もしっかりカバーできるのが質権の強みです。
質物を手元に置ける力「留置的効力」
質権者は、被担保債権の弁済を受けるまで、質物を留置することができます(347条本文)。
ただし、この留置的効力は、質権者よりも優先権を有する債権者に対しては対抗することができません(347条但書)。
質物を売って回収「優先弁済的効力」
返済がない場合、質物は競売にかけられます。
債権者は、競売によって目的物を換価し、優先的に弁済を受けることができます。さらに、目的物が生み出す果実からも優先弁済を受けることが可能です(350条、297条)。
他の担保に使える?「転質」のルール
転質とは、質権者が質物をさらに別の債権の担保として質入れすることを指します。
質権者は、質権の存続期間内であれば、自らの責任において質物を転質することが可能です(348条前段)。3
ただし、転質によって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、質権者が責任を負います(348条後段)。
質物をそのまま取得する「流質契約」はOK?
質権設定者は、設定行為または債務の弁済期前の契約の時点で、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることや、法律で定められた方法以外で質物を処分させることを約束する「流質契約」をすることはできません(349条後段)。
ただし、債務の弁済期を過ぎた後の契約であれば、このような約定も認められます。
商法では特例あり!流質契約が自由にできる?
✅あわせてチェック
商法では、商行為の特則が定められおり、流質契約も認められています。👉商行為の特則(流質契約の自由)
✅まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 質権とは | 担保として物を預かり、返済されなければ優先して弁済を受ける権利 |
| 設定方法 | 質物の引き渡しが必要(占有がポイント) |
| 主な効力 | 留置・優先弁済・転質の可否 |
| 注意点 | 弁済期前の流質契約は原則NG(商取引ではOK) |