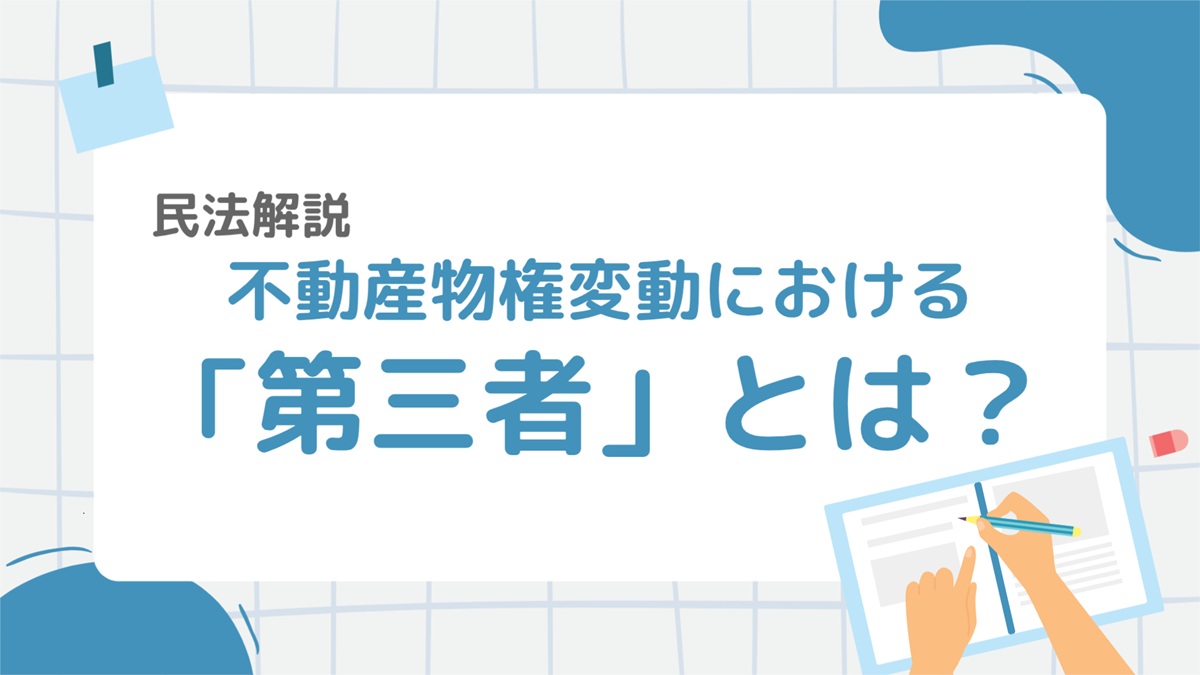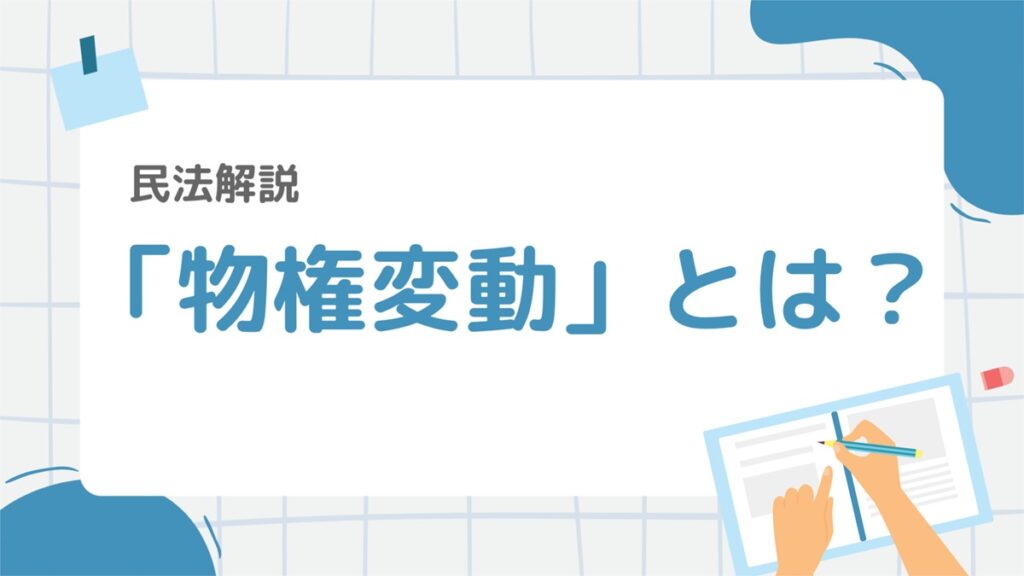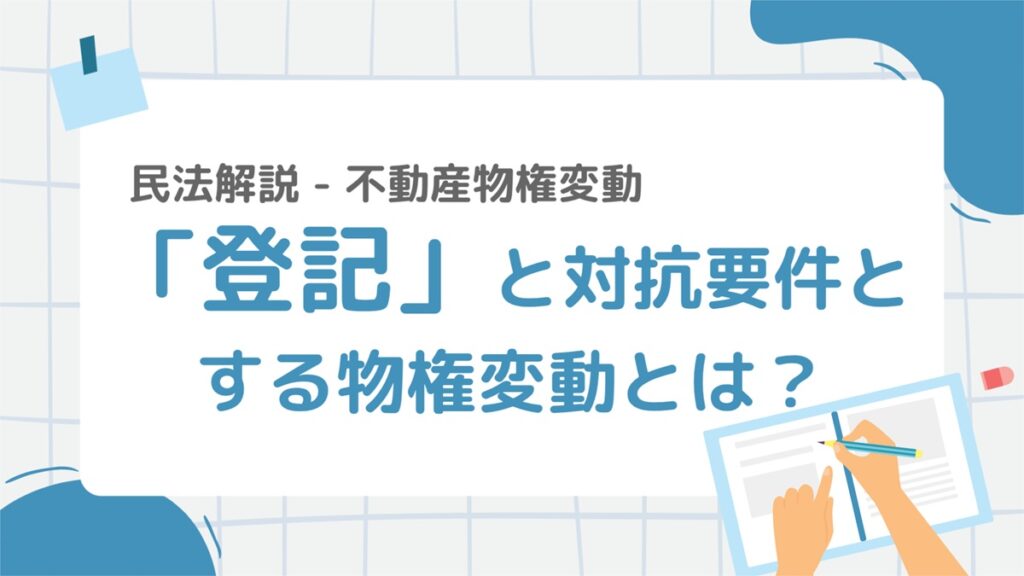- 「不動産の所有権って登記がないと無効になるの?」と疑問に思っている方
- 民法177条の「第三者」の意味がよくわからない受験生
- 行政書士試験対策として、不動産の物権変動の基礎をしっかり理解したい方
- 二重譲渡の事例において、どちらが所有者になるかを判例ベースで知りたい方
📘不動産の物権変動とは?
民法177条と「第三者」の意味をわかりやすく解説
◆「対抗要件」とは何か?
不動産を売買すると、買主がその物件の所有者になります。しかし、ただ売買契約をしただけでは、他人にその事実を主張(=対抗)することはできません。
177条では、「不動産の物権の取得・喪失・変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない」と定めています。
つまり、所有権をしっかり主張したいなら登記が必要ということです。
🧩事例で考える:登記のない買主 vs 登記をした買主
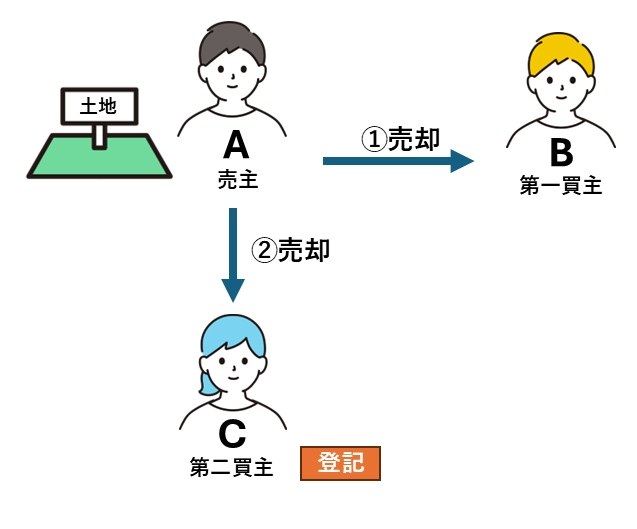
Aはまず、ある土地をBに売りました(ただし、Bへの所有権移転登記は行っていませんでした)。
その後、Aは同じ土地を今度はCにも売り、Cには所有権移転登記をしました。
このように、同じ土地を2人に売ってしまう「二重譲渡」が起きた場合、誰が最終的な所有者になるのでしょうか?
答えは、登記を先にしたCです。
法律上は、一物一権主義の原則(1つの物に1つの権利)により、所有者は1人に決まります。
登記をしない限り、BはCに対して自分が所有者だと主張することができません。1
👤民法177条の「第三者」とは?
ここでポイントになるのが「第三者」という言葉です。
登記をしていないと主張できない「第三者」とは、いったい誰のことを指すのでしょうか?
◆①客観的要件(法律上の定義)
判例(大連判明41.12.15)によると、「第三者」とは、
当事者若しくはその包括承継人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪・変更の登記の欠缺2を主張する正当の利益を有する者のことです。
つまり、自分の権利を守るために「登記の欠如」を主張できる立場の人が「第三者」になります。
✅「第三者」に当たる人(主張できる)
- 二重譲渡の譲受人
- 対抗要件を具備した賃借人(最判昭49.3.19)
- 差押債権者(最判昭39.3.6)
❌「第三者」に当たらない人(主張できない)
- 不法占有者(最判昭25.12.19)
- 無権利者(最判昭34.2.12)
- 転々譲渡の後主・前主の関係にある者(最判昭39.2.13)
- 譲渡人の相続人3
◆②主観的要件(善意・悪意は関係ない?)
「第三者」に当たるかどうかは、その人が善意であろうと悪意であろうと関係ありません(最判昭32.9.19)。
つまり、例のCが「実はAがBに土地を売っていたことを知っていた」としても、Cが登記をしていれば勝ち、Bは対抗できません。
❗ただし「背信的悪意者」は除かれる
とはいえ、極端に不誠実な行動をした人は例外です。
判例では、「信義に反する行動」をした人は「第三者」には当たらないとしています。これを「背信的悪意者」と呼び、対抗要件を備えていなくても物権変動があったことを主張(対抗)できるとされています。4
背信的悪意者とされる例(登記があっても対抗不可)
- 詐欺または強迫によって登記申請を妨害した者(不動産登記法5条1項)
- 復讐目的で買い受けた者(最判昭36.4.27)
- 登記のない第一買主に高値で売りつけようとして買い受けた者(最判昭43.8.2)
- 第一譲渡の代理人であった者(最判昭43.11.15)
このような人たちは、不誠実な行動が原因で「第三者」としての保護を受けられません。
📝まとめ|不動産取引では「登記」が命!
不動産の売買では、登記がなければ第三者に所有権を主張できません。
「第三者」に当たる人にはしっかり登記をしておく必要がありますし、「背信的悪意者」と判断されないよう誠実な取引が重要です。
行政書士試験でもよく出題されるこのテーマ、まずは「第三者」の定義と例外をしっかり押さえておきましょう。
物権変動インデックス
- 不動産の物権変動
- 動産の物権変動