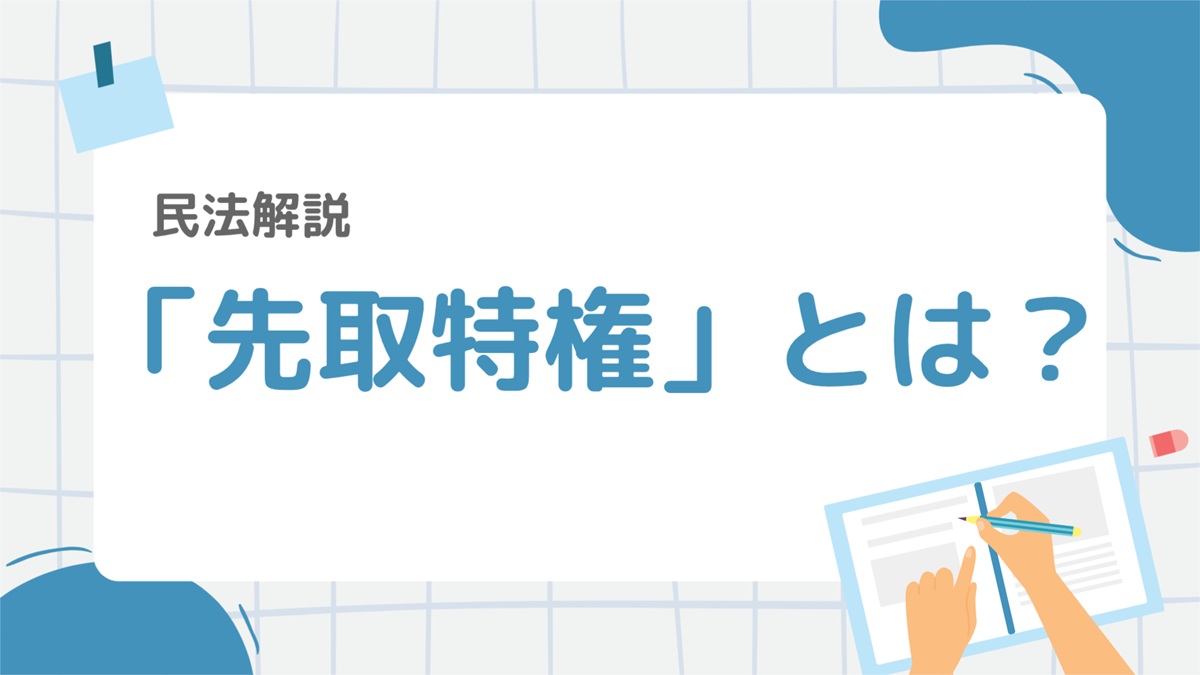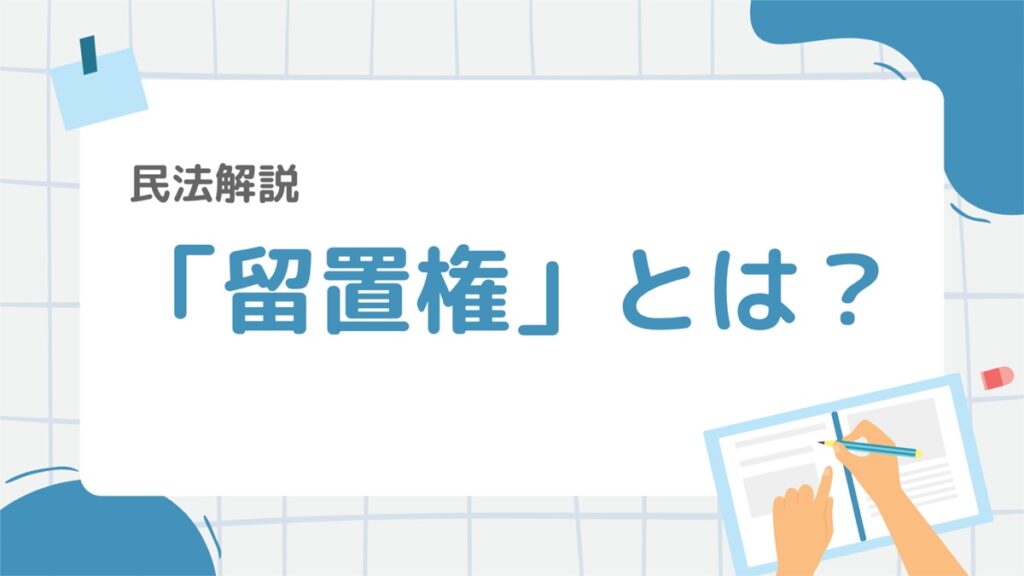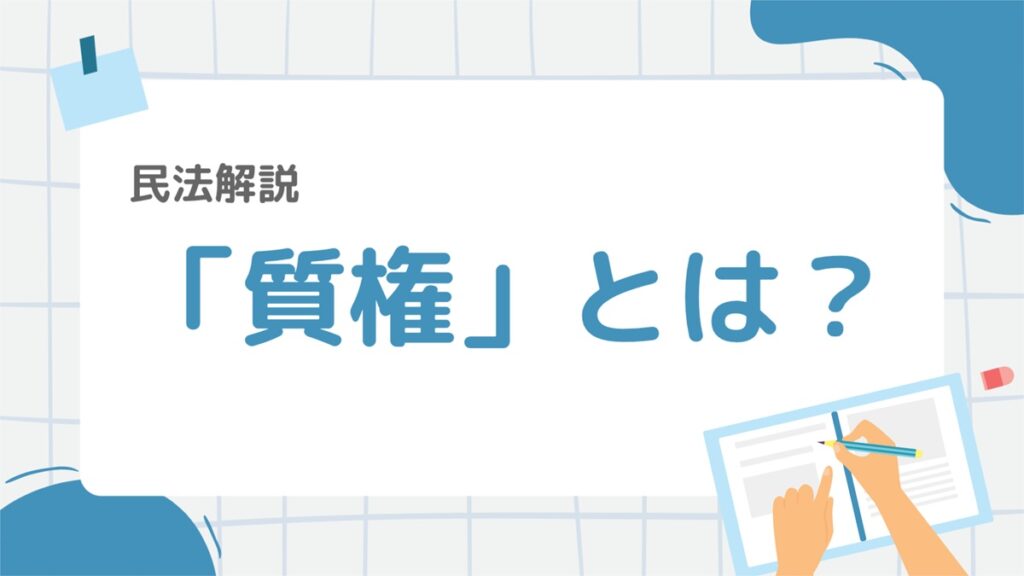- 「先取特権って何?」という初学者の方
- 民法の担保物権に苦手意識がある方
- 行政書士試験に向けて効率的にポイントを押さえたい方
- 先取特権の種類や具体例を整理したい方
先取特権とは?|他の債権者より優先して支払ってもらえる権利
flowchart LR
A("A<br>債務者<br>資金10万円")
B("B<br>債権者<br>先取特権")
銀行
B -->|給料債権_10万円| A
銀行 -->|貸金債権_90万円| AAは、製造業を営んでおり、Bをパートとして雇っていました。
しかし経営が行き詰まったため、Bに対する今月分の給料10万円を支払っていませんでした。
また、Aは銀行から90万円を借りており、その返済も滞っています。
現在、Aの手元にある資金はわずか10万円だけです。
通常、債務者が複数の債権者から借金をしていて、その財産だけでは全員に満額返済できない場合、債権者は平等に財産を分け合うことになります。これを「債権者平等の原則」といいます。
しかし、中には生活に直結するような債権もあります。たとえば、1か月分の給料(賃金債権)などです。
例:給料債権の優先例
Bさん:債務者から給料10万円をもらっていない
銀行:債務者に90万円を貸している
→ 債務者の財産が10万円しかない場合…
本来なら、Bは1万円、銀行は9万円を受け取るのが原則です。
しかしBの生活が困ってしまいます。
そこで登場するのが「先取特権」。
これは、法律上特別に守られた債権者が、他の債権者よりも優先して弁済を受けられる権利のことです(303条)。
上の例では、Bさんが銀行よりも優先して、全額10万円を受け取ることができます。

先取特権の種類|3つのパターンに分類
先取特権は、対象となる財産の種類によって、以下の3つに分類されます。
①一般先取特権
一般先取特権の被担保債権には、次の4種類があります。(306条)。
- 共益の費用
- 雇用関係
- 葬式の費用
- 日用品の供給
これらの債権が小口のものに限定されている理由は、一般先取特権が債務者の総財産を対象とする担保物件であり、公示の制度もないため、大きな債権を担保すると他の債権者との公平を害してしまうからです。
②動産先取特権
以下のような場合に生じた債権を持つ者は、債務者の特定の動産について先取特権を有します(311条)。1
なお、動産先取特権は、債務者がその目的である動産を第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができません(333条)。2
③不動産先取特権
不動産の保存・工事・売買によって生じた債権を持つ者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有します(325条)。
先取特権の効力とは?
先取特権を持つことで、次のような法律上の力が発生します。
①優先弁債権
先取特権の最も重要な効力は優先弁済権です。これは、目的物を強制的に換価し、他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利を指します。3
②物上代位
先取特権は、目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができます(304条1項本文)。これを物上代位といいます。
ただし、物上代位を行うためには、払渡しや引渡しがされる前に差押えをしなければなりません(304条1項但書)。4
まとめ|先取特権は「特別に守られた債権者」の優先権
先取特権は、「誰を優先的に守るべきか」を法律が定めた制度です。
行政書士試験でも、
- 種類ごとの違い
- 優先弁済や物上代位のルール
などがよく問われるポイントなので、しっかり理解しておきましょう。
- 重要判例:動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、買主がその動産を用いて第三者のために請負工事を行った場合であっても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事内容に照らして、請負代金債権の全部または一部をもって転売代金債権と同視するに足りる特段の事情が認められるときは、動産の売主はその請負代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(最決平10.12.18) ↩︎
- 重要判例:動産売買先取特権の存在する動産が譲渡担保権の目的である集合物の構成部分となった場合、譲渡担保権者は「第三取得者」に該当する(最判昭62.11.10) ↩︎
- 参考:不動産賃貸の先取特権は、動産売買の先取特権に優先する(330条1項1号・3号) ↩︎
- 重要判例:動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債券が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後は、自ら目的債券を差し押さえて物上代位権を行使することができない(最判平17.2.22) ↩︎