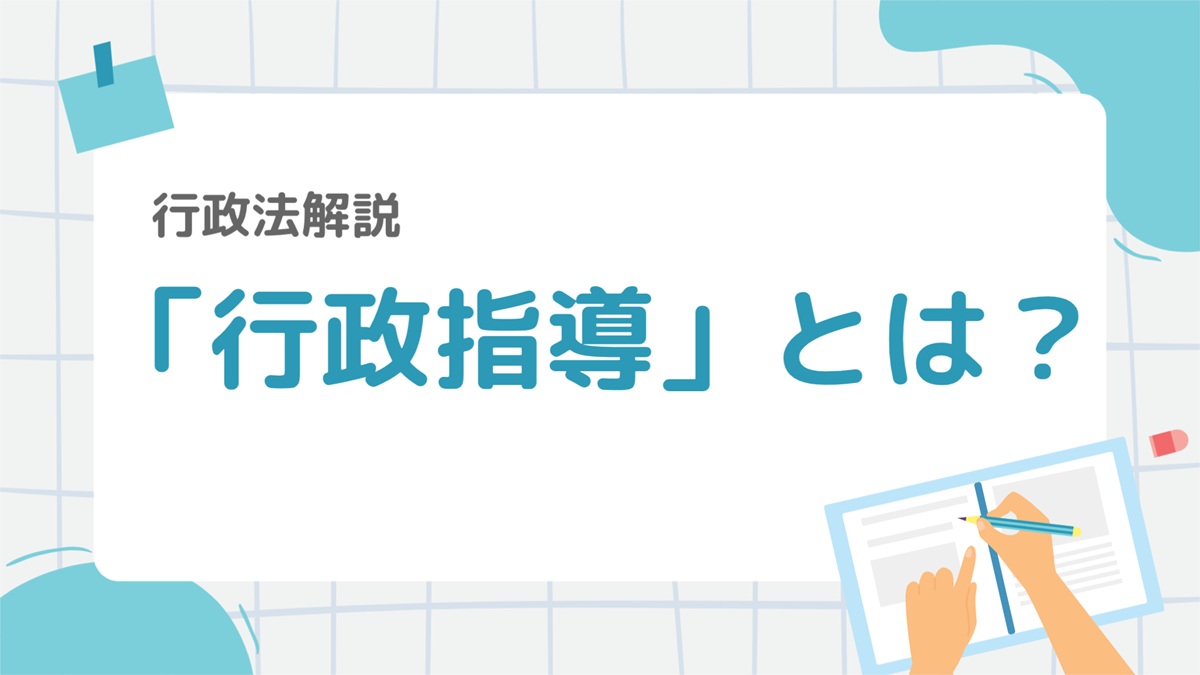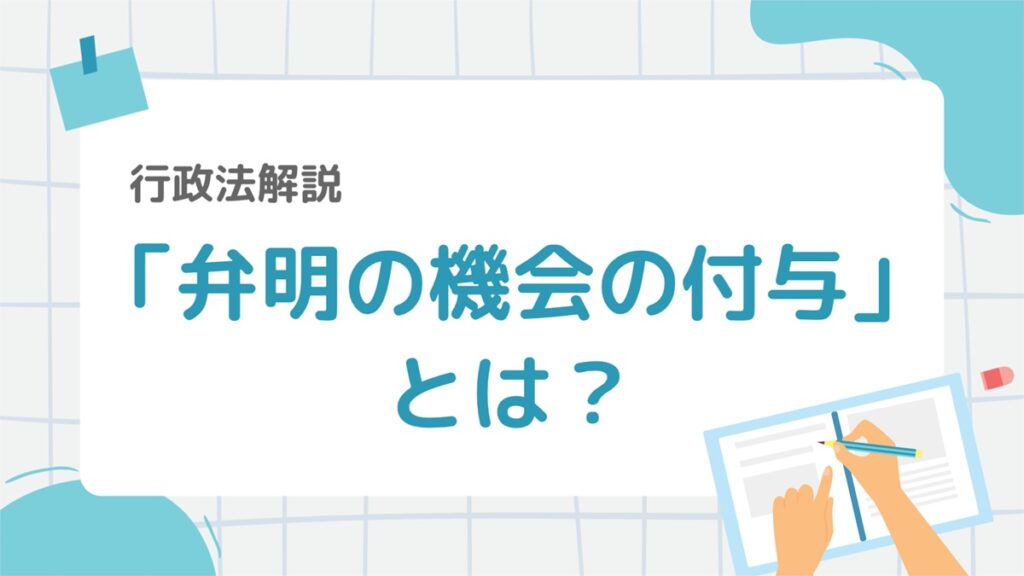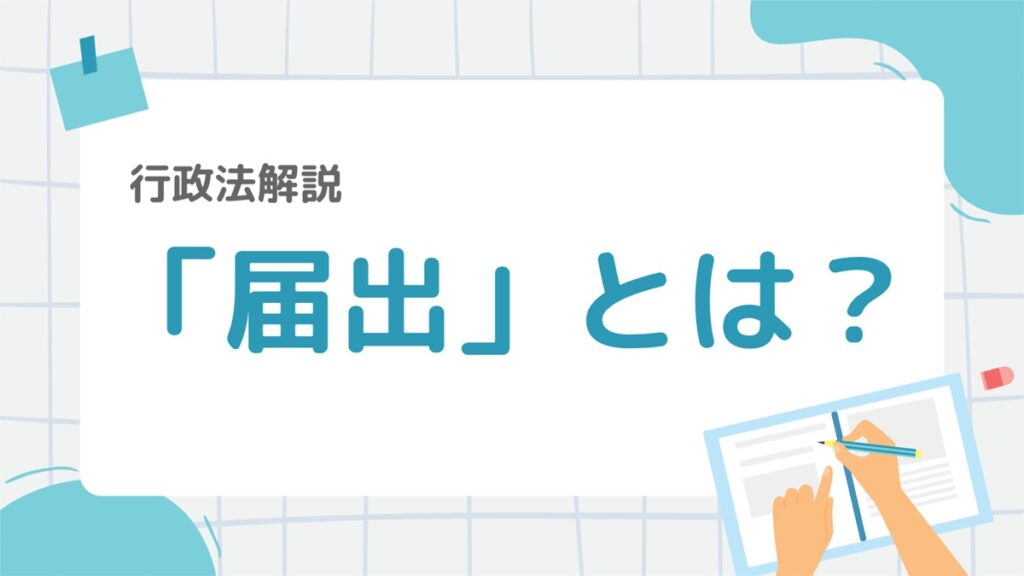- 行政書士試験の「行政法」対策として、行政指導の内容をしっかり理解したい方
- 「申請の拒否」や「許認可の保留」が問題になるケースを正しく押さえたい方
- 行政手続法の条文に対応したポイントを整理して覚えたい方
行政指導とは?行政手続法での意味と目的
行政指導とは、行政機関が法律に基づく処分ではなく、一定の目的を達成するために国民に対して行う「お願い」や「アドバイス」などの行為をいいます。
行政手続法では、次のように定義されています。
行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
行政手続法2条6号
行政指導に関する手続ルール
行政指導の一般原則
行政指導は、本来であれば行政行為(=法律に基づく義務づけ)として行うべきものを、法律の根拠なしに行うという問題点がありました。
そのため、次のようなルールが定められています。(32条1項)。
- 行政機関は、自分の任務または掌握事務範囲を超えて行政指導をしてはならない
- 行政指導の内容は、相手方の任意の協力によってのみ実現されること
つまり、行政指導はあくまでも「強制力のないお願い」である点が重要です。
申請に関連する行政指導
例えば、生活保護を申請した人に対して「親族に頼れませんか?」と行政指導したうえで、申請書を受理しない…といったケース。これは重大な人権侵害にもつながります。
このような問題を防ぐため、以下のルールが定められています。
なお、実際上は行政指導自体の違法性が争われるのではなく、行政指導をしている間、申請によって求められた許認可等を留保したことの違法性が争われることが多くなっています。
許認可等の権限に関連する行政指導
行政機関が、実際には許認可を出す意思がないにもかかわらず、「出せるかも」と示唆して相手を従わせるような行政指導は問題です。
そのため、次のような規定があります。
- 許認可の権限がない、または行使するつもりがない場合には、行政指導に携わる者は、そのような権限があるかのように装って相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならないとされています(34条)。
行政指導の方式
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨・内容・責任者を明確に示す義務を負います(35条1項)。もっとも、必ずしも書面で示す必要はありません。
しかし、行政指導が口頭でされた場合、相手方から行政指導の趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、交付しなければなりません(35条3項)。
ただし、すでに文書または電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求める行政指導については、書面を交付する義務はありません(35条4項2号)。
・趣旨・内容・責任者を明確にする
・口頭も可(ただし相手方に求められた場合、特別の支障がない限り書面を交付)
・すでに通知済などの場合、書面交付の義務なし
複数の者を対象とする行政指導
同じ行政目的のもとに、複数の人へ行政指導をする場合は、不公平が生じないように次の対応が求められます。
これにより、行政指導の客観性と公平性が担保されます。
行政指導の中止や見直しを求める制度
法令違反行為の是正を求める行政指導(その根拠規定が法律に置かれているものに限る)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます(36条の2第1項本文)。3
処分等の求め
何人も、法令違反の事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分・行政指導(その根拠規定が法律に置かれているものに限る)がされていないと思料するときは、当該処分・行政指導をする権限を有する行政庁・行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分・行政指導をすることを求めることができます(36条の3第1項)。
当該行政庁・行政機関は、この申し出があったとき、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分・行政指導をしなければなりません(36条の3第3項)。
まとめ:行政指導は「お願い」だけどルールあり!
行政指導は、処分とは異なり強制力はありません。しかし、自由な意思を尊重しながらも、一定のルールに従って行われる必要があるという点が大切です。
行政書士試験では、「申請や許認可との関係」「条文ごとの具体例」などを押さえておくと得点源になります!