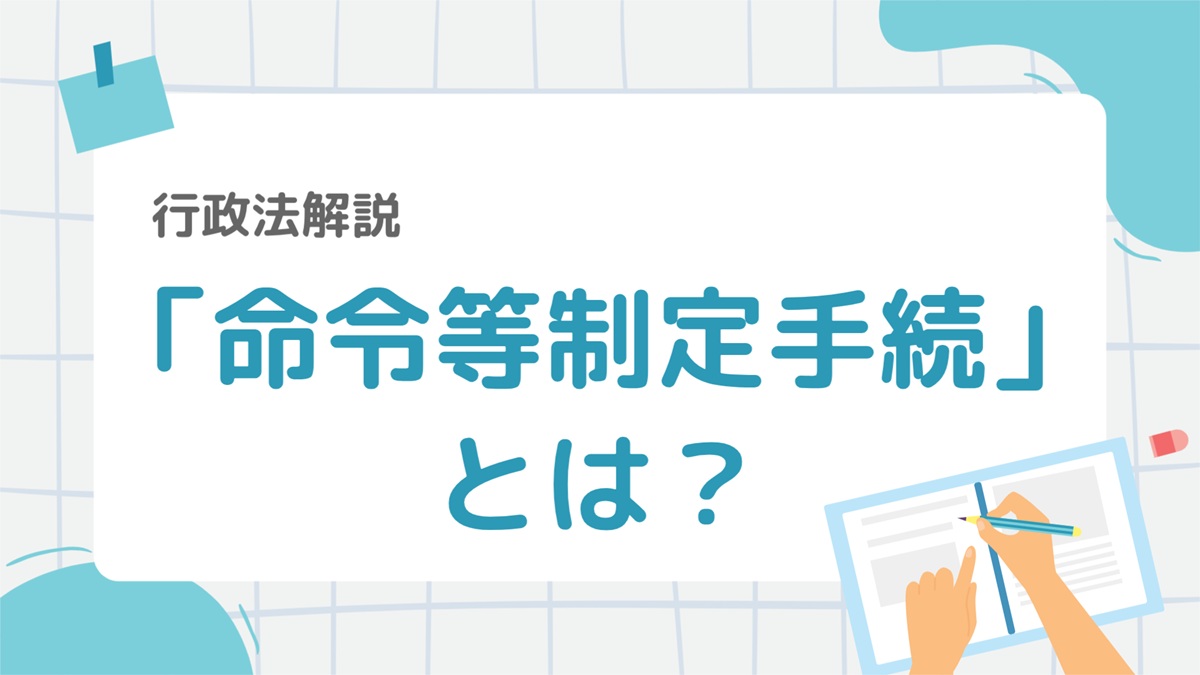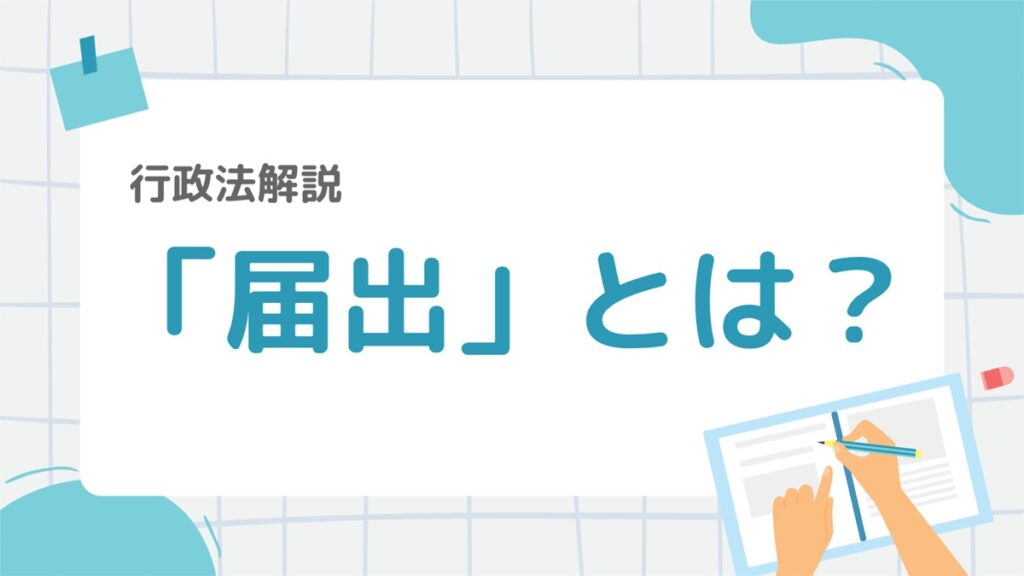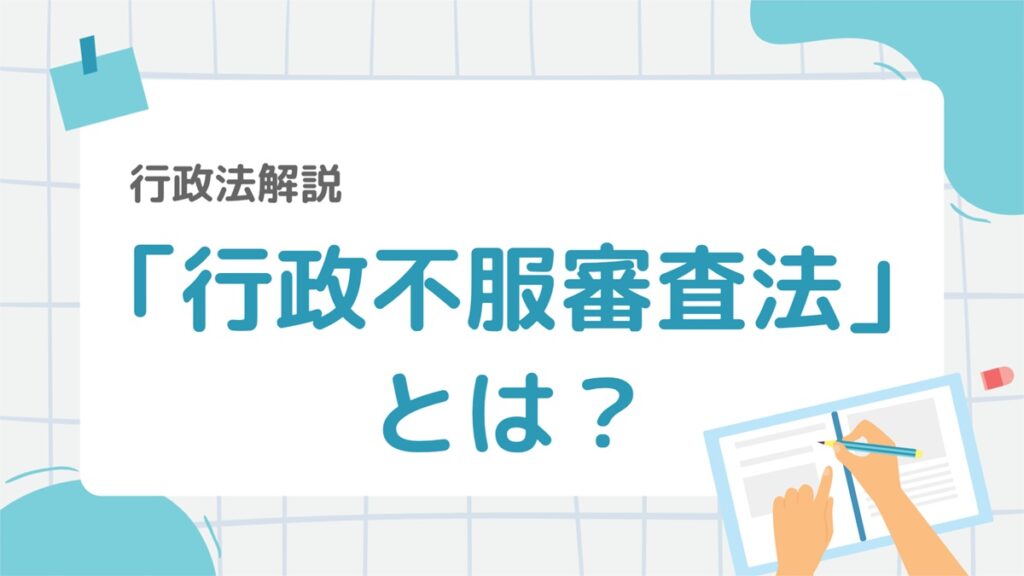- 「命令等の一般原則」ってなんとなく抽象的で覚えにくい…
- 意見公募手続の流れやポイントをしっかり理解しておきたい!
- 行政書士試験で出題されやすい箇所だけ効率よく押さえたい!
✍️命令等を定めるときの基本ルール
命令等制定の一般原則
38条1項では、命令等制定機関が命令等(命令・規則・基準など)を定める際の基本ルールが定められています。
✅ 第1項:法令の趣旨に合致すること
命令等制定機関は、命令等を定める際には、その命令の根拠となる法令の趣旨に適合させる必要があります(38条1項)。
。
✅ 第2項:命令等の継続的な見直し
命令等を定めたあとも、社会情勢や実施状況に応じて、必要に応じて見直しを行うべきとされています(38条2項)。
これは、「一度作ったルールは永遠に正しい」というわけではなく、適正を確保するよう努めなければならないという考え方に基づいています。
これらは、違法な行政活動は無効になるとする法律の優位の原則から、命令等について法的な制限をかけようとするものです。
💬 意見公募手続とは?行政立法に国民の声を反映させる仕組み
行政機関が定める命令等は、私たち国民の生活や権利に大きく関わるものです。
そのため、行政の独断で命令等(行政立法)が定められないのと同時に、より良い行政を目指すため、国民の意見を取り入れる「意見公募手続(パブリックコメント)」が法定されています。
🔁 意見公募手続の流れ(行政手続法39条~45条)
意見公募手続は、以下の4ステップで構成されます。
命令等の案・関連資料の公示
- ①原則
-
命令等を定めようとする行政機関は、あらかじめ命令等の案や関連する資料をあらかじめ公示して、意見の提出先・意見提出期間を明示して、広く一般の意見を募らなければなりません。(39条1項)。
これが意見公募手続の原則的なルールです。
- 法律に基づく命令・規則
- 審査基準
- 処分基準
- 行政指導指針 など
- ②特例:意見提出期間の短縮や省略
-
状況によっては、以下のような例外的な措置も認められています。
意見提出の条件
意見は、誰でも提出可能です。
国籍や利害関係の有無は問われず、外国人や法人でも意見を出すことができます。
提出意見の考慮と結果の公示
✅ 意見の取り扱い(42条)
提出された意見については、行政機関が十分に考慮する義務があります。(42条)
ただし、「必ず採用しなければならない」というわけではありません。
✅ 結果の公示(43条・45条)
意見公募手続の結果は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(WEBなど)を利用する方法などで公示されます(45条1項)。
以下のような情報を公開することが義務づけられています(43条1項)。
- 命令等の題名
- 命令等の案の公示日
- 提出意見(意見がなかった場合はその旨)2
- 提出意見を考慮した結果及びその理由
また、命令等を定めない場合や、意見公募手続を実施しなかった場合にも、その旨と理由を公示する必要があります。
- 意見公募手続を実施したが命令等を定めない場合(43条4項)
-
- 命令等を定めないこととした旨
- 命令等の題名
- 命令等の案の公示日
- 意見公募手続を実施せずに命令等を定めた場合(45条5項)
-
- 命令等の題名および趣旨3
- 意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由
✅ まとめ:行政書士試験に向けた重要ポイント
| 項目 | 試験対策ポイント |
|---|---|
| 命令等の一般原則 | 法令の趣旨に合致+社会情勢に応じた見直し努力義務(38条) |
| 意見公募手続の目的 | 国民の意見を行政立法に反映させる(39条) |
| 原則と例外 | 原則:30日以上の意見公募、省略・短縮の特例あり(40条) |
| 意見の提出者 | 制限なし(外国人・法人もOK) |
| 公示義務 | 手続結果を電子的に公開(43条・45条) |
- 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとする場合や、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとする場合には、意見公募手続を省略することができる(39条4項5号・7号) ↩︎
- 提出意見がなかった場合は、その旨を公示すれば足り、再度の意見公募手続を行う必要はない ↩︎
- 命令等の趣旨は、39条4項1号~4号の適用除外事由に該当することが当該命令等自体から明らかであるときは、公示する必要がない ↩︎