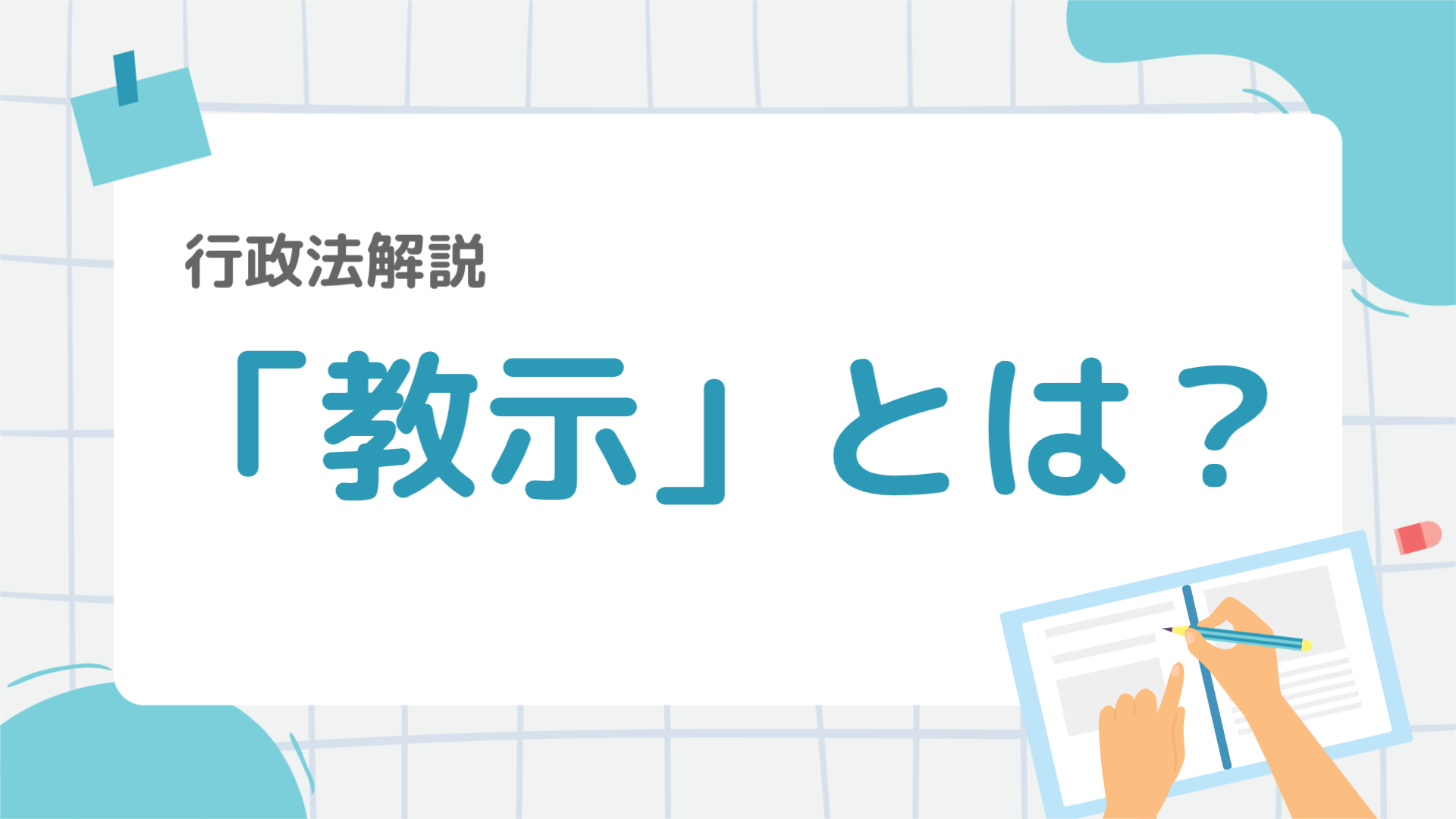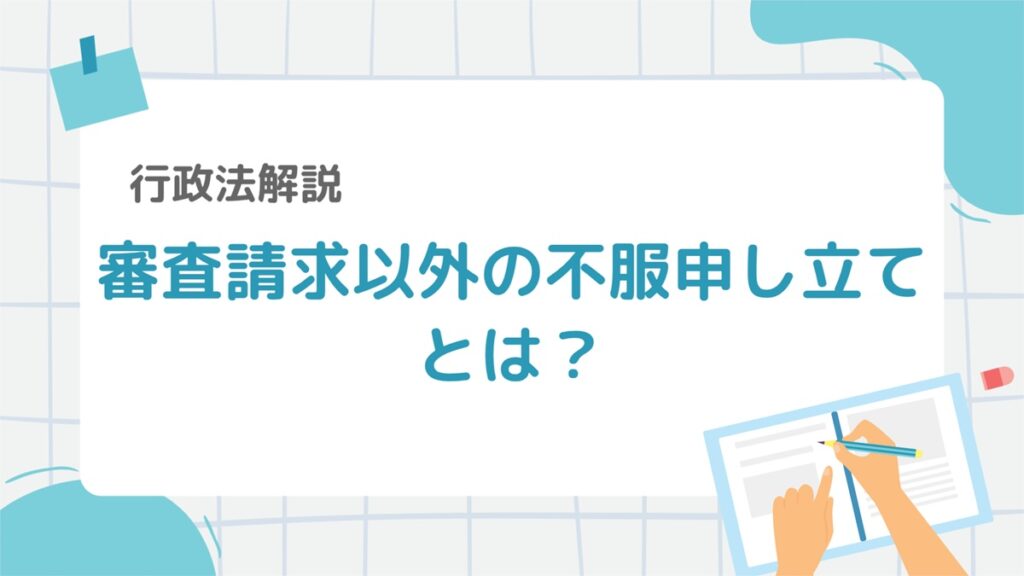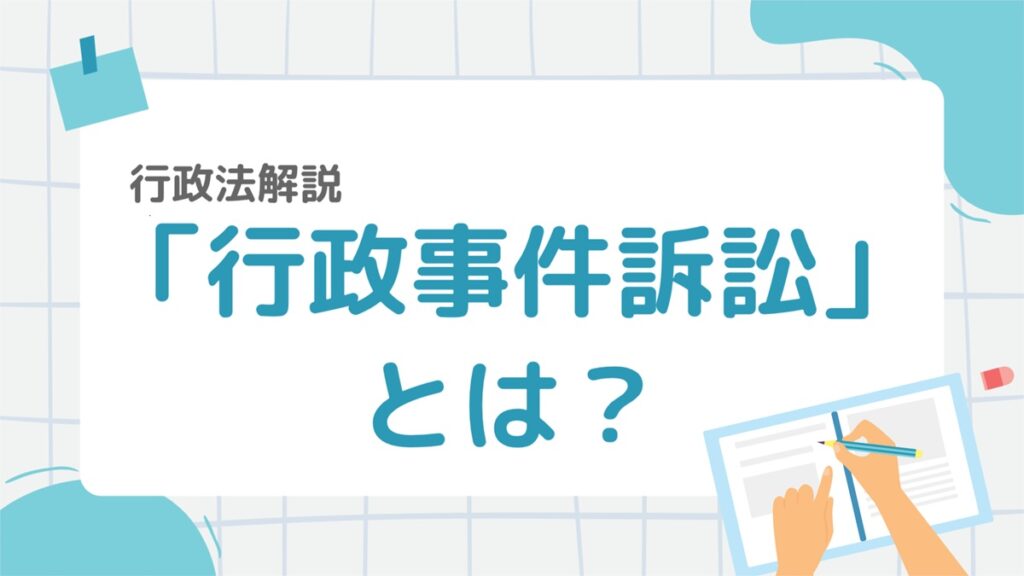- 「教示ってそもそも何?」と疑問に思っている行政書士試験の受験生
- 行政不服審査法の制度の流れを整理したい方
- 試験対策として条文と制度趣旨の理解を深めたい方
- 重要条文(行政不服審査法82条〜83条、22条)を事例と一緒に覚えたい方
💡教示とは?〜「不服申立てできるよ」と教えてくれる制度〜
行政庁が処分を出すとき、相手方がその処分に不服がある場合には、不服申立てという救済手段があります。
しかし、一般の人にとって不服申立て制度は難しくて、使いこなすのが大変です。
そこで、不服申立てができることや、その手続き方法を相手方に分かりやすく伝えるために設けられているのが 「教示」です。
これは、国民の権利救済を確実にするためのサポート制度といえます。

📌教示には2つのパターンがある!
①【必要的教示】書面による処分を出すときは、必ず教えなければいけない
行政庁が処分を書面で出すときは、その相手方に以下の内容を書面で教示しなければなりません(82条1項本文)。
- その処分に対して不服申立てができる旨
- どの行政庁に申立てをすればいいのか(不服申立て先)
- いつまでに申立てをすればいいのか(期間)
🗣ただし、口頭で処分を出すときは教示義務はありません(82条1項但書)。
これは、軽微な処分が多いため、形式的な手続を省略してもよいとされているからです。
②【請求による教示】質問されたら、きちんと教えなければならない
処分の相手方や利害関係人から「この処分、不服申立てできる?」と聞かれた場合、行政庁は次のような情報を教示する義務があります(82条2項)。
- 不服申立てが可能な処分かどうか
- 不服申立てできる場合の、行政庁(申立て先)
- 申立ての期間
そして、相手方から「書面で教えて」と求められたら、書面で教示しなければなりません(82条3項)。
🚨教示ミスがあった場合の救済措置
教示は制度的なサポートではありますが、間違った教示があったからといって、その処分が自動的に違法になるわけではありません。
ただし、以下のような救済措置が用意されています。
①【教示をしなかった場合】→ 不服申立てはできる
行政庁が教示義務を怠ってしまった場合でも、処分を受けた人はその処分庁に対して、不服申立書を提出することができます(83条1項)。
②【申立先を間違って教えた場合】→ 書面が回送される
審査請求をすることができる処分について、処分庁が、誤った申立て先を教えたことで、申立人がその教示どおりに申立てした場合でも大丈夫。
- 誤って申立てを受けた行政庁は、速やかに正しい行政庁にその審査請求書を送付し、申立人にも通知しなければなりません(22条1項)。
- 処分庁が審査請求書を受け取った場合も同様に、速やかに審査庁へ書類を回送して通知する義務があります(22条2項)。
③【「再調査できる」と誤って教えた場合】→ 形式上の誤りは吸収される
もし行政庁が「再調査請求できるよ」と誤って教えてしまい、申立人がその指示に従って再調査請求をした場合でも大丈夫。
行政不服審査法と行政事件訴訟法の教示の比較
| 行政不服審査法 | 行政事件訴訟法 | |
| 処分の相手方 | 教示義務あり ※口頭で処分をする場合は、教示義務なし | |
| 利害関係人 | 教示を求められた場合、教示義務あり ※書面による教示を求められた場合、書面による教示が必要 | 教示義務なし |
| 誤った教示などの救済規定 | あり | なし |
✅まとめ|教示制度は「国民を迷わせないための道しるべ」
教示は、行政庁が一方的に処分を行うだけでなく、「不服があればこうすればいいですよ」と相手方に道筋を示す、とても大切な制度です。
行政書士試験でも条文(82条〜83条、22条)の知識と、趣旨・流れの理解が問われますので、この記事でしっかり整理しておきましょう!