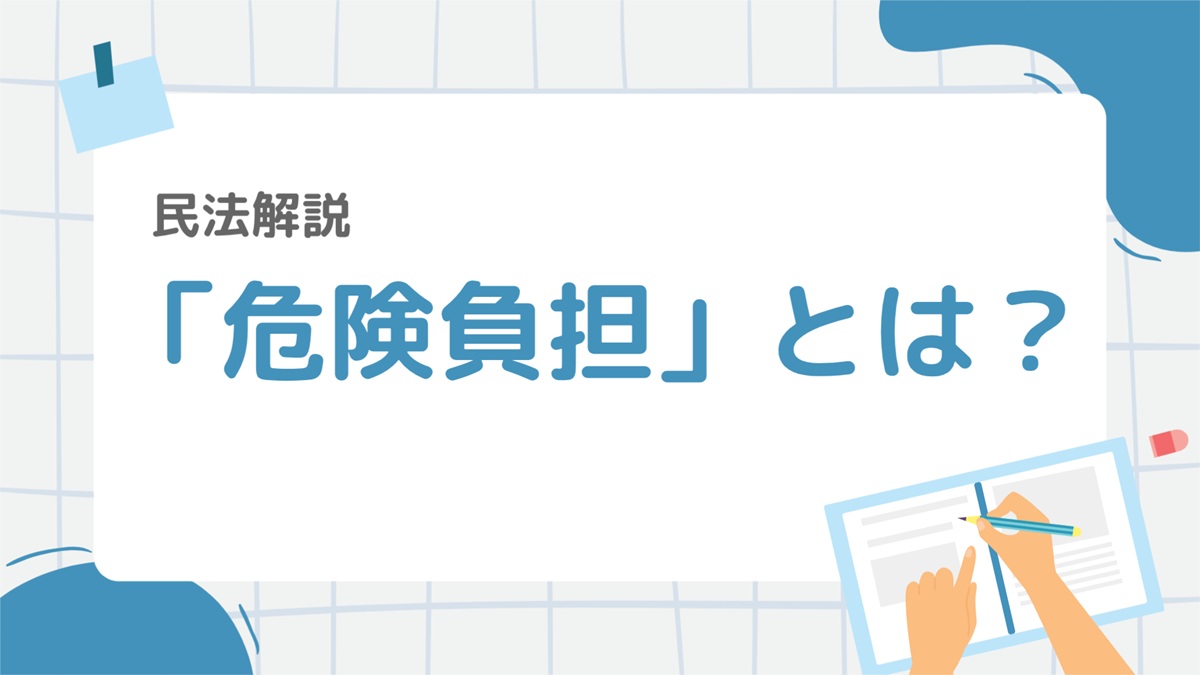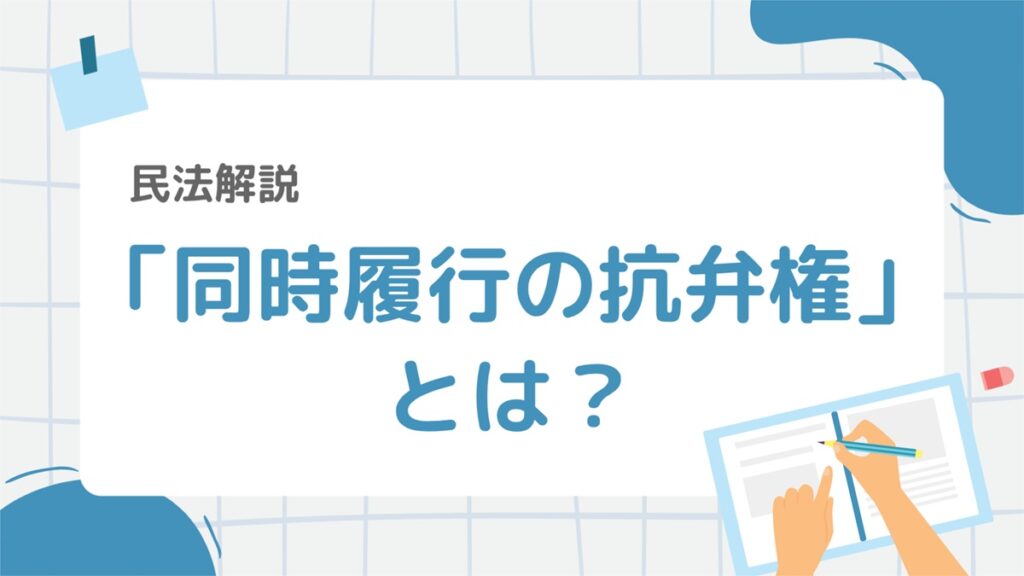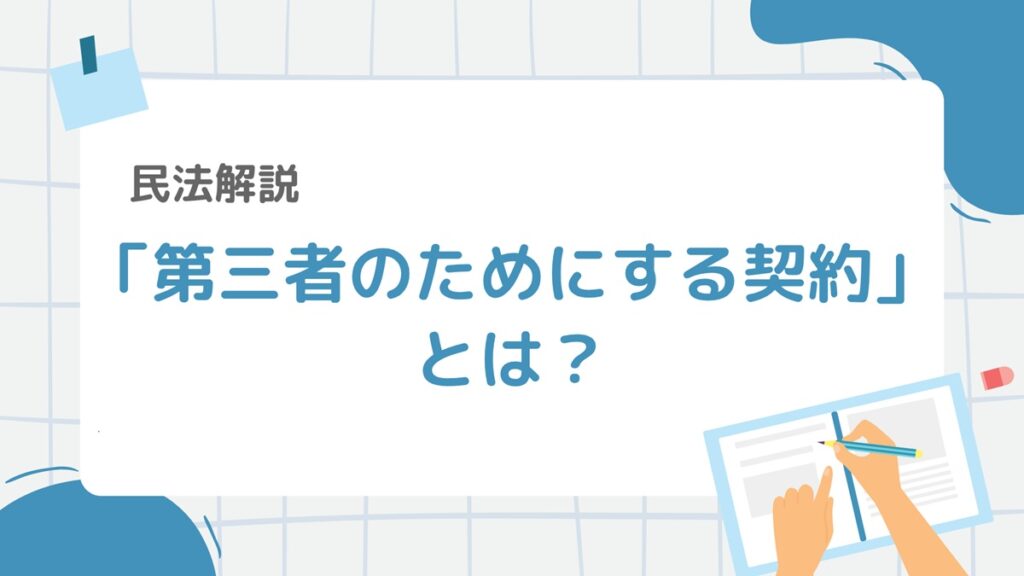【この記事はこんな人におすすめ】
- 「危険負担って何?民法の条文が難しすぎる!」と感じている方
- 行政書士試験の民法対策を進めたい方
- 危険負担の条文(536条)を具体例を交えて理解したい方
目次
危険負担とは?わかりやすく解説!
事例
--- config: theme: neutral --- sequenceDiagram participant A所有の建物 actor A_売主 actor B_買主 A_売主 ->> B_買主:建物引渡債務 B_買主 ->> A_売主:代金債務 A所有の建物 ->> A所有の建物: 落雷により焼失 note over A所有の建物: 建物引渡を履行できなくなる A_売主 ->> B_買主:×建物引渡⇒履行不可 B_買主 ->> A_売主:代金債務 note over A_売主,B_買主: 履行拒絶できるか?
AがBに対して建物を売却したが、未だ引渡しがされないうちに、建物が落雷により焼失した。
危険負担とは、双務契約において一方の債務が、債務者の責任ではない理由で履行できなくなったとき、“もう一方の当事者が自分の義務を果たさなければならないか?”という問題です。
ちょっとイメージしにくいですよね。
たとえば、AさんとBさんが「建物を引き渡す契約」を結んでいたとします。しかし、引き渡し前にその建物が火事で焼失してしまいました。Aさんには過失がないとしましょう。
このとき、Bさんは「建物を受け取れなかったんだから、代金は払わなくてもいいの?」という話になるわけです。
これが「危険負担」の問題です。
危険負担の基本ルール(民法536条)
危険負担に関しては、民法536条にルールが定められています。
ポイントを2つに分けて押さえましょう!
- ①当事者双方の責めに帰することができない事由の場合(536条1項)
-
債務が、当事者双方の責めに帰することができない事由(たとえば自然災害や第三者の不可抗力による損害など)で履行できなくなったとき、
➡債権者は自分の支払いの義務(反対給付)のを拒むことができます(536条1項)。つまり、先ほどの例なら、
- Aさんの建物引渡債務が、A・Bどちらのせいでもなく履行不能になったなら、
- Bさんは「もう建物がないから、代金は払わない(代金債務の履行を拒絶)」と言ってOKです!
- ②債権者の責めに帰すべき事由による場合(536条2項)
-
反対に、債務の履行不能が債権者自身の責任だった場合はどうでしょう?
この場合は、
➡ 債権者は、支払い義務を免れることができません。(536条2項)。たとえば、Bさんが受け取りを渋ったせいで建物がダメになった場合、
- Bさんには責任があるので、
- Bさんは、建物を受け取れなかったとしても、代金を払わなければなりません!
まとめ
危険負担とは、契約が思い通りに進まなくなったとき、「支払い義務などがどうなるか?」を決めるルールです。
特に、“誰に責任があるか(債務者か債権者か)”を見極めることがポイントです!
行政書士試験では、民法536条の条文の流れと具体例をセットで覚えておくと、得点アップにつながります!