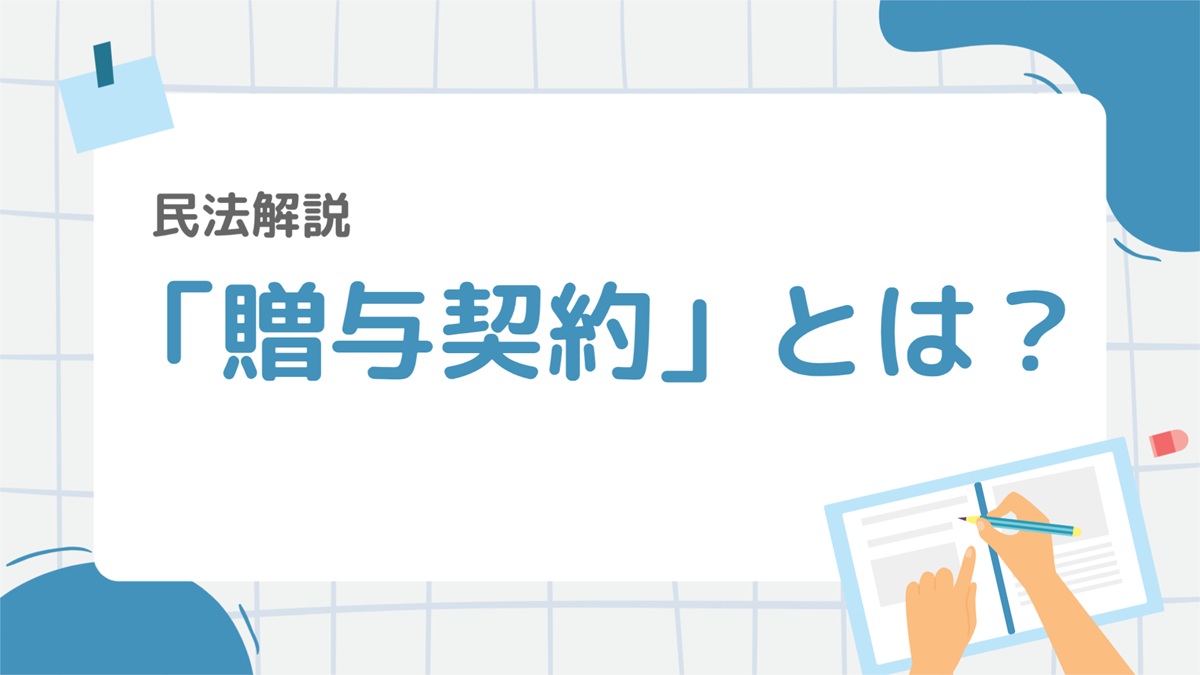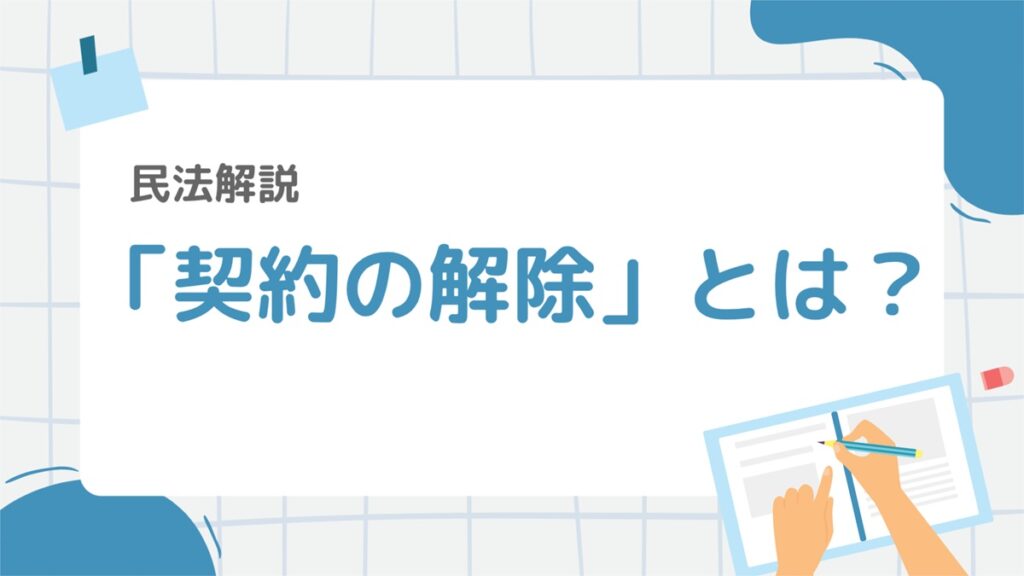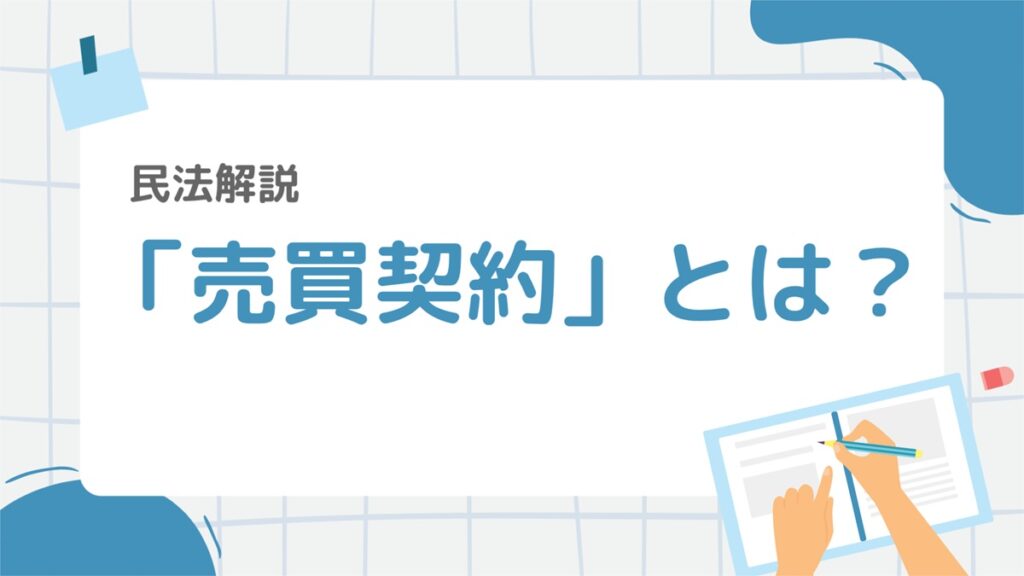- 贈与契約の基本をわかりやすく押さえたい方
- 定期贈与や負担付贈与など、特殊な贈与の種類を整理したい方
- 行政書士試験の民法対策として、贈与契約を確実に理解しておきたい方
贈与契約とは?
---
config:
theme: neutral
---
flowchart LR
時計(("時計"))
A_贈与者 --目的物_時計--> B_受贈者
AはBに対して「自分の所有する時計を譲りたい」と申込みをし、Bはこれを承諾した。
贈与契約とは、一方の当事者(贈与者)が、自分の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを約束する契約です(549条)。
つまり、お金や物をタダであげると決める法律上の約束のことを指します。
書面によらない贈与と解除
贈与契約は口頭でも成立しますが、書面によらない贈与については、当事者のどちらからでも解除することが可能です(550条本文)。
これは、軽い気持ちで贈与することを防ぎ、贈与の意思を確かなものにするためです。1
ただし、すでに履行(実行)された部分については解除できません(550条但書)。これは受贈者が不利益を受けてしまうのを防止するためです。
履行が終わったかどうかは、次のように判断されます。
贈与者の担保責任
贈与者は、贈与の対象となる物や権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約束したものと推定されます。
そのため、基本的には担保責任(欠陥などに対する責任)を負わない(=原則:担保責任なし)とされています(551条1項)。
ただし、負担付贈与(後述)では話が変わります。
負担の限度内で、売主と同じレベルの担保の責任を負うことになります(551条2項)。
特殊な贈与の種類
定期贈与
定期贈与とは、たとえば「毎月5万円をあげる」といったように、定期的な給付を約束する贈与をいいます。
この場合、贈与者または受贈者の死亡すると、その契約は終了します(552条)。
信頼関係を前提とするため、どちらかがいなくなると契約も自然に終わる仕組みです。
負担付贈与
負担付贈与とは、贈与される側(受贈者)が、何らかの義務を負うタイプの贈与です。
具体例は以下の通りです。
- 不動産を贈与する代わりに、住宅ローンの残債を受けてもらう
- 現金を贈与する代わりに、将来介護してもらう
- 車をあげる代わりに、月に数回貸してもらう
負担付贈与は性質上、双務契約(お互い義務を負う契約)に似ているため、同時履行の抗弁権・危険負担・解除など双務契約に関するルールが適用されます(最判昭53.2.17)。
死因贈与
死因贈与とは、贈与者の死亡を条件に効力が生じる贈与です。
生前に贈与契約を交わしておき、贈与者が亡くなったときに贈与の効果が発生します。
死因贈与はあくまで贈与契約です。
よく似た制度に「遺言による遺贈」がありますが、遺贈は贈与とは異なり単独行為(一方的な意思表示)です。
なお、死因贈与には、必要に応じて遺贈に関する規定が準用されることになっています(554条)。34
まとめ
贈与契約は一見シンプルですが、書面・履行状況・負担の有無などによって適用されるルールが異なります。
行政書士試験では、定期贈与・負担付贈与・死因贈与など特殊な贈与の知識も問われやすいので、しっかり整理して覚えておきましょう!
- 重要判例:贈与が書面によってされたといえるためには、贈与の意思表示自体が書面によっていることを必要としないことはもちろん、書面が贈与の当事者間で作成されたこと、または書面に無償の趣旨の文言が記載されていることも必要としない(最判昭60.11.29) ↩︎
- 重要判例:「引渡し」には、占有改定も含まれる(最判昭31.1.27) ↩︎
- 重要判例:死因贈与の撤回については、1022条がその方式に関する部分を除いて準用されるため、贈与者は、いつでも、死因贈与を撤回することができる(最判昭47.5.25) ↩︎
- 重要判例:負担の履行気が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約に基づき、受贈者が約旨に従い負担の全部またはそれに類する程度の履行をした場合、特段の事情がない限り、伊郷の撤回に関する1022条を準用するのは相当ではない(最判昭57.4.30) ↩︎