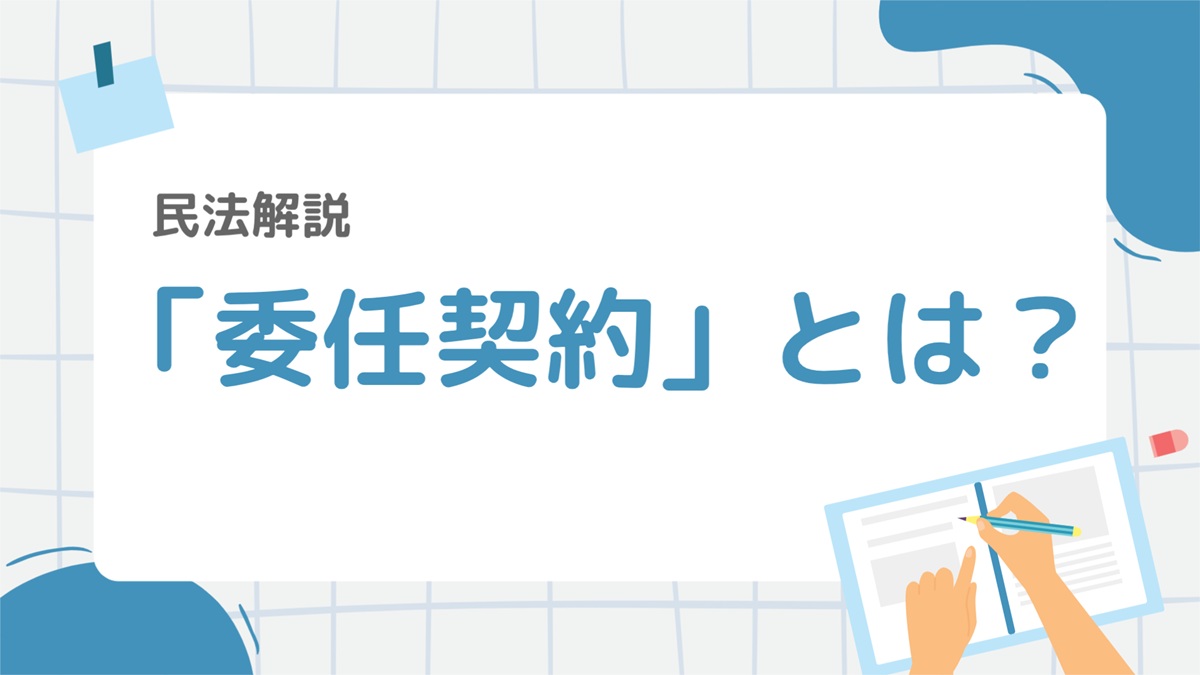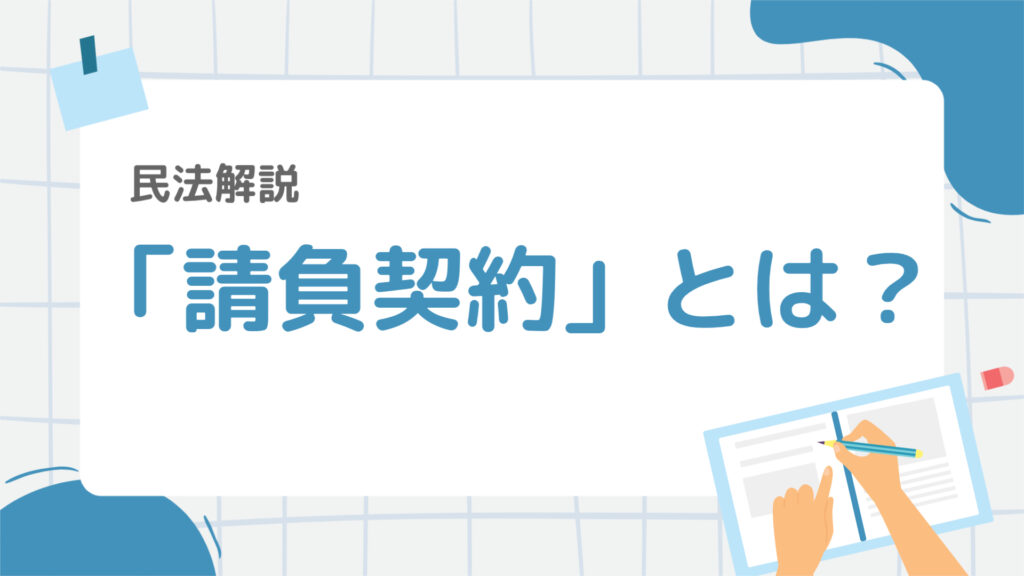✅委任契約とは?わかりやすく解説
--- config: theme: neutral --- flowchart LR A_委任者 B_受任者 C A_委任者 -->|①委託| B_受任者 B_受任者 -->|②法律行為(示談)| C A_委任者 -->|③報酬_特約あり or 無報酬| B_受任者
交通事故を起こしたAは弁護士Bに対して「被害者であるCとの示談をお願いしたい」と申込みをし、Bはこれを承諾した。
「委任契約」とは、ある人(委任者)が(例:示談交渉など)を他人(受任者)に頼み、その相手が「わかりました」と承諾することで成立する契約のことです(643条)。
たとえば、弁護士に「交渉をお願い」と依頼するのは典型的な委任契約です。
また、委任契約では原則として報酬は発生しません。つまり、「特に取り決め(特約)がなければタダ」です(648条1項)。この点で雇用契約や請負契約とは異なります。
また、委任契約においても、請負契約と同様に、受任者は委任者から独立しています。
👤受任者(頼まれる側)の義務とは?
受任者には、委任を受けた以上、いくつかの重要な義務が課されます。
①善良な管理者の注意義務(善管注意義務)
報酬の有無にかかわらず、受任者は善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって委任されたことを処理しなければなりません(644)。1これはプロ意識のようなものです。
②付随的義務
委任の内容は契約ごとに異なりますが、民法では委任事務の処理において通常求められる義務が定められています。これを付随的義務といい、以下が代表的です。
- 報告義務
受任者は、委任者の請求があった場合、いつでも委任事務の処理状況を報告しなければなりません。また、委任が終了した後は、遅滞なくその経過および結果を報告する義務があります(645条)。 - 受取物・果実の引渡義務
受任者は、受任事務の処理の過程で受け取った金銭や物品(果実も含む)を、委任者に引き渡さなければなりません(646条1項)。 - 取得権利の移転義務
受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を、委任者に移転しなければなりません(646条2項)。 - 金銭消費の責任
受任者が委任者に引き渡すべき金額や、その利益のために用いるべき金額を自己のために消費した場合、消費した日以降の利息を支払う義務があり、さらに損害が生じた場合には、その賠償責任を負います。(647条)
🔁複委任はできる?(第三者に再委任)
複委任とは、受任者が第三者に自己の代わりに事務を処理させることをいいます。
委任は信頼関係を基礎としているので、原則、受任者が他の人に依頼すること(複委任)はできません。
ただし、次のいずれかならOKです(644条の2第1項)。
- 委委任者の許諾を得た場合
- やむを得ない事由がある場合(病気など)
👥委任者(頼む側)の義務とは?
委任者も、ただお願いするだけではなく、受任者をサポートする義務があります。
- 費用前払義務
委任事務を処理に費用が必要な場合、委任者は受任者の請求に応じて、その費用を前払いしなければなりません(649条)。 - 費用償還義務
受任者が委任事務を遂行するために必要な費用を支出した場合、委任者は、その費用および支出の日以降の利息を償還する義務を負います(650条1項)。 - 債務の代弁済・担保提供義務
受任者が委任事務を遂行するために必要な債務を負担した場合、委任者に対し、その弁済を請求することができます。また、債務の弁済期が到来していない場合には、委任者に相当の担保を提供させることができます(650条2項)。 - 損害賠償義務
受任者が委任事務を遂行する過程で、自己の過失なく損害を受けた場合、委任者に対してその損賠の賠償を請求することができます(650条3項)。
🛑委任の終了パターンとは?
① 自由に解除できる(任意解除/651条)
委任は、各当事者(どちらからでも)がいつでも解除することができます(651条1項)。
ただし、タイミングが悪いと損害賠償が必要になることも。たとえば、
- 相手に不利な時期に解除した場合
- 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)を目的とする委任を解除した場合
解除を行った者は、やむを得ない事由がない限り、相手方の損害を賠償しなければなりません(651条2項)。
② 自動的に終了するケース(653条) 死亡・破産・後見開始
委任は、次の事由により終了します(653条)。
📝まとめ
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 委任契約の特徴 | 法律行為を他人に依頼する契約。原則報酬なし |
| 受任者の義務 | 善管注意義務・報告義務・成果の引渡しなど |
| 委任者の義務 | 費用の前払い・損害の賠償など |
| 終了事由 | 任意解除、受任者の死亡・破産など |
- 参考:委任が委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行ができなくなったとき、または履行の中途で終了した時は、受任者は、すでにした履行の割合に応じて報酬を請求することができる(648条3項1号・2号) ↩︎