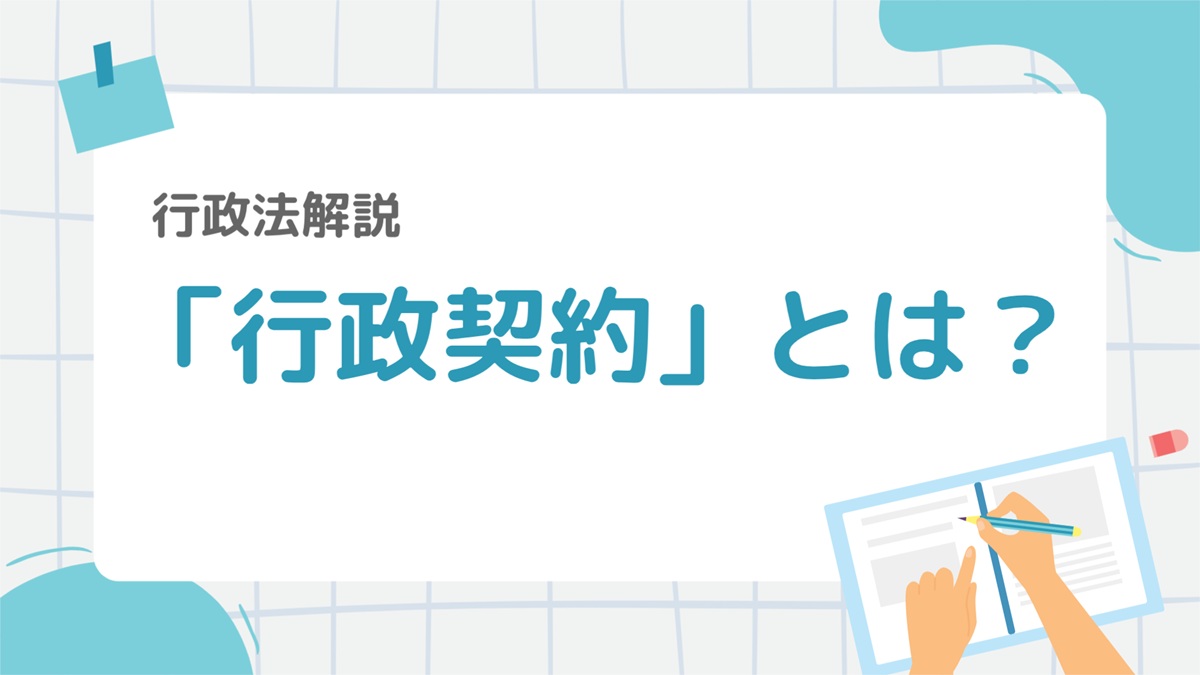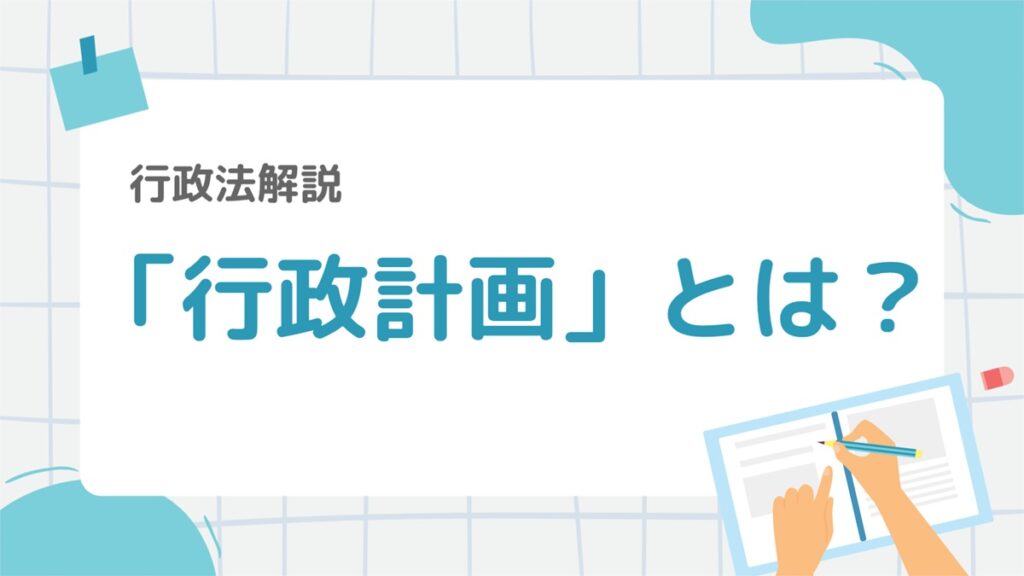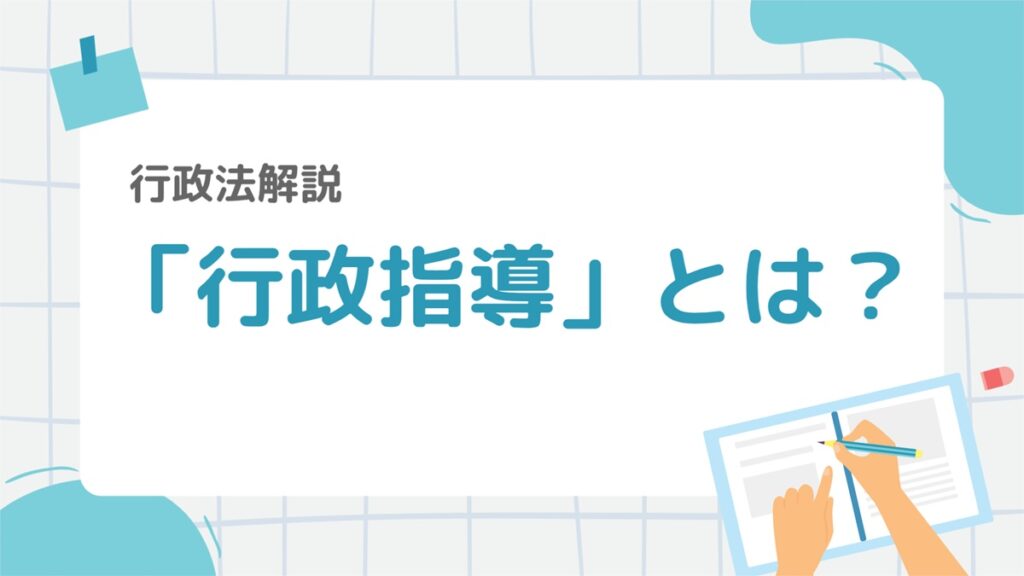- 「行政契約って何?」と基礎から知りたい行政書士試験の受験生
- 民法と行政契約の違いを整理したい方
- 準備行政・侵害行政・給付行政の具体例を押さえておきたい方
行政契約とは?|行政と私人が対等に結ぶ契約

行政契約とは、行政主体(国や地方公共団体)が行政目的を達成するために、国民(私人)と対等な立場で締結する契約のことです。1
民間同士の契約と異なり、行政による特別な目的を持つ契約という点が特徴です。
行政契約が使われる場面とは?【分野別に解説】
行政契約は、行政の目的に応じて使われ方が異なります。以下、3つの行政分野ごとに代表的な例を見ていきましょう。
① 準備行政における行政契約
準備行政とは、行政を遂行するのに必要な物品を購入したり、整備するなどの準備的な活動を行う分野です。
この分野では、次のような行政契約が積極的に活用されています。
- 事務用品の購入契約
- 庁舎建設の請負契約
このように、行政の事務を行うために必要な物品や施設を整える契約が多く見られます。
② 侵害行政における行政契約
侵害行政とは、行政が私人に義務を課したり、権利を制限するような行為を行う分野です。
かつてはこの分野での契約はほとんど認められておらず、行政行為(一方的な処分)が原則でした。
しかし現在では、以下のような形で行政契約も一部認められています。
- 公害防止協定2
- 開発負担金や教育負担金などを私人が負担する契約
このように、行政と私人の合意に基づく契約方式も徐々に取り入れられています。
③ 給付行政における行政契約
給付行政は、行政が国民に対して利益を与える分野です。
この分野では、契約方式を採用する法律が増えてきており、以下のような契約が行われます。
- 公的資金の助成に関する契約
- 指定管理者制度における契約
つまり、行政サービスの提供に関しても契約という形式が重視されつつあるのです。3▶判例
行政契約に関するルールや原則
法律の根拠は必要?
行政契約は、当事者の合意に基づいて成立するため、法律の根拠は必要ではありません。
その契約内容が国民に義務を課したり、権利を制限するものである場合でも、同様です。
行政法の一般原則が適用される
行政契約はたとえ売買契約や請負契約の形を取っていても、行政の活動の一環です。
そのため、以下のような行政法の一般原則が適用されます。
この点は、民間同士の契約と異なる大きな特徴です。
民法の規定も基本的に適用される
行政契約も契約の一種であるため、民法に定められた契約に関する一般規定が原則として適用されます。
ただし、行政特有の規制や原則が加わる点に注意しましょう。▶判例
まとめ|行政契約は「合意+行政目的」で成り立つ
行政契約は、行政がその目的を達成するために私人と対等に結ぶ契約です。
民法の規定が基本となりつつ、行政法の制限や原則が加わる特別な契約形態です。
行政書士試験でも、行政契約の位置づけや分野ごとの活用状況、適用される法原則などが問われるため、民法との違いを意識しながら理解しておくことが重要です。