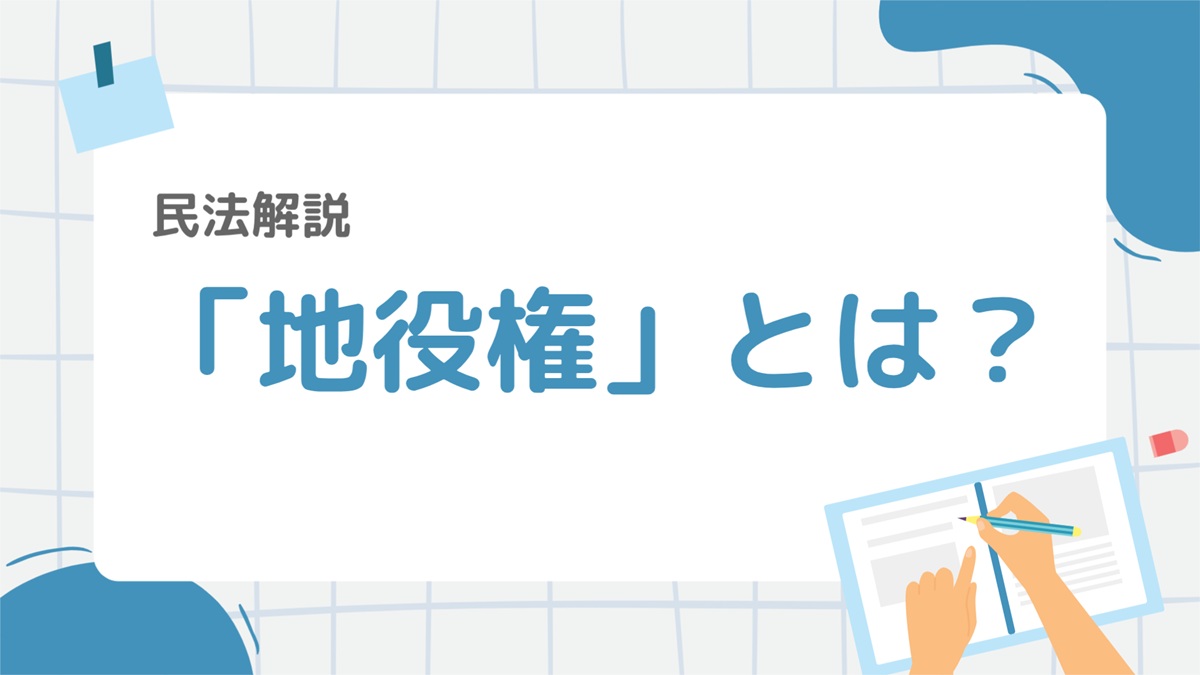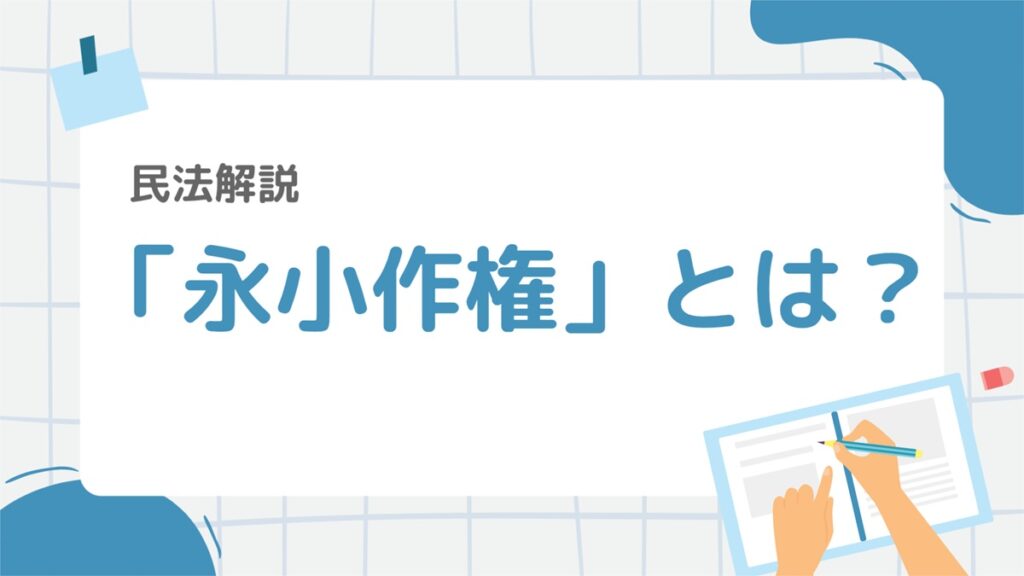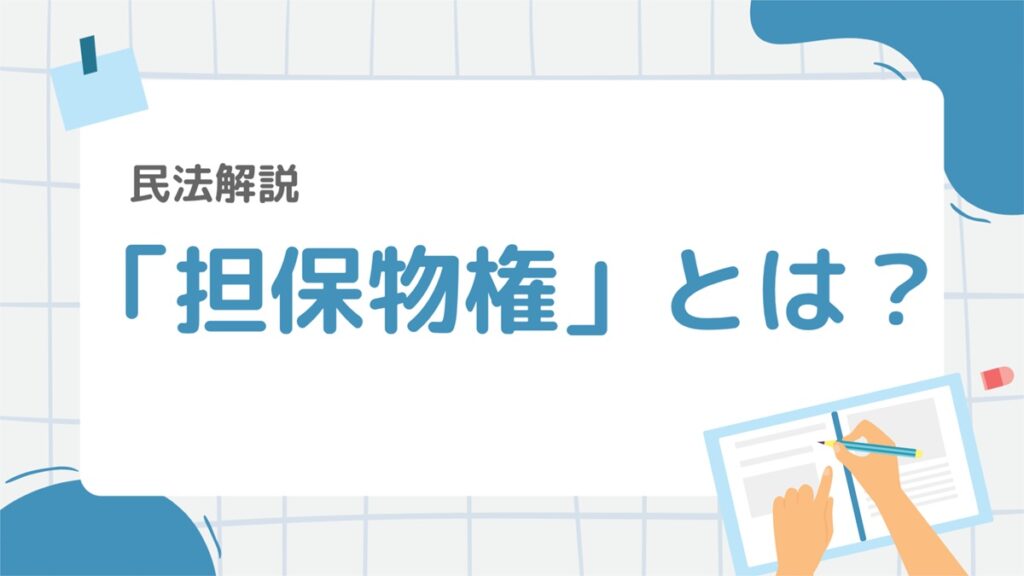- 「地役権」という言葉の意味がよくわからない
- 民法の試験対策で、地役権の性質や要件を整理したい
- 土地の権利関係について具体的にイメージしたい
- 行政書士・司法書士など法律系資格を目指している
地役権とは? ─ 他人の土地を使える特別な権利
地役権(ちえきけん)とは、自分の土地(要役地)を便利に使うために、他人の土地(承役地)を利用できる権利のことです(280条本文)。
たとえば、自分の土地から道路に出るために、隣の土地を通行できるようにする権利などが地役権にあたります。
- 地役権を設定された他人の土地 → 承役地(しょうえきち)
- 地役権によって利益を受ける自分の土地 → 要役地(ようえきち)
地役権の2つの性質|付従性と不可分性
①付従性
地役権は、「土地とセット」で移転する性質を持ちます。つまり、要役地の所有権に付随して、所有権とともに、地役権も一緒に引き継がれるのが原則です(281条1項本文)。この性質を付従性といいます。
また、地役権だけを切り離して譲ったり、他の目的に使ったりすることはできません(281条2項)。
このように、地役権は要役地に付随して動く権利という特徴があります。
✅ ポイント
地役権は「土地の一部のようなもの」と考えるとイメージしやすいです。
②不可分性
地役権は、土地全体にかかる権利として扱われます。
たとえば、要役地や承役地が複数の人で共有されている場合でも、地役権はその土地全体に対して認められるのが原則です。この性質を不可分性といいます。
この性質により、共有者の一人が勝手に権利を分けたり、他の共有者の権利を無視したりすることはできません。1
✅ ポイント
地役権は「土地の一部の人のもの」ではなく、「土地全体のためのもの」として扱われます。
時効による地役権の取得・消滅について
取得時効
地役権は、以下の条件を満たせば時効によって取得することができます。
- 継続的に行使されていること(例:通行などが長期間続いている)
- 外から見てわかる形で行使されていること(=外形的に明らか)
これらを満たして期間が経過すると、時効によって取得することができます(283条)。
消滅時効
要役地が複数の共有されている場合、一人の共有者について時効の完成猶予や更新が認められると、その効力は他の共有者にも及びます(292条)。
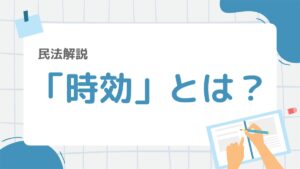
| 地上権 | 永小作権 | 地役権 | |
| 存続期間 | 当事者間で永久と定めることも可能 (大判明36.11.16) | 20~50年の範囲で定めることができる(278条1項前段) | 当事者間で永久と定めることも可能 |
| 地代・小作料 | 要素でない (266条) | 要素である (270条) | 要素でない (280条) |
| 物権的請求権 | 返還請求〇 妨害排除請求〇 妨害予防請求〇 | 返還請求〇 妨害排除請求〇 妨害予防請求〇 | 返還請求× 妨害排除請求〇 妨害予防請求〇 |
| 抵当権の設定 | 〇 (369条2項) | 〇 (369条2項) | × |
まとめ|地役権は土地と一体となる権利
地役権は、「他人の土地を自分の土地のために使う」という特別な権利ですが、その本質は土地と土地の関係を調整するためのルールです。
付従性や不可分性、そして時効による取得・消滅などの要素は、すべて「土地全体の調和」を図るために設けられています。
行政書士試験などでもよく出題されるテーマなので、しっかり整理しておきましょう。