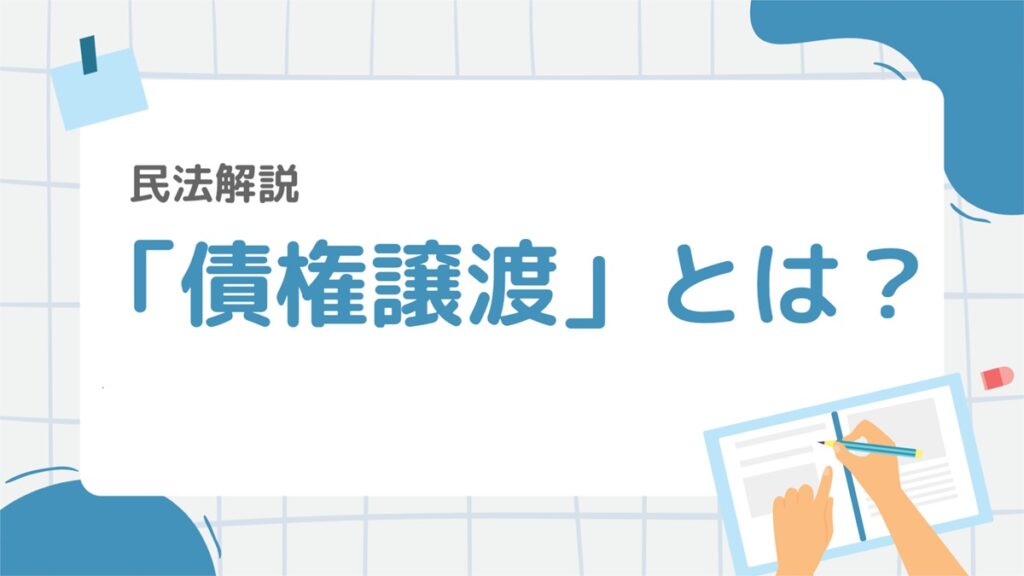保証債務とは?
---
config:
theme: neutral
---
flowchart LR
A("A<br>主たる債務者")
C("C<br>保証人")
B("B<br>債権者")
B--主たる債務-->A
B--保証債務-->C
AがBから100万円を借りる際、BとCの間で、「もしAが返済できなかった場合には、Cが代わりに100万円を支払う」という内容の契約が結ばれました。
保証債務とは、債務者が債務を履行しない場合に、その債務者(主たる債務者)に代わって履行する義務を負う債務のことです(446条1項)。この保証債務を負う人のことを「保証人」といいます。
保証債務の法的性質
付従性
保証債務は、主たる債務の存在を前提とし、主たる債務に従う性質を持ちます。この性質を「付従性」といいます。そのため、主たる債務が成立しなければ保証債務も成立せず、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅します。1
また、保証債務は主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償などの従たるすべてのものを含みます(447条1項)。
さらに、保証人は保証債務についてのみ、違約金や損害賠償の額を定めることができます(447条2項)。
随伴性
主たる債務が譲渡された場合、保証債務もそれに伴って移転します。この性質を「随伴性」といいます。
補充性
保証人は、主たる債務者が債務が履行しない場合に初めて履行の責任を負います(446条1項)。
この補充性には、以下の2つの抗弁権が含まれます。
■保証債務の補充性2
- 催告の抗弁権
債務者が保証人に履行の請求をした場合、保証人は、まず主たる債務者に催告をするよう求めることができます(452条本文) - 検索の抗弁権
債権者が主たる債務者に催告をした後でも、保証人が主たる債務者に弁済能力があり、かつ執行が容易であることを証明した場合、債権者はまず主たる債務者の財産に対して執行しなければなりません(453条)
保証債務の成立
保証契約
保証債務は、保証人と債権者の間で保証契約を結ぶことによって成立します。
ただし、この保証契約は書面で締結しなければ効力を持ちません(446条2項)。これは、安易に保証契約を締結させないための規定です。
保証人の要件
一般的に、保証人になるために特別な資格は必要なく、制限行為能力者でも保証人になることができます。
ただし、債務者が保証人を立てる義務を負う場合、その保証人は行為能力者であり、弁済する資力を有していなければなりません(450条1項)。34
主たる債務の存在
主たる債務が行為能力の制限を理由に取り消された場合、付従性の原則により保証債務も消滅します。
ただし、保証人が保証契約を締結した時点で、その取消しの原因を知っていた場合、保証人は主たる債務と同一の目的を有する独立の債務を負うものと推定されます(449条)。
保証人の求償権
保証人は、主たる債務者が最終的に負担すべき債務を一時的に肩代わりする立場にあるため、保証人が保証債務を履行した場合、主たる債務者に対して求償権を取得します。
■保証人の求償権
| 委託を受けた保証人 | 委託を受けていない保証人 | ||
| 主たる債務者の意思に反しない場合 | 主たる債務者の意思に反する場合 | ||
| 弁済前 | あり5 (460条) | なし | |
| 弁済後 | あり (459条1項) | あり (462条1項・2項) | |
| 範囲 | 弁済があった日以後の法定利息および避けることができなかった費用その他の損害の賠償も含む (459条2項、442条2項) | 主たる債務者が弁済の当時に利益を受けた限度(462条1項・459条の2第1項) | 求償の時点で現存利益の限度(462条2項) |
特殊な保証の形態
連帯保証
連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを合意した保証のことです。
連帯保証も保証債務の一種であり、主たる債務に付従するため、付従性の効果は通常の保証債務と同じです。しかし、連帯保証には補充性がありません。そのため、連帯保証人は、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を主張できません(454条)。
また、連帯保証人について生じた事由の効力については、連帯債務の規定が準用されます(458条、438条、439条1項、440条、441条)。
■主たる債務者と保証人に生じた事由の効力6
| 通常の保証 | 連帯保証 | ||
| 主たる債務者に生じた事由 | 保証人に対しても効力を生ずる7 | ||
| 保証人に生じた事由 | 主たる債務を消滅させる事由 弁済・代物弁済・保証人自身の債権による相殺・更改など | 主たる債務者に対しても効力を生ずる | |
| 混同 | 主たる債務者に対しては効力を生じない | 主たる債務者に対しても効力を生ずる | |
| その他の事由 | 主たる債務者に対しては効力を生じない | ||
※商法では、商行為の特則が定められています。👉商行為の特則(連帯保証)
共同保証
共同保証とは、同じ主たる債務に対して複数の保証人が存在する場合を指します。この場合、各保証人は債権者に対して均等に分割された額のみを保証します(456条、427条)。この考え方を「分配の利益」といいます。8
共同保証人の1人が自己の負担部分を超える額を弁済した場合、他の共同保証人に対して求償権を持ちます(465条)。
根保証
根保証とは、特定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務として保証する形態のことです。
特に、保証人が自然人(個人)である場合、その保証契約を「個人根保証契約」といいます(465条の2第1項)。この契約では、極度額を定めなければ効力を生じません(465条の2第2項)。9
個人根保証契約の制度は、悪質な金融業者によって不当に利用される危険性があるため、保証人に過大な負担がかかることを防ぎ、保証人を経済的破綻から救済するために設けられました。
保証人の保護制度の拡充
債権者の情報提供義務
保証人は常に主たる債務者の返済状況を把握できるわけではありません。
そのため、保証契約締結後も保証人を保護するために、債権者には主たる債務の履行状況を保証人に提供する義務「情報提供義務」が規定されています。
■債権者の情報提供義務
| 保証人の請求があった場合 (458条の2) | 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合 (458条の3) | |
| 時期 | 保証人の請求時 | 主たる債務の期限の利益喪失を知った時から2か月以内 |
| 相手方 | 委託を受けた保証人(個人・法人) | 保証人(委託の有無を問わない。個人のみ) |
| 内容 | 主たる債務の元本・利息・違約金・損害賠償などの不履行の有無・残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額 | 主たる債務者が期限の利益を喪失したこと |
| 義務違反の場合 | 規定なし | 遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生じていたものを除く)にかかる保証債務の履行請求不可 |
事業用融資における個人保証の制限
金融機関が中小企業に融資を行う際、経営者の親族や友人など第三者の個人保証を求めることが一般的でした。しかし、事業者融資の金額は高額であるため、保証責任を負った個人が生活破綻に陥るケースが多くみられました。
そのため、事業のために負担した貸金などの債務を主たる債務とする保証契約・根保証契約では、その締結の日前の1か月以内に作成された公正証書を作成し、保証人の意思を確認しなければ効力を持たないとされています(465条の6第1項)。
以上のように、保証債務は主たる債務と密接に関連しながらも、保証人を保護するための様々な規定が設けられています。
- 参考:保証人の負担が債務の目的または態様において主たる債務より重い時は、主たる債務の限度に減縮される(448条1項)。 ↩︎
- 物上保証人には、補充性(催告の抗弁権・検索の抗弁権)が認められていない。 ↩︎
- 参考:保証人が弁済をする資力を欠くに至った場合、債権者は資力を具備する者に代えることを請求することができる(450条2項) ↩︎
- 参考:450条1項・2項は、債権者が保証人を指名した場合は、適用されない(450条3項) ↩︎
- 重要判例:物上保証人は、被担保債務の弁済期が到来したとしても、債務者に対し、あらかじめ求償権を行使することができない(最判平2.12.18) ↩︎
- 重要判例:主たる債務者が時効の利益を放棄した場合でも、保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができる(大判大5.12.25) ↩︎
- 参考:保証人は、主たる債務者が債権者に対して相殺権を有するときは、主たる債務者が債務を免れるべき限度において履行拒絶ができる(457条3項)。 ↩︎
- 連帯保証の場合、分別の利益はない(大判大6.4.28) ↩︎
- 参考:保証人が法人である場合、個人根保証契約に当たらず、極度額の定めは不要。 ↩︎