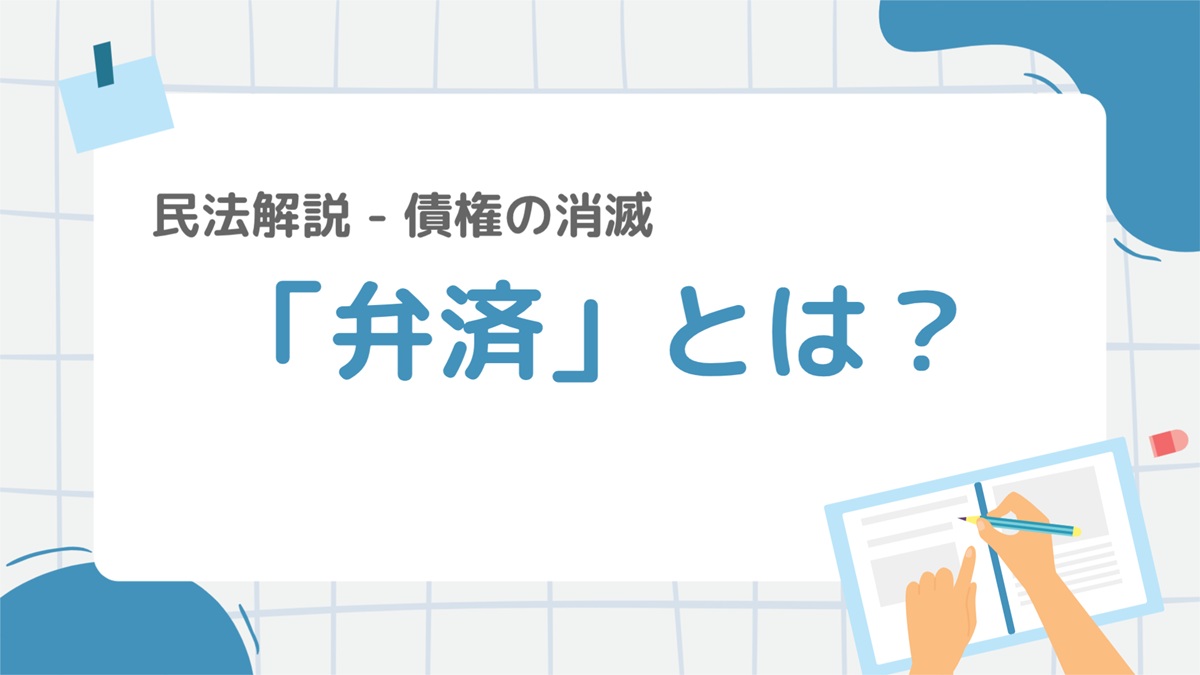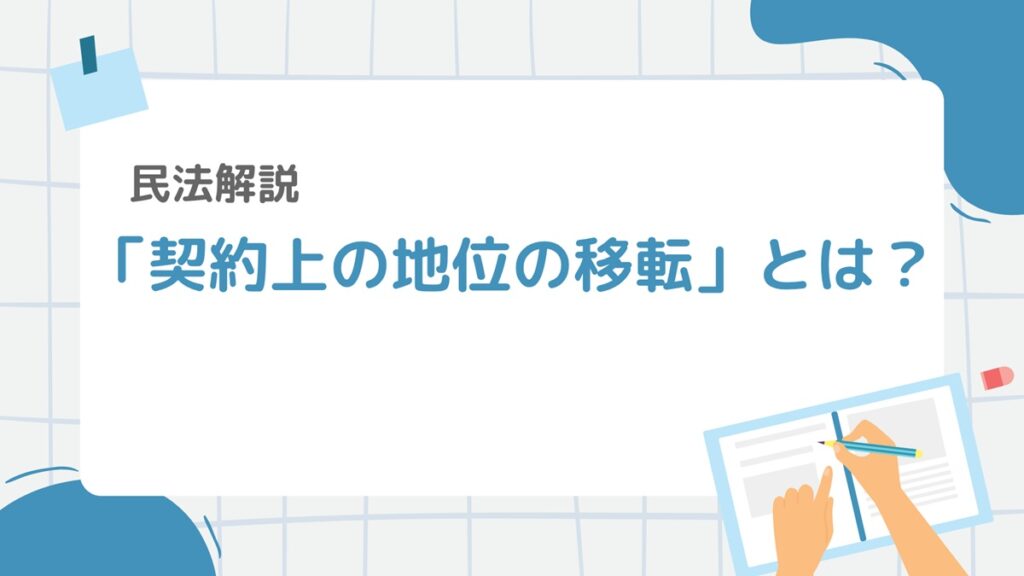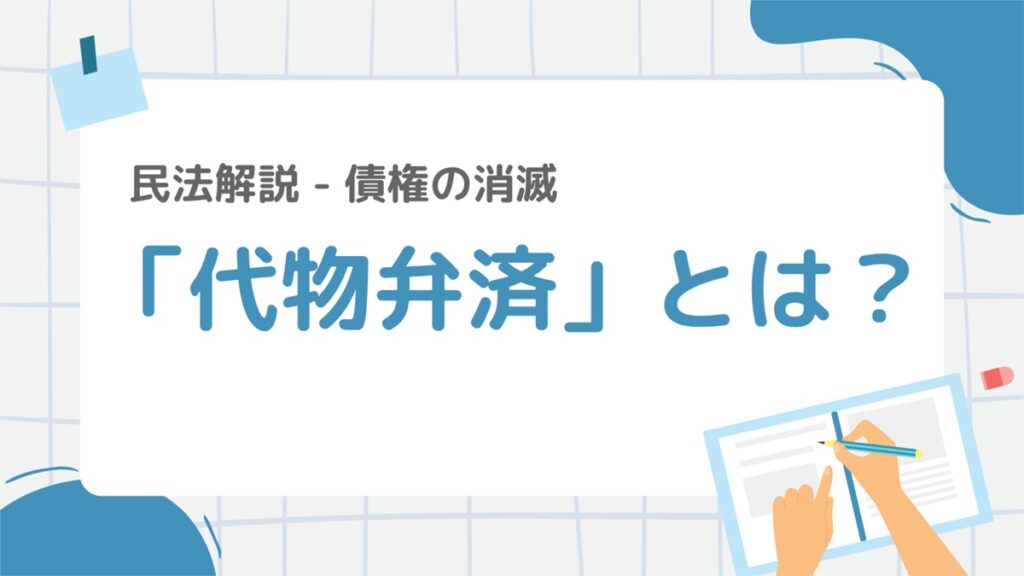- 民法の「弁済」について基本から体系的に学びたい
- 行政書士試験に向けて、弁済の要件や効果を整理したい
- 第三者弁済や弁済による代位などの細かいポイントまでしっかり押さえたい
弁済とは?
弁済とは、債権の内容に従って、その給付を実現する行為をいいます。
--- config: theme: neutral --- sequenceDiagram actor A(売主) actor B(買主) note over A(売主),B(買主): 売買契約(8月1日) A(売主) ->> B(買主):引渡し(9月1日) B(買主) ->> A(売主):代金支払い(9月1日)
AとBは、8月1日にAが所有する土地をBに売却する契約を結びました。契約では、履行期(実際の引き渡しや支払いの期限)を9月1日と定めていました。そして、約束通り9月1日に、Aは土地を引き渡し、Bは売買代金を支払いました。
事例1のケースでは
Aの「代金請求権」と
Bの「土地引渡請求権」
が存在しており、それぞれの給付(代金支払い・土地引渡し)が弁済に当たります。
弁済の要件
弁済は、原則として「債務の本旨に従った内容」でなければなりません。1
何が「債務の本旨に従うか」は当事者の合意によりますが、民法にも補助的なルールが定められています。
- 特定物債権
債権の発生原因や取引上の社会通念に照らして、引渡し時の品質を特定できない場合には、引渡し時点での現状のままでその物を引き渡す必要があります(483条)。 - 種類債権
中等の品質を有する物を給付しなければなりません(401条1項)。
弁済の場所
弁済場所は、通常、当事者の合意または商習慣により決まります。
決まっていない場合は以下の通りです(484条1項)。
- 特定物の引渡しは⇒債権発生の時にその物が存在した場所
- その他の弁済⇒債権者の現在の住所
✅あわせてチェック
商法では、商行為の特則が定められています。👉商行為の特則(債務の履行場所)
弁済の費用
弁済にかかる費用は、原則(特に定めがない場合)として債務者負担です(485条本文)。
ただし、債権者が住所移転などにより費用が増えた場合、その増加分は債権者が負担します(485条但書)。
第三者弁済とは?
第三者弁済とは、第三者が他人の債務を自己の名で弁済することをいいます(474条1項)。
原則として自由に認められますが、以下のような場合には制限されます。
- 債権の性質が許さない場合(474条4項)2
- 当事者が反対の意思を表示した場合(474条4項)
- 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者が債務者または債権者の意思に反して弁済した場合(474条2項本文・3項本文)3
※債務者の意思に反する時でも、そのことを債権者が知らなかった場合、弁済は有効(474条2項但書)
※債権者の意思に反する時でも、第三者が債務者の委託を受けて弁済することを債権者が知っていた場合、弁済は有効(474条3項但書)
受領権者に見える者への弁済
原則として、受領権限のない者に弁済しても無効です。
この場合、債務者は真の債権者から請求があれば、再度の弁済を求められることになります。
ただし、
弁済の提供とは?
弁済の提供とは、債務者が準備を整え、債権者に「受け取ってください」と申し出る行為をいいます。
効果
弁済の提供により、債務者は「履行遅滞の責任」を免れることになります(492条)。
その結果、債務者は損害賠償や強制履行を請求されることがなくなり、双務契約でも、契約を解除される心配がなくなります。
方法
弁済の提供は、
原則:債務の本旨に従った現実の提供をしなければなりません(493条本文)。これを「現実の提供」といいます。
ただし、
・債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合や、
・債務の履行に債権者の行為が必要な場合には、
弁済の準備をしたことを通知し、受領を催告することで足ります(493条但書)。これを「口頭の提供」といいます。56
弁済による代位とは?
弁済による代位(代位弁済)とは、第三者が債務者に代わって弁済し、元の債権者の権利を引き継ぐことをいいます(499条)。
--- config: theme: neutral --- sequenceDiagram participant A所有の建物 actor A_債務者_抵当権設定者 actor B_債権者_抵当権者 actor C_保証人 B_債権者_抵当権者 ->> A_債務者_抵当権設定者:2,000万円 activate B_債権者_抵当権者 B_債権者_抵当権者 -->> A所有の建物:抵当権 C_保証人 ->> B_債権者_抵当権者:代位弁済 B_債権者_抵当権者 -->> C_保証人:抵当権の移転 deactivate B_債権者_抵当権者 activate C_保証人 C_保証人 -->> A所有の建物:抵当権 C_保証人 ->> A_債務者_抵当権設定者:求償権 deactivate C_保証人
Aは、Bから2,000万円を借り入れ、その借金を担保するために、自分の所有する建物に抵当権を設定しました。Cはこの借金について保証人となっていましたが、最終的にCがAに代わってBへ返済を行いました。
事例2の場合、は
弁済による代位の要件
弁済による代位が認められるには、正当な利益を有する者であることが必要です(500条括弧書)。
「正当な利益を有する者」とは、例えば以下の者を指します。
- 債権者との関係では、自ら債務を負うが、債務者との関係では実質上他人の債務の弁済となるもの(連帯債務者・保証人)
- 自らは債務を負わないが、債務者の意思に反してでも弁済しうる利害関係を有する第三者(物上保証人・抵当不動産の第三取得者・後順位抵当権者)
なお、正当な利益を有しない者が弁済した場合は、
・債権者から代位弁済があった事実を債務者に通知するか、
・債務者が代位弁済を承諾しなければ、
弁済による代位を第三者に対抗することはできません(500条、467条)。
弁済による代位の効果
代位した者は、自己の権利に基づいて求償することができる範囲内で、元の債権者が有していた一切の権利を行使することができます。7
代位をなすべき者が複数の場合
- 保証人と第三者の関係
第三取得者は、保証人に対して代位することができない(501条3項1号) - 第三取得者相互間・物上保証人相互間の関係
第三取得者・物上保証人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者・物上保証人に対して代位する(501条3項2号・3号) - 保証人と物上保証人の関係
保証人と物上保証人の間においては、その数に応じて、債権者に代位するが、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、代位する(501条3項4号)
まとめ
弁済は、債権の履行として非常に重要なテーマです。
第三者による弁済や代位など、行政書士試験でも狙われやすい論点なので、しっかり押さえておきましょう!
- 参考:債務者が元本の他、利息・費用を支払うべき場合において、弁済者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、①費用、②利息、③元本の順で充当しなければならない(489条1項)。 ↩︎
- 具体例:芸術家の創作や講演など ↩︎
- 重要判例:借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反していても、地代を弁済することができる(最判昭63.7.1) ↩︎
- 具体例:銀行預金の通帳・印鑑を所持している泥棒、債権譲渡が無効な場合の債権譲受人など ↩︎
- 重要判例:債権者が契約の存在を否定する等、弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行責任を免れる(最大判昭32.6.5) ↩︎
- 具体例:「債権者の行為を要するとき」の例として、取立債務の場合や、相手方の持ってきた車を修理する債務のように債権者の先行的協力行為が必要とされる場合など ↩︎
- 参考:債権の一部について代位弁済があったときでも、債権者は単独で抵当権を実行でき(502条2項)、配当についても、債権者が代位者に優先する(502条3項)。 ↩︎