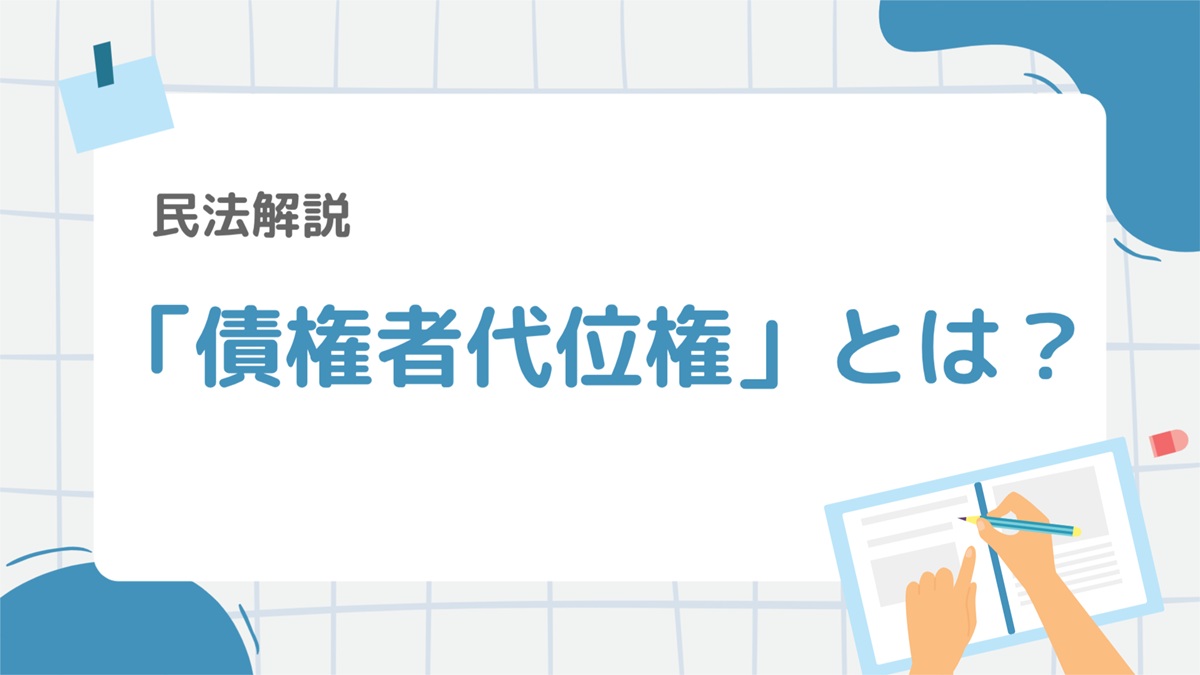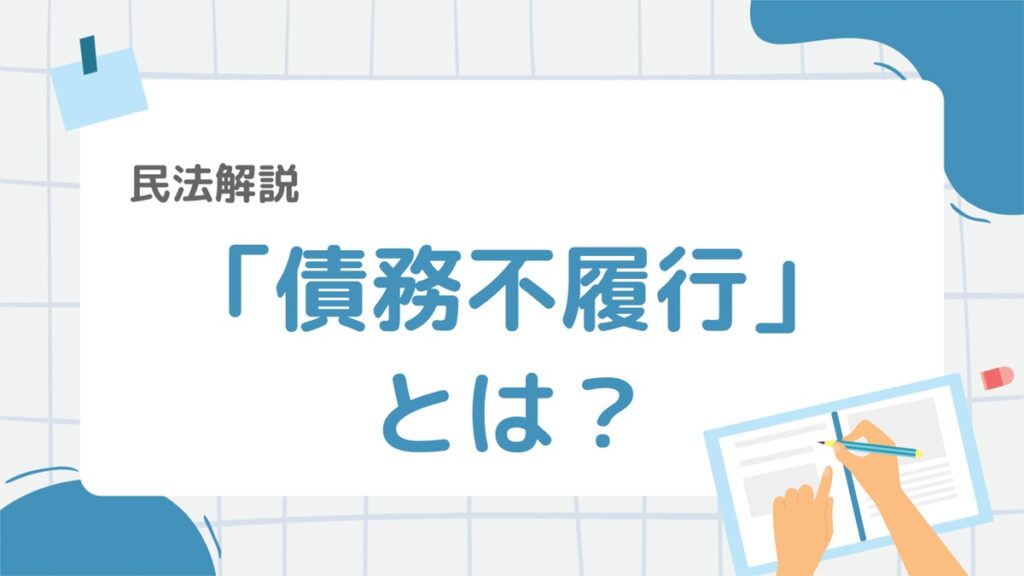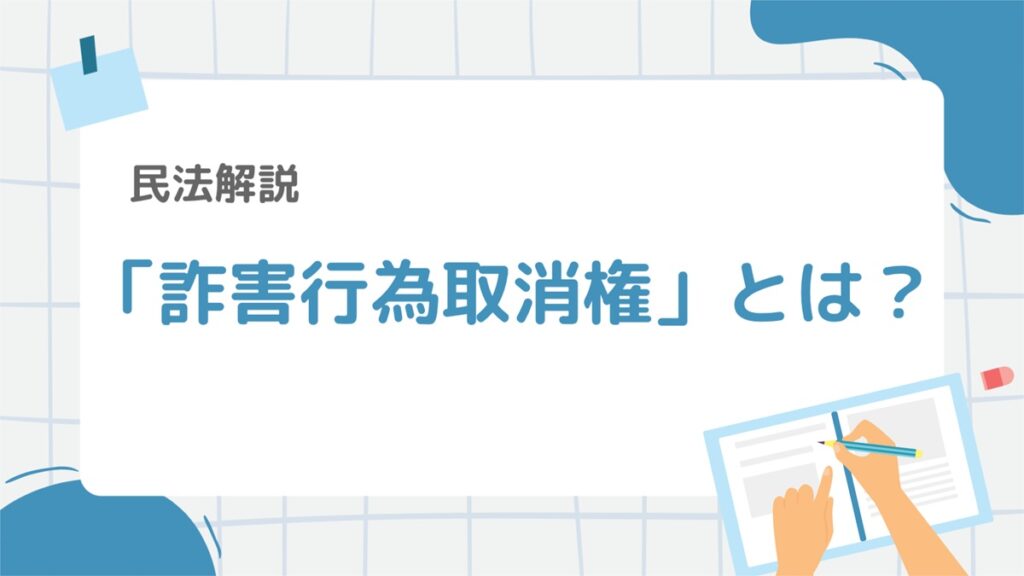債権者代位権とは?
---
config:
theme: neutral
---
graph LR
A("👨💼<br>A<br>債権者")--100万円の債権-->B("🤵♀️<br>B<br>債務者<br>【無資力】")
B--100万円の債権-->C("🧑🏭<br>C<br>第三債務者")
A--変わって行使-->CAは、Bに対して100万円を貸しており、つまり100万円の貸金債権を持っていました。
一方で、BもCに対して同額の100万円を貸しており、Cに対する貸金債権を有していました。ところが、Bには無資力にもかかわらず、Cに対して支払い請求をしようとしなかったため、Aは債権者代位権を行使して、Bに代わってCに対し100万円の支払いを請求しました。
債権者代位権とは、債務者Bが自らの権利を行使しない場合に、債権者Aが債務者Bに代わってその権利を行使することをいいます。
この制度の目的は、強制執行の準備として、債務者の責任財産1を保全することにあります。
要件
債権保全の必要性
債権者は、自己の債権を保全するため必要がある場合、債務者に属する権利(被代位権利)を行使することができます(423条1項本文)。そのため、債権保全の必要性が要件とされていいます。
ここでいう債権保全の必要性とは、債務者が無資力であることを意味します。2
ただし、金銭債権の保全以外を目的とする債権者代位権の転用(423条の7)の場合には、債務者の無資力は要件とされていません。3
被代位権利が債務者の「一身専属権」・「差押えを禁じられた権利」ではないこと
債務者の一身に専属する権利や、差押えを禁じられた権利は、債権者代位権の対象にはなりません(423条1項但書)。
「一身に専属する権利」とは、特定の権利主体だけが行使できる権利のことで、その該当性は個々の権利の性質や規定の趣旨を考慮して判断されます。例えば、認知請求権(787条)など、身分に関わる権利の多くがこれに該当すると考えられています。
| 代位行使できる | 代位行使できない |
|---|---|
| 登記請求権(大判明43.7.6) 妨害排除請求権 賃借人の場合:大判昭4.12.16 抵当権者の場合:最大判平11.11.24等 債権者代位権(最判昭39.4.17) 消滅時効の援用権(最判昭43.9.26) 取消権や解除権などの形成権 | 債権譲渡の通知(大判昭5.10.10) 名誉棄損による慰謝料請求権(最判昭58.10.6) ※当事者間で具体的な金額が確定したときは、代位行使できる 遺留分4遺留分侵害額請求権5(最判平13.11.22) ※権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合は、代位行使できる。 |
債権の履行期が到来していること
債権者は、その債権の期限が到来していない間は、被代位権利を行使することができません(423条2項本文)。
ただし、保存行為については、履行気が到来していなくても行使が認められます(423条2項但書)。6
債務者が権利を行使していないこと
債権者代位権を行使するには、債務者が自らその権利を行使していないことが必要です(最判昭28.12.14)。
これは、もともと債務者のみんが自由に行使できる権利に対して、債権者が干渉する以上、その干渉は必要最小限にとどめるべきであるという考えに基づいています。
行使方法
権利行使の名義
代位債権者は、債務者の代理人として権利行使をするわけではなく、自己の名で権利を行使します。
代位行使の範囲
代位債権者は、被代位権利の目的が可分である場合、自己の債権額の範囲でのみ、被代位権利を行使することができます(423条の2)。
この理由は、債権者代位権が債権の保全を目的として例外的に認められる制度であり、債務者の財産的自由を制約するものであるため、その行使範囲もも必要最小限に限られるべきだからです。
請求の内容
代位行使する権利の種類によって、請求の内容は異なります。
- 金銭債権・動産の引渡請求権
代位債権者は、直接自己へ給付を請求することができます(423条の3)。 - 賃貸人の妨害排除請求権
代位債権者は、直接自己に対して明渡しを請求することができます(最判昭29.9.24)。 - 所有権移転登記請求権
債務者名義への移転登記請求はできますが、代位債権者自身の名義に直接移転登記請求をすることはできません。
効果
債権者が被代位権利を行使した場合でも、債務者は被代位権利について、自ら取立てやその他の処分を行うことができます。また、相手方も被代位権利について、債務者に対して履行することができます(423条の5)。
- 責任財産:強制執行の対象物として、ある請求の実現のために提供される財産のこと ↩︎
- 重要判例:交通事故の被害者が、加害者が保険会社に対して有する自動車対人賠償責任保険の保険金請求権を代位行使する場合、加害者が無資力でなければならない(最判昭49.11.29) ↩︎
- 具体例:賃借人が賃貸人の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使する場合(大判昭4.12.16)
抵当権者が抵当不動産の所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使する場合(最大判平11.11.24)など ↩︎ - 遺留分:相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保しておくこと ↩︎
- 遺留分侵害額請求権:遺留分が侵害された場合に、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利 ↩︎
- 具体例:時効の完成猶予・更新のための請求や、未登記の権利の登記など ↩︎