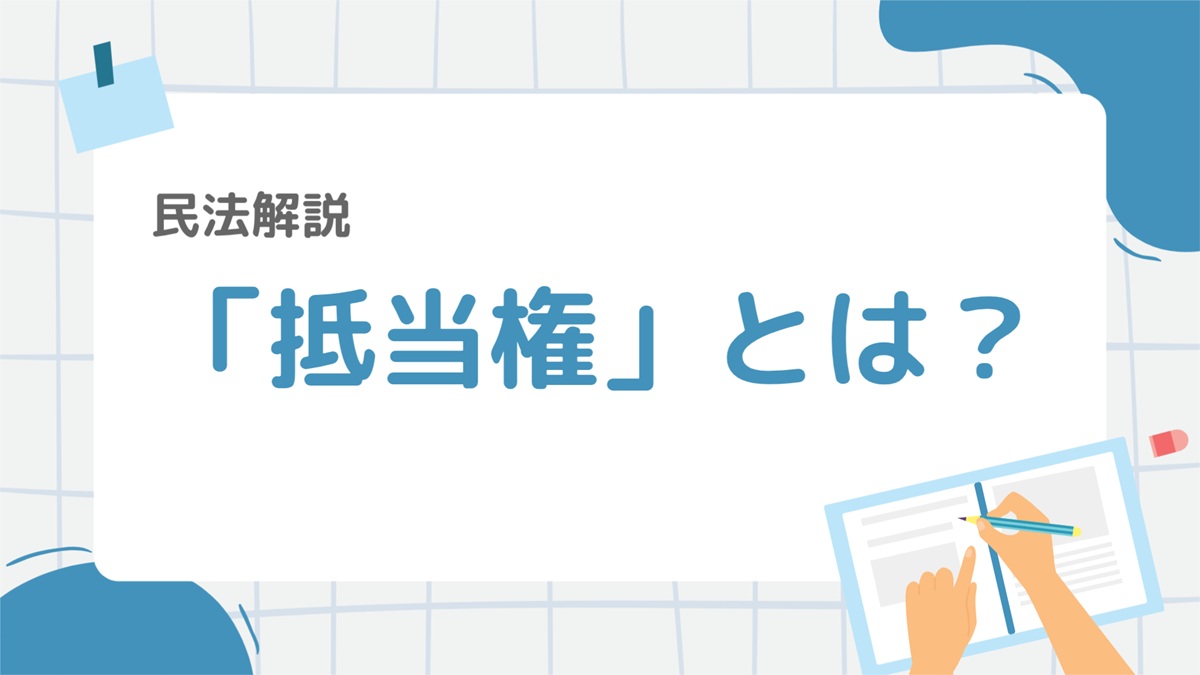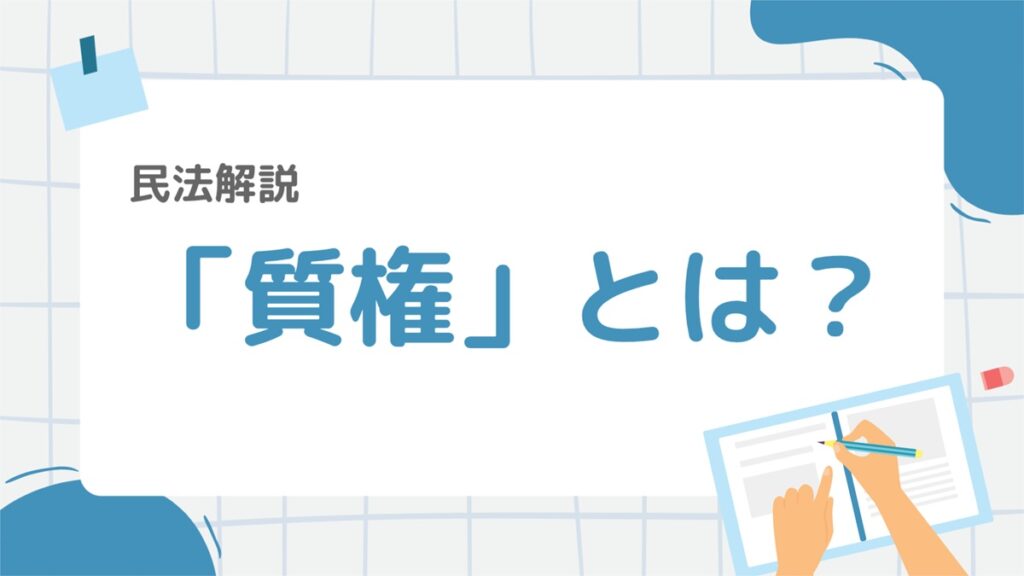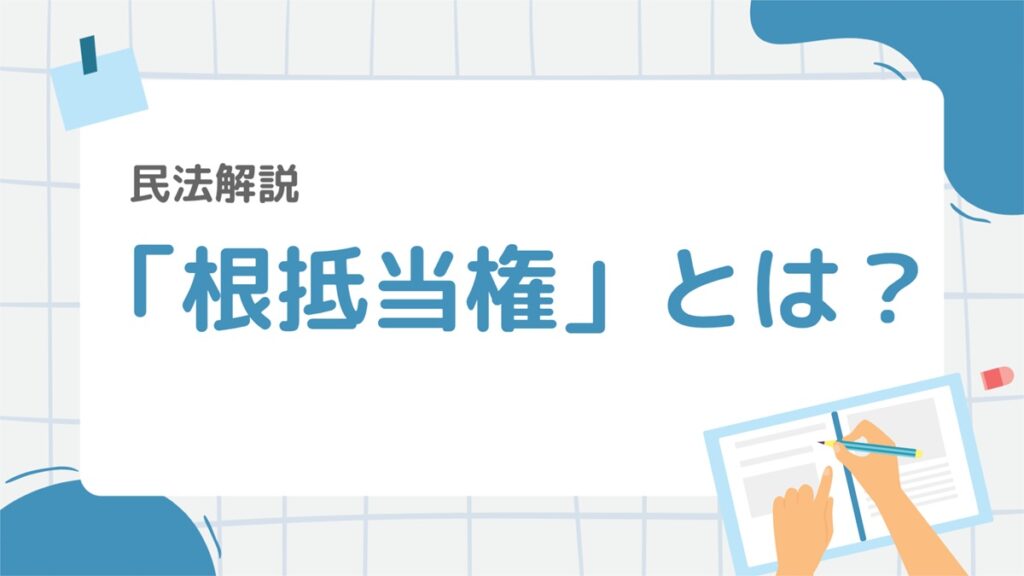抵当権とは?

sequenceDiagram autonumber participant Aの所有する建物 actor A_債務者_抵当権設定者 actor B_債権者_抵当権者 B_債権者_抵当権者 ->> A_債務者_抵当権設定者:貸金債権 A_債務者_抵当権設定者 --> B_債権者_抵当権者:抵当権設定契約 B_債権者_抵当権者 ->> Aの所有する建物:抵当権
Aは、Bから借金をする際に、その返済を担保するため、自分の所有する建物に抵当権を設定する契約を結びました。その後もAは、引き続きその建物に住み続けています。
抵当権とは、債務の返済ができなかったときに、不動産を売って代金を回収できる権利のことです(369条)。債務者や第三者が所有する不動産に設定し、その不動産を使い続けながら担保として差し出すことができます。
ポイントは、占有を移転せずに担保にできる点です。つまり、不動産を債権者に引き渡す必要はなく、債務者は引き続きその不動産を利用できます。
債務の弁済がないときは、抵当権を実行して不動産を競売にかけ、その代金から優先的に弁済を受けることができます。
抵当権と質権の違い
抵当権は、質権と類似した担保物件ですが、以下の点で異なります。
| 比較項目 | 抵当権 | 質権 |
|---|---|---|
| 目的物 | 不動産に限られる (※関連:動産は譲渡担保) | 動産や権利も対象 |
| 占有の移転 | 不要(引き渡しなし) | 必要(引き渡しあり) |
抵当権は、抵当権は占有を移転しないため、不動産の使用を妨げない柔軟な担保手段といえます。
抵当権の設定に関する基本知識
目的物
民法上、抵当権の目的は不動産とされており、動産に抵当権を設定することはできません(369条1項)。
なお、地上権や永小作権も抵当権の目的の対象とすることができます(369条2項)。
被担保債権の範囲
抵当権は付従性を有するため、原則として担保する債権(被担保債権)があることが前提です。
ただし、被担保債権は抵当権設定時点で必ずしも存在している必要はなく、将来の債権や条件付債権も被担保債権となることができます。これを付従性の緩和といいます。
また、抵当権者が利息などの定期金を請求する権利を有している場合、満期となった最後の2年分についてのみ、抵当権を行使することができます(375条1項本文)。
この制限が設けられている理由は、無制限に利息や遅延損害金が担保されると、被担保債権の総額が不明瞭になり、後順位の抵当権者が目的物の担保価値を正確に評価することができなくなるためです。1
抵当権の順位と登記
同じ不動産に複数の抵当権が設定された場合、登記の先後によって順位が決まります(373条)。
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができます。ただし、利害関係を有する者がいる場合は、その承諾を得る必要があります(374条1項)。
さらに、順位の変更を行う際は、登記をしなければ効力が生じません(374条2項)。
抵当権の効力が及ぶ範囲
①付加一体物
抵当権は、抵当権が設定された不動産(抵当不動産)に付加して一体となっている物にも及びます(370条本文)。23
ただし、設定行為に別段の定めがある場合や、債務者の行為に対して詐害行為取消請求が可能な場合には、たとえ付加一体物であっても抵当権の効力は及びません(370条但書)。
②借地権
土地の賃借人が土地上に所有する建物に抵当権を設定した場合、原則として、抵当権の効力は当該土地の賃借権に及びます(最判昭40.5.4)。これは、借地権は建物の従たる権利であるためです。
③果実
抵当権は、担保する債権について不履行があった場合、その後に発生した抵当不動産の果実(収益)にも及びます(371条)。
④物上代位
sequenceDiagram Actor C participant Aの所有する建物 actor A_債務者_抵当権設定者 actor B_債権者_抵当権者 B_債権者_抵当権者 ->> A_債務者_抵当権設定者:①2,500万円 A_債務者_抵当権設定者 --> B_債権者_抵当権者:②抵当権設定契約 B_債権者_抵当権者 ->> Aの所有する建物:③抵当権 C ->> Aの所有する建物:④放火 Aの所有する建物 -->> C:⑤損害賠償請求権 B_債権者_抵当権者 ->> C:⑥物上代位
Bは、Aに対して2,500万円の貸付金債権(お金を貸したことによる権利)を持っており、その債権を担保するために、AとBが共同で所有している建物に抵当権を設定しました。ところがその後、この建物は第三者Cの放火によって焼失してしまいました。
事例2では、建物が焼失しているため、抵当権も消滅すると思えます。しかし、Bが損害賠償請求権を取得し、損害が塡補されているにもかかわらず、Aが抵当権を失うというのは不当といえます。
そこで、抵当権は、その目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭やその他の物(AのCに対する損害賠償請求権)に対しても行使することができます(372条、304条1項本文)。この仕組みを物上代位といいます。
■物上代位の可否
| 物上代位できる | 物上代位できない |
| ①不法行為に基づく損害賠償請求権(大判大6.1.22) ②火災保険金請求権(大連判大12.4.7) ③賃料債権(最判平1.10.27) ④買戻代金債権(最判平11.11.30) | 転貸賃料債権(裁決平12.4.14) ※抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合は物上代位できる |
抵当権者が物上代位を行うには、払渡しまたは引渡しの前に差押えをしなければなりません(372条、304条1項但書)。456
この差押えが求められる理由は、抵当権の効力が及ぶことを知らない第三債務者が、誤って別の相手に弁済してしまうのを防ぐためです。
抵当権侵害と対抗手段
妨害排除請求
第三者が抵当不動産を不法に占有し、その結果、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような場合、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求をすることができます(最大判平11.11.24)。
また、適法な占有権原の設定を受けて抵当不動産を占有する者であっても、その占有が競売手続きを妨害する目的であり、その結果、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられている場合には、同様に妨害排除請求を行うことが可能です(最大判平17.3.10)。7
損害賠償請求
抵当権が侵害され、それによって抵当不動産の交換価値が減少し、被担保債権の弁済を受けることができなくなった場合、抵当権者は侵害者に対して損害賠償請求をすることができます(709条)。8
抵当権と抵当不動産利用権の調整
法定地上権
sequenceDiagram actor C_買受人 participant Aの所有する建物 actor A_債務者_抵当権設定者 actor B_債権者_抵当権者 B_債権者_抵当権者 ->> A_債務者_抵当権設定者:①2000万円 B_債権者_抵当権者 ->> Aの所有する建物:抵当権 Aの所有する建物 ->> C_買受人:③競売
Aは、Bから2,000万円を借り入れました。この借金を担保するために、Aは自分が所有している土地と建物のうち「建物のみ」に抵当権を設定しました。その後、この抵当権が実行され、建物は競売にかけられ、Cがその建物を購入しました。
事例3の場合、買受人Cが建物の所有権を取得しても、土地の利用権を持たないという不都合が生じます。そこで、法律上当然に買受人のために地上権が発生するとされています(388条前段)。この権利を法定地上権といいます。
法定地上権の要件
また、後順位抵当権が存在する場合や、土地・建物が共有であった場合には、以下のような対応が必要です。
■後順位抵当権と法定地上権
| 1番抵当権を建物に設定 | 1番抵当権を土地に設定 | |
| 1番抵当権設定時⇒土地上に建物なし 2番抵当権設定時⇒土地上に建物あり | – | × (最判昭47.11.2) |
| 1番抵当権設定時⇒土地・建物別人所有 2番抵当権設定時⇒土地・建物同一人所有 | 〇 (大判昭14.7.26) | ×14 (最判平2.1.22) |
〇:成立する ×:成立しない
■共有と法定地上権
| 建物に抵当権設定 | 土地に抵当権設定 | |
| 建物が共有 | 〇 (通説) | 〇 (最判昭46.12.21) |
| 土地が共有 | × (最判昭44.11.4) | × (最判昭29.12.23) |
〇:成立する ×:成立しない
一括競売
更地に抵当権を設定された後に建物が築造された場合、その建物のために法定地上権が成立しません。このような建物があると、土地のみを競売にかけることが困難になります。
そこで、抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときには、抵当権者は土地と建物を一括して競売することができます(389条1項本文)。ただし、抵当権者の優先弁済権は土地の代価についてのみ行使できます(389条1項但書)。
抵当不動産の賃借人を守る仕組み
抵当権の設定登記がされた後に抵当建物に対して賃借権が設定された場合、その賃借権は抵当権に対抗できません。そのため、競売により建物を取得した買受人が現れた場合、賃借人は退去しなければならないことになります(177条)。
しかし、それでは賃借人にとってあまりに不利益が大きいため、法律上、賃借人を保護する制度が設けられています。
■抵当不動産の賃借人の保護制度
- ①同意の登記による賃貸借の対抗制度
-
登記をした賃貸借契約について、その登記前に登記された抵当権を持つすべての抵当権者が同意し、かつ、その同意の登記がある場合には、賃借人は同意をした抵当権者に対して賃貸借契約を対抗することができます(387条1項)。
- ②建物使用者の明渡猶予制度
-
抵当建物の使用者は、競売により買受人が建物を取得した場合でも、買受の時から6か月間は建物の明け渡しを猶予されます(395条1項)。ただし、その間の建物使用の対価を支払う義務があります(395条2項)。15
抵当権の消滅に関する制度
代価弁済・抵当権消滅請求
sequenceDiagram actor C_第三取得者 participant A所有の土地 actor A_債務者_抵当権設定者 actor B_債権者_抵当権者 B_債権者_抵当権者 ->> A_債務者_抵当権設定者:①1500万円 B_債権者_抵当権者 ->> A所有の土地:②抵当権 A所有の土地 ->> C_第三取得者:③譲渡 C_第三取得者 ->> B_債権者_抵当権者:④代価弁済 C_第三取得者 ->> B_債権者_抵当権者:⑤抵当権消滅請求
Aは、Bから1,500万円を借り入れ、その借金を担保するために、自分が所有している土地に抵当権を設定しました。その後、Aはこの土地を第三者であるCに譲渡しました。
事例4のCのように、抵当不動産の所有権を取得した者を、第三取得者といいます。
この第三取得者は、いつ抵当権が実行されて所有権を失うかわからないため、抵当権を消滅させて所有権を安定させる必要があります。
そこで、抵当権者が請求する代価弁済(378条)や、第三取得者が請求する抵当権消滅請求(379条)といった制度が設けられています。
■代価弁済と抵当権消滅請求
〇:なし得る ×:なし得ない
抵当権の消滅時効
抵当権は、債務者および抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しません(396条)。これは、抵当権の消滅に関する付従性を定めたものであり、債務者および抵当権設定者との関係では、被担保債権が消滅しない限り、抵当権のみが時効によって消滅することはありません。17
※関連:消滅時効
目的物の取得時効による消滅
債務者または抵当権設定者でない者が、抵当不動産について取得時効の要件を満たす占有をした場合、抵当権は消滅します(397条)。
この規定の趣旨は、抵当不動産が取得時効によって取得された場合に、その効果を債務者や抵当債債権券設定者にまで及ぼすことは適切でないと考えられるため、これらの者を除外する点にあります。
目的たる用益権の放棄
地上権または永小作権を抵当権の目的とした地上権者または永小作人は、その権利を放棄しても、抵当権者に対抗することはできません(398条)。
これは、抵当権の目的物として拘束を受けている以上、その権利の主体であっても自由に消滅させられるものではないためです。18
まとめ
抵当権は、不動産を担保にしつつ、占有を移転せずに債権を保全できる便利な制度です。行政書士試験では、質権との違い・登記の優先順位・法定地上権や物上代位の仕組みなど、周辺知識までしっかり押さえることが重要です。
- 重要判例:被担保債権の範囲が制限されているのは後順位抵当権者の利益のためであるから、債務者自身が元本と最後の2年分の利息を提供して抵当権の抹消を請求することはできない。債務者は債務の全額を弁済することが必要である(大判大4.9.15) ↩︎
- 重要判例:抵当権の効力は、特段の事情の無い限り、抵当不動産の従物にも及び、従物について別個に対抗要件を具備しなくても、第三者に対抗することができる(最判昭44.3.28) ↩︎
- 参考:石垣や立木などの付合物は、不動産の所有権に吸収されるから、付合する時期が抵当権設定前であるか設定後であるかを問わず「付加して一体となっている物」に含まれる ↩︎
- 重要判例:抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて、物上代位権を行使することができる。(最判平10.1.30) ↩︎
- 重要判例:債権について一般債権者の差押えと、抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合には、両者の優劣は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決すべきである’(最判平10.3.26) ↩︎
- 需要判例:対抗要件を備えた抵当権者が、物上代位権の行使として目的債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない(最判平13.3.13) ↩︎
- 参考:抵当不動産の所有者が、抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には、抵当権者は、占有者に対し、直接自己への抵当不動産の明け渡しを求めることもできる。 ↩︎
- 重要判例:抵当権者は、抵当権を実行する前であっても、被担保債権の弁済期が到来していれば、損害賠償請求をすることができる(大判昭7.5.27) ↩︎
- 重要判例:土地に抵当権を設定した当時、建物が存在していれば、後にその建物が滅失して再築された場合でも、旧建物を基準とする法定地上権が成立する(大判昭10.8.10) ↩︎
- 重要判例:土地および地上建物に共同抵当権を設定した後に、建物が取り壊され、土地上に新しい建物が建築された場合、特段の事情の無い限り、新建物のために法定地上権は成立しない(最判平9.2.14) ↩︎
- 重要判例:土地と建物が同一の所有者に属していれば、登記名義が同一でなくても、この要件を満たす(最判昭48.9.18) ↩︎
- 重要判例:抵当権設定当時に土地及び建物の所有者が同一であるときは、抵当権設定後に土地または建物が第三者に譲渡された場合でも、法定地上権は成立する(大連判大12.12.14) ↩︎
- 重要判例:抵当権設定当時に、土地および建物の所有者が異なるときは、抵当権の実行による競落の際に土地および建物が同一人に帰属していても、法定地上権は成立しない(最判昭44.2.14) ↩︎
- 重要判例:1番抵当権が消滅した後に、2番抵当権が実行された場合には、法定地上権が成立する(最判平19.7.6) ↩︎
- 参考:買受人の買受の時より後に、建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し、相当の期間を定めてその1か月分以上の支払いの催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、明渡猶予制度は適用されない(395条2項)。 ↩︎
- 参考:地上権取得者が代価弁済をする場合、抵当権は消滅せず、地上権に対抗できなくなるのみ ↩︎
- 396条の反対解釈から、抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権者との関係では、抵当権は、被担保債権とは別に20年の消滅時効(166条2項)によって消滅する(大判昭15.11.26) ↩︎
- 重要判例:着地上の建物に抵当権を設定した者の借地権の放棄も、抵当権者に対抗することができない(大判大11.11.24) ↩︎