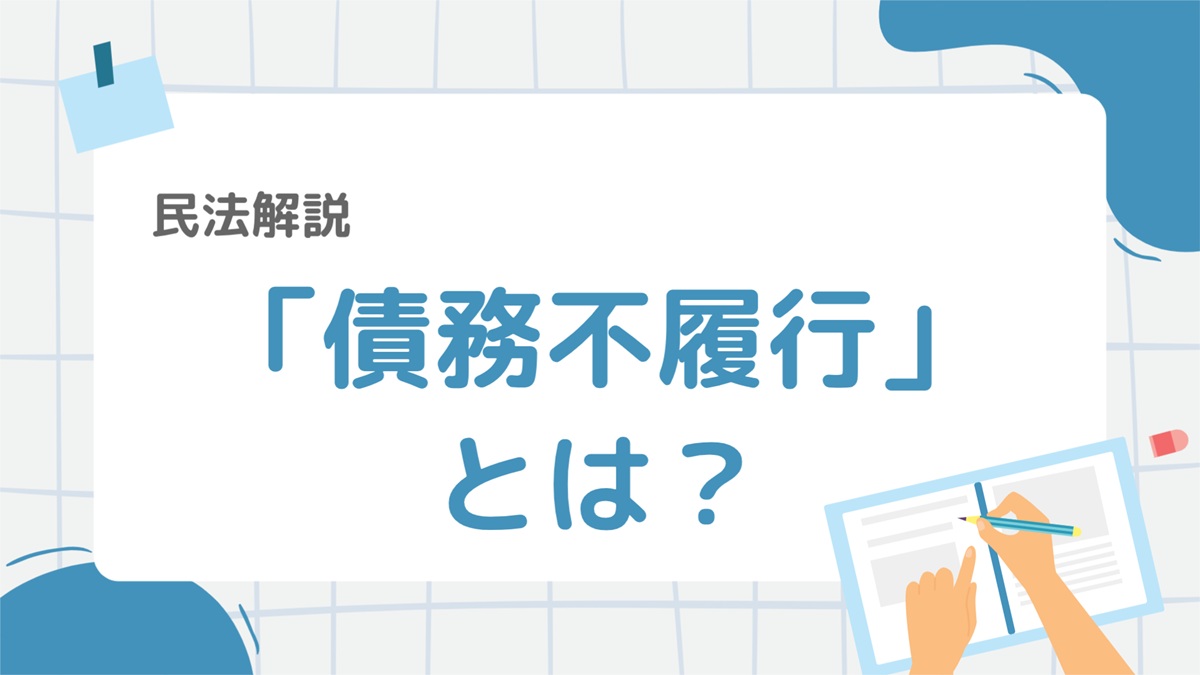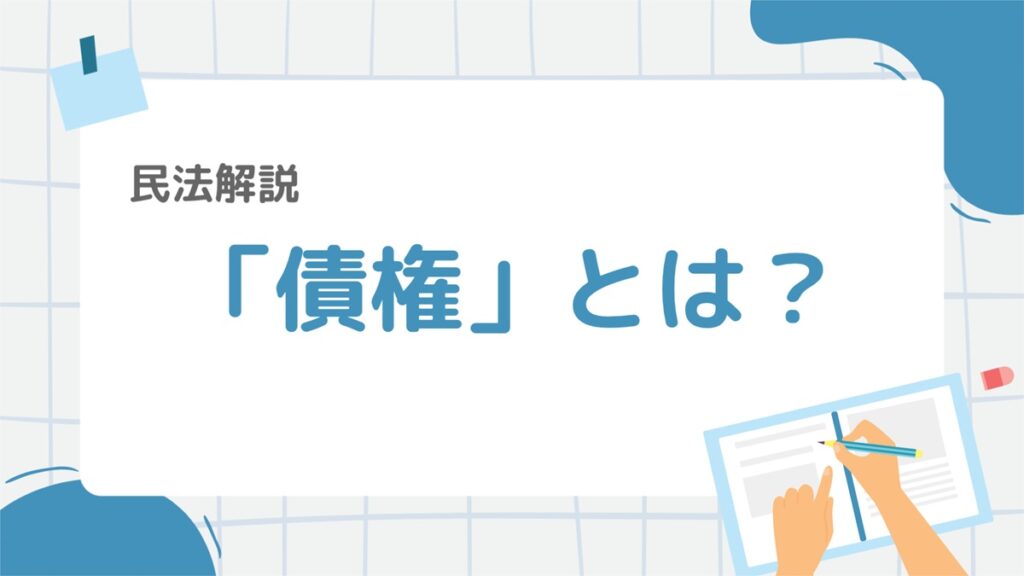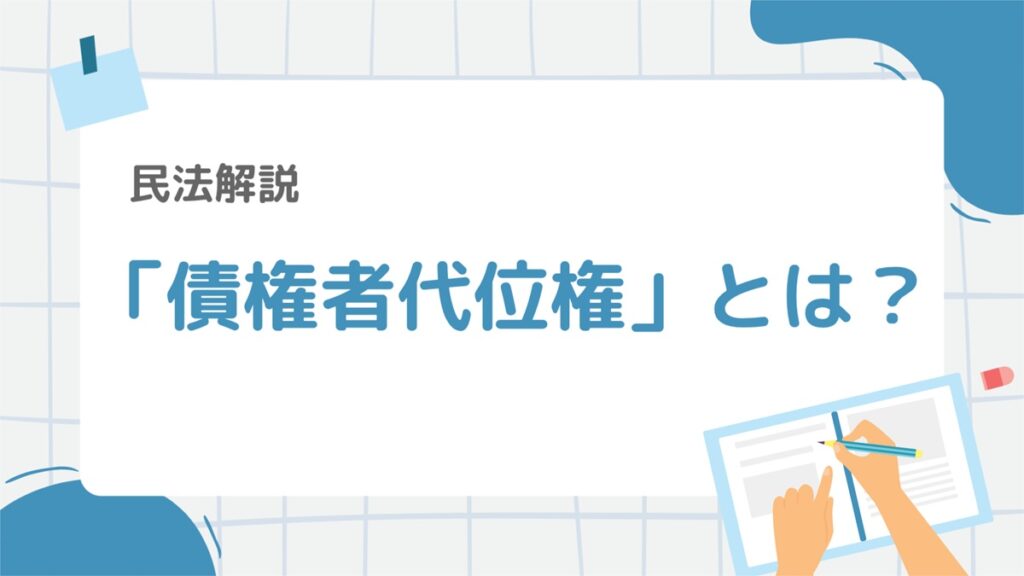債務不履行とは?
債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行を行わないことを指します。
債務不履行には、以下の3つの類型があります。
- 期限を過ぎる履行遅滞
- 履行が不可能となる履行不能
- 形の上で履行はなされたが、それが完全な履行ではない不完全履行
これらのいずれかに該当する場合、債務不履行として責任を問われることがあります。
債務不履行の要件
債務不履行の事実
- ①履行遅滞
-
履行遅滞と認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。1
■消滅時効(客観的期間)と履行遅滞の起算点
消滅時効(客観的期間)
の起算点履行遅滞の起算点 確定期限のある債権 期限到来時 期限到来時
(412条1項)不確定期限の
ある債権期限到来時 債務者が期限到来後、履行の請求を受けたときまたは期限の到来を知った時のいずれか早い時(412条2項) 期限の定めのない債権 債権成立時 履行の請求を受けたとき
(412条3項)返還時期の定めのない消費貸借 消費貸借契約の時から相当期間の経過後 貸主が返還の催告をしてから相当期間の経過後
(591条1項)債務不履行による損害賠償請求権 本来の債務の履行を請求できるとき(最判平10.4.24) 履行の請求を受けたとき
(412条3項)不法行為による損害賠償請求権 ①被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時(724条1号)
②不法行為時(724条2号)不法行為時
(最判昭37.9.4) - ②履行不能
-
履行が不能かどうかは、契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして判断されます(412条の2第1項)。
例えば、引き渡すべき目的物が滅失した場合や、不動産が第三者に二重に譲渡され登記が経由された場合なども履行不能となります。2
- ③不完全履行
-
不完全履行は、損害の発生の仕方によって、大きく大きく2つの類型に分けられます。
損害の発生・因果関係
債務不履行による損害賠償責任が発生するためには、損害の発生と債務不履行の事実との間に因果関係があることが必要です。5
金銭債務の特則
金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償については、債務者は不可抗力を理由に抗弁することができません(419条3項)。そのため、帰責事由の有無に関わらず損害賠償責任を負います。
これは、金銭は相当の利息を支払えば容易に入手できるものであり、履行不能が想定されていないためです。
また、債権者は損害を証明する必要がなく(419条2項)。債務不履行の事実のみを証明すれば足ります。
債務不履行の効果
債務不履行があった場合、債権者は以下の2つの措置をとることができます。
履行の強制
債務者が任意に債務の履行を行わない場合、債権者は裁判所に対して履行の強制を請求することができます(414条1項本文)。このように、債務不履行が発生した場合、債権者には履行請求権が認められ、強制的に債権を実現することが可能です。6
ただし、具体的にどのような方法で債権が実現されるかは、以下の通り、債務の種類によって異なります。
| 意味 | 債務の態様 | 具体例 | |
| 直接強制 | 債務者の財産に対して実力行使し、債務者の意思を無視して債権の内容を実現する方法 | 引渡債務 | 金銭債務、特定物債務・種類債務 |
| 代替執行 | 債務者に代わって第三者に債務の内容を実現させ、それを要する費用を債務者から強制的に徴収する方法 | 代替的行為債務 | 建物を収去する債務、謝罪広告をする債務 |
| 間接強制 | 債務を履行しないことに対し、一定額の金銭の支払いを命じることにより、債務者の履行を経済的に強制する方法 | 引渡債務、行為債務(被代替的も含む)、不作為債務 | 騒音を出さない債務、ある人に会ってはいけない債務 |
損害賠償請求
- ①要件
-
債務者がその債務の本旨に従った履行を行わない場合または債務の履行が不能である場合は、債権者は、そのことによって生じた損害の賠償を請求することができます(415条1項本文)。
ただし、その債務不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものである場合は、損害賠償を請求することはできません(415条1項但書)。
- ②履行補助者を用いた場合の責任
-
履行補助者とは、債務者が債務を履行する際に使用する者のことを指します。7
この履行補助者の行為は、債務不履行が認められるかどうか、また「債務者の責めに帰すことができない事由」に該当するかどうかを断する際に考慮されることがあります。89
- ③損害賠償の方法
-
損害賠償は、特別な意思表示がない限り、金銭によってその額が定められます(417条)。
このように、損害賠償の方法としては、金銭の支払いによって損害が発生しなかった状態を回復する「金銭賠償」が原則とされています。 - ④損害賠償の範囲
-
債務不履行に対する損害賠償請求は、通常生ずべき損害の賠償を目的とします(416条)。
この規定の趣旨は、債務不履行と関連するすべての損害を賠償の対象としてしますと、賠償しなければならない損害が際限なく拡大する可能性があるため、合理的にその範囲を制限することになります。ただし、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであった場合には、債権者はその賠償を請求することができます(416条2項)。10
- ⑤損害額の調整:過失相殺
-
債務不履行またはこれによる損害の発生・拡大について、債権者にも過失がある場合、裁判所はこれを考慮し、損害賠償の責任および賠償額を定めることができます(418条)。これを「過失相殺」といいます。
これは、損害の発生や拡大の原因が債務者の過失だけでなく、債権者の過失にもある場合に、すべての損害を債務者に負担させることが不公平であるためです。
- ⑥損害賠償額の予定
-
当事者は、債務不履行に関する損害賠償の額を予定を決めておくことができます(420条1項)。
これは、債務不履行による損害賠償をめぐって、損害の有無や範囲に関する争いが発生しやすいため、事前に定めておくことで紛争を防ぐ目的があります。11
受領遅滞
受領遅滞とは?
受領遅滞とは、債権者が債務の履行を受けることを拒否したり、受け取ることができない状態のことを指します。12
受領遅滞の効果
- ①注意義務の軽減
-
債権の目的が特定物の引渡しである場合、債務者は通常、引渡しをするまで、善管注意義務を負います(400条)。
しかし、受領遅滞が発生した場合には、債務者は履行の提供を行った時点から引渡しを完了するまで、自己の財産に対するのと同一の注意を払えば足りるとされています(413条1項)。
- ②増加費用の負担
-
受領遅滞によって債務の履行にかかる費用が増加した場合、その増加額は債権者が負担することになります(413条2項)。
不法行為責任との違い
不法行為による損害賠償責任と債務不履行責任による損害賠償責任の違いは以下の表のとおりです。
| 債務不履行責任 | 不法行為責任 | |
| 立証責任 | 債務者が自己の帰責事由の不存在について立証責任を負う(大判大14.2.27) | 被害者(債権者)が加害者(債務者)の故意・過失の存在について立証責任を負う |
| 消滅時効 | 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年(166条1項1号) 本来の債務の履行を請求できる時から10年(166条1項2号・最判平10.4.24) | 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(724条1号) ※生命身体を害する場合は5年(724条の2) 不法行為の時から20年(724条2号) |
| 履行遅滞 | 債権者から履行の請求を受けたとき(413条3項) | 不法行為の時(最判昭37.9.4) |
| 過失相殺 | 損害賠償責任の免除または損害賠償額の減額を必ずしなければならない(418条) | 損害賠償額の減額のみを任意にすることができる(722条2項) |
- 参考:履行遅滞が生じた後に不可抗力によって債務が履行不能となった場合、債務者は、履行不能による損害につき賠償責任を負う(413条の2第1項) ↩︎
- 重要判例:仮登記が備えられただけでは、未だ履行不能とはならない(最判昭35.4.21)。 ↩︎
- 具体例:スーパーで野菜を買ったところ、傷んでいて食べれなかった場合など ↩︎
- 具体例:スーパーで弁当を買ったところ、傷んでいた者の気付かずに飲んでしまい、食中毒になり入院した場合など。 ↩︎
- 参考:損害には、財産に対して加えられた財産的損害と、それ以外の精神的損害の両方が含まれる ↩︎
- 重要判例:夫婦の同居義務(752条)は、債務者の自由意思の尊重という観点から、直接強制・間接強制とも許されない(大決昭5.9.30) ↩︎
- 具体例:家具の引渡債務を負っている家具屋が依頼した運送業者など ↩︎
- 重要判例:賃借人が賃貸人の承諾を得て賃貸不動産を転貸したが、転借人の過失により同不動産を損傷させた場合、賃借人は転借人の選任・監督について過失がなくても、賃貸人に対して債務不履行責任を負う(大判昭4.6.19) ↩︎
- 参考:受寄者が寄託者の承諾を得て寄託物を第三者に保管させたが、当該第三者の過失により寄託物を損傷させた場合、受寄者は寄託者に対して債務不履行責任を負う ↩︎
- 重要判例:416条2項の文言上は「当事者」とされているが、ここでいう予見すべきであったかどうかは、債務者にとってのものであると解されている(大判大7.8.27) ↩︎
- 参考:違約金は、債務不履行に対する制裁であり損害の補填を目的とするものではないので、損害賠償額の予定と性質を異にするものであるが、民法上は、賠償額の予定と推定されることになる(420条3項) ↩︎
- 参考:受領遅滞の場合、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみたされる(413条の2第2項) ↩︎