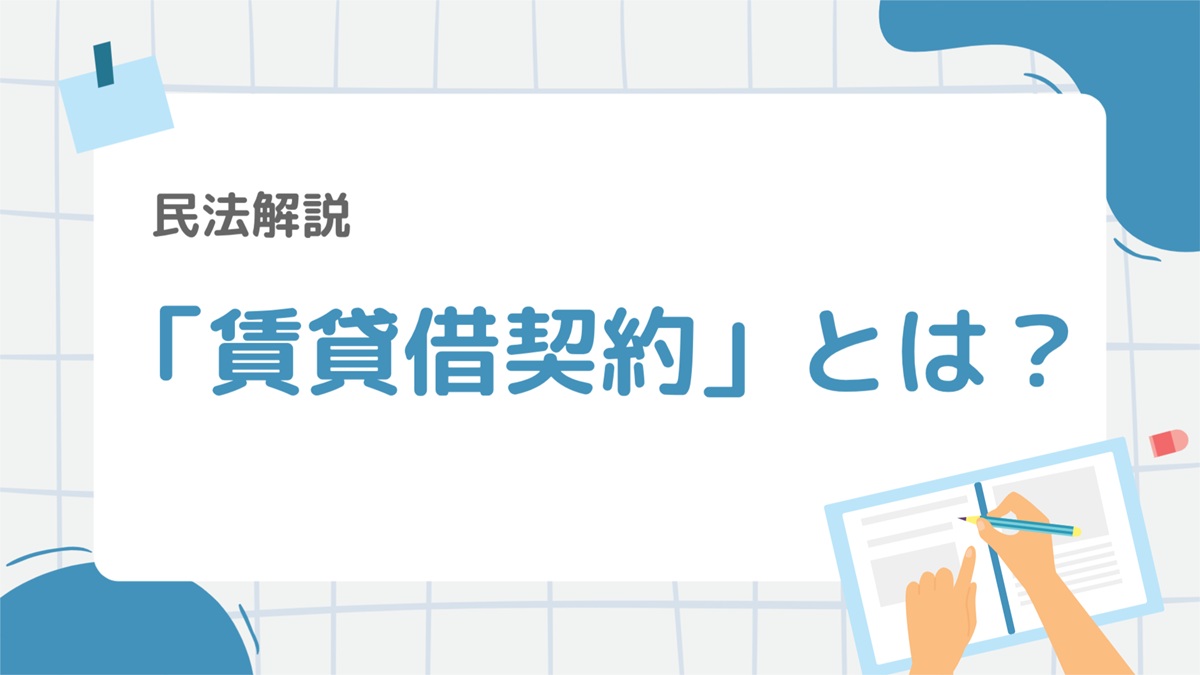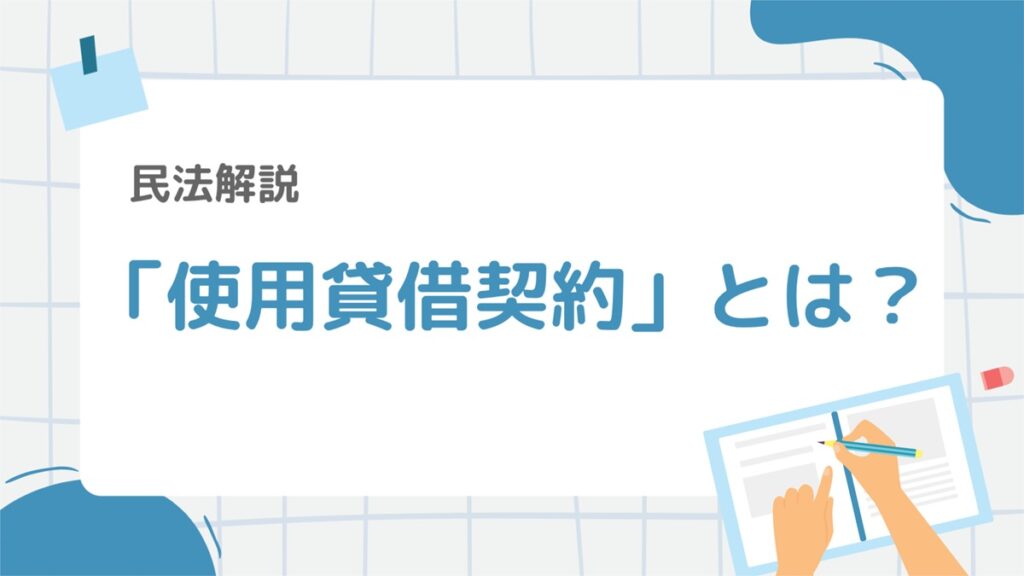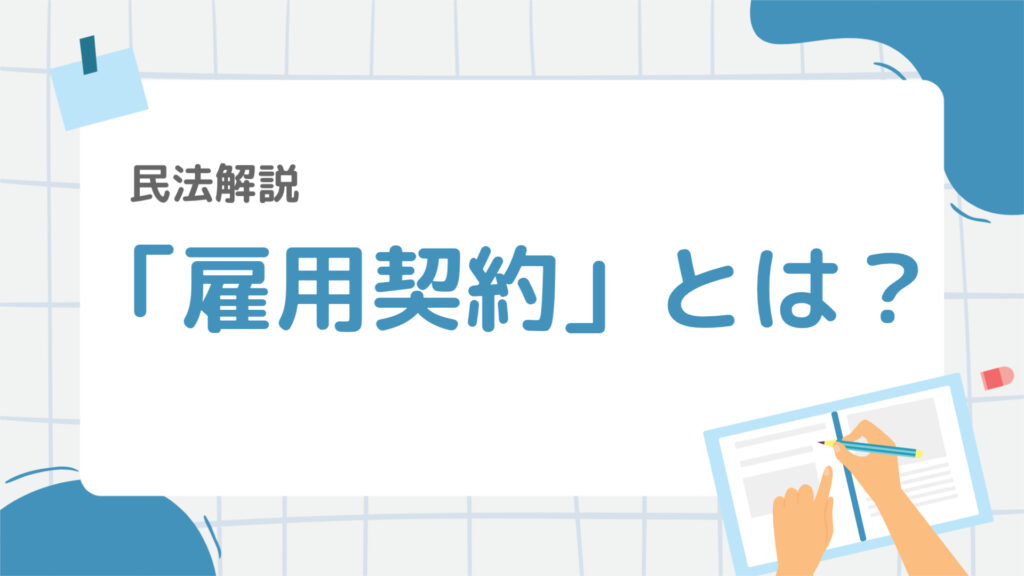- 賃貸借契約の基本をしっかり押さえたい行政書士受験生
- 「敷金」「賃借権の譲渡・転貸」などをイメージで覚えたい方
- 不動産賃貸借の対抗要件や第三者との関係を整理したい方
賃貸借契約とは?【基本のキホン】
--- config: theme: neutral --- sequenceDiagram autonumber actor A_賃貸人 actor B_賃借人 A_賃貸人 ->> B_賃借人:目的物(建物) B_賃借人 ->> B_賃借人:使用・収益 B_賃借人 ->> A_賃貸人:賃料
AはBに対して、「自分の所有する建物を賃料月額10万円で貸したい」といって申し込みをしたところ、Bはこれを承諾した。
賃貸借契約とは、賃貸人が物を貸し、賃借人が賃料を支払うことを約束する契約です(601条)。
賃借人は、物を返す義務も負います。簡単に言えば、「貸してあげるから、お金を払って、使い終わったら返してね」という約束です。
敷金とは?【お金を預ける意味】
敷金とは、賃借人が賃貸人に渡す「保証金」のようなものです(622条の2第1項かっこ書)。
未払いの賃料などに充てるために預けます。名前が違っていても、性質が同じなら敷金とみなされます。1
敷金はいつ返ってくる?
賃貸借が終わり、物を返したときに、未払い分などを差し引いて返還されます(622条の2第1項)。
- 賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けたとき
- 賃貸人が適法に賃借権を譲り渡したとき
敷金返還の相手は誰?
不動産が売却されて賃貸人が変わったときは、新しい賃貸人に敷金返還を請求できます(605条の2第4項)。2
※賃借人が交代した場合は、特別な事情がない限り引き継がれません(最判昭53.12.22)。
賃貸人・賃借人のそれぞれの義務
賃貸人の義務
賃貸人には、以下の義務があります。
さらに、賃貸借契約は有償契約であるため、賃貸人は売主と同様の担保責任を負います(559条)。そのため、土地・建物の賃借人が賃借物に対する権利を有する第三者から明渡しを請求された場合、以後の賃料支払いを拒絶することができます(576条、最判昭50.4.25)。
賃借人の義務
賃貸人に対して賃料を支払う義務(601条)。
賃料とは、目的物の使用・収益に対する対価のことをいいます。7
賃借権の譲渡・転貸【違いと注意点】
賃借権の譲渡・転貸とは?
--- config: theme: neutral --- sequenceDiagram autonumber actor A_賃貸人 actor B_旧賃借人 actor C_新賃借人 A_賃貸人 ->> B_旧賃借人:賃貸借契約 activate B_旧賃借人 B_旧賃借人 ->> C_新賃借人:賃借権の譲渡 deactivate B_旧賃借人 activate C_新賃借人 note over B_旧賃借人:賃貸借関係から離脱 A_賃貸人 --> C_新賃借人:賃貸借契約 deactivate C_新賃借人
AはBに対して、自己の所有する建物を賃貸した。その後、BはCに対してこの建物の賃借権を譲渡した。
--- config: theme: neutral --- sequenceDiagram autonumber actor A_賃貸人 actor B_賃借人_転貸人 actor C_転借人 A_賃貸人 ->> B_賃借人_転貸人:賃貸借契約 B_賃借人_転貸人 ->> C_転借人:転貸借契約
AはBに対して、自己の所有する建物を賃貸した。その後、BはCに対してこの建物を転貸した。
賃借権の譲渡とは、事例2のように、賃借人(B)が第三者(C)に賃借権を譲渡し、自らは賃貸借関係から離脱する場合。
転貸とは、事例3のように、賃借人(B)が目的物を第三者(C)に又貸しし、自らも賃貸借関係を存続させる場合。8
無断譲渡・転貸はNG!承諾がない場合の譲渡・転貸
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借物を譲渡し、または転貸することができません(612条1項)。
承諾の無い譲渡・転貸(無断転貸)が行われた場合、賃貸人・賃借人・転借人の関係は、次のようになります。
- 賃貸人 ⇔ 賃借人 間
賃貸人は、契約の解除をすることができる(612条2項)。9 - 賃貸人 ⇔ 転借人 間
原賃貸借を解除しなくても、賃貸人は転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することができます(最判昭26.5.31)。 - 賃借人 ⇔ 転借人 間
賃借人が転借人に対して相当の担保を提供していない限り、転借人は賃借人に対して転貸借の賃料の支払いを拒絶することができます(559条、576条、最判昭50.4.25)。
--- config: theme: neutral --- flowchart LR 賃貸人 転借人 賃借人 賃貸人 --契約の解除可能--> 賃借人 賃貸人 --明渡しを請求可能--> 転借人 転借人 --担保を提供していない場合、賃料支払を拒絶可能--> 賃借人
承諾がある場合の賃借権の譲渡・転貸
賃貸人(貸主)の承諾を得て賃借権が譲渡されると、もとの賃借人(旧賃借人)は賃貸借契約から離れることになります。10
一方、賃借人が賃貸人の承諾を得て目的物を転貸(また貸し)した場合、転借人(また貸しを受けた人)は、賃借人が負っていた債務の範囲内で、直接賃貸人に対して義務を負うことになります(613条1項前段)。
また、転借人は賃貸人に対して、賃料の前払いしたことを理由に支払い義務を免れることはできません(613条1項後段)。1112
賃貸借契約が解除された場合の転貸借への影響
- 合意解除の場合
賃貸借が合意解除された場合でも、その解除を転借人に対抗することはできません(613条3項本文)。 - 債務不履行による解除の場合
賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了します(613条3項但書、最判平9.2.25)。13
賃借権と第三者との関係【登記がカギ】
不動産賃借権の対抗力
--- config: theme: neutral --- sequenceDiagram autonumber actor A_賃貸人 actor B_賃借人 actor C_新所有者 A_賃貸人 ->> B_賃借人:賃貸 A_賃貸人 ->> C_新所有者:売却
AはBに対して、自己の所有する建物を賃貸したが、引渡しはまだされていない。その後、AはCに対してこの建物を売却した。
Bは、賃借権という債権をもっていますが、債権は債務者(A)という特定の人に対してしか主張できず、Cに対して賃借権を主張することはできません。そのため、建物の新所有者であるCは、Bに対して物権的請求権を行使し、建物から退去するよう請求することができます。
しかし、生活の基盤となる建物の賃貸借において、目的物の譲渡により賃貸借関係が覆されてしまうと、賃借人(B)は大きな影響を受けてしまいます。そこで、不動産の賃貸借は、これを登記した場合には、その不動産を取得した者祖恩多の第三者に対抗することができます(605条)。
つまり、Bは建物の賃貸借について登記を行えば、Cに対しても賃借権を主張でき、退去する必要がなくなります!1415
賃貸の地位の移転
法令の規定による対抗要件を備えた場合、その不動産が譲渡されると、その不動産の賃貸人たる地位は譲受人に移転します(605条の2第1項)。
また、賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転を登記しなければ、賃借人に対抗することができません(605条の2第3項)。
なお、賃貸人たる地位が譲受人に移転したときは、費用の償還に係る債務および敷金の返還に係る債務は、譲受人が承継する(605条の2第4項)。
賃借権の二重設定
賃借権が二重に設定された場合の優劣は、対抗要件の先後によって決まります(最判昭28.12.18)。
不法占拠者との関係
所有者たる賃貸人は、不法占拠者に対して、所有権に基づく妨害排除請求権を行使することができます。そのため、賃借人は、この妨害排除請求権を代位行使(423条)することができます(大判昭4.12.16)。
また、賃借人は、賃借権について対抗要件を備えている場合、直接賃借権に基づく返還請求を行うことも可能です(605条の4第2号)。
--- config: theme: neutral --- flowchart LR 賃貸人 賃借人 不法占拠者 賃貸人 --妨害排除請求権--> 不法占拠者 賃貸人 --> 賃借人 賃借人 --妨害排除請求権を代位行使--> 不法占拠者 賃借人 --賃借権に基づく返還請求--> 不法占拠者
賃貸借と使用貸借の違い
| 賃貸借 | 使用貸借 | |
| 契約の性質 | ①諾成契約(引渡無くても成立) ②有償契約 | ①諾成契約(引渡無くても成立) ②無償契約 |
| 対抗力 | あり(605条) | なし |
| 費用償還請求権 | ①必要費:直ちに償還請求可(608条1項) ②有益費:賃貸借終了時に償還請求可(608条2項) | ①通常の必要費:償還請求不可(595条1項) ②非情の必要費・有益費:目的物の返還時に償還請求可(595条2項) |
| 借主の死亡 | 契約継続 | 契約終了(597条3項) |
まとめ
賃貸借契約は、「貸す側」「借りる側」の義務をしっかり押さえること、敷金や登記の重要性を理解することがカギです!
行政書士試験でも頻出ポイントなので、図やイメージを使いながら覚えましょう!
- 参考:賃貸人は、賃借人が賃料債務などを履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができるが、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することはできない(622条の2第2項) ↩︎
- 重要判例:家屋の賃貸借終了後、明渡前にその所有権が他に移転された場合、敷金に関する権利義務関係は、旧所有者と新所有者との合意のみによっては、新所有者に承継されない(最判昭48.2.2) ↩︎
- 具体例:屋根からの雨漏りの修繕費や、トイレが故障した場合の修理費など ↩︎
- 参考:建物の賃借人が有益費を支出した後に建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、新賃貸人が有益費の償還義務を承継し、旧賃貸人は当該償還義務を免れる(605条の2第4項) ↩︎
- 具体例:借家の駐車場を舗装した場合の費用など ↩︎
- 重要判例:賃借人が賃借建物に付加した増改築部分が賃貸借終了前に滅失した場合、特段の事情のない限り、賃貸人の有益費償還義務は消滅する(最判昭48.7.17) ↩︎
- 参考:賃料は、動産、建物および宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない(614条本文)。 ↩︎
- 重要判例:賃貸人の承諾がある転貸において、賃貸人が当該建物を転借人に譲渡し、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰属したときであっても、賃借人と転借人間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り、転貸借関係は当然には消滅しない(最判昭35.6.23) ↩︎
- 重要判例:賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用・収益をさせた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、賃貸人は、契約を解除することはできない(最判昭28.9.25) ↩︎
- 重要判例:賃貸人がいったん賃借権の譲渡・転貸を承諾した場合、賃借人が第三者との間で賃借権の譲渡・転貸をする前であっても、賃貸人は、これを撤回することができない(最判昭30.5.13) ↩︎
- 重要判例:「賃料の前払い」とは、転貸借契約で定められた弁済期前に賃料を支払うことである(大判昭7.10.8) ↩︎
- 参考:賃貸人が賃借人に対して。その権利を行使することは妨げられない(613条2項)。 ↩︎
- 重要判例:適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない(最判昭37.3.29) ↩︎
- 重要判例:賃借権は債権であるから、賃借人は賃貸人に対してその登記を請求することはできない(大判大10.7.11)。 ↩︎
- 重要判例:借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができるが(借地借家法10条1項)、借地上の建物の登記が家族名義の場合には、これをもって第三者に対抗することができない(最大判昭41.4.27) ↩︎