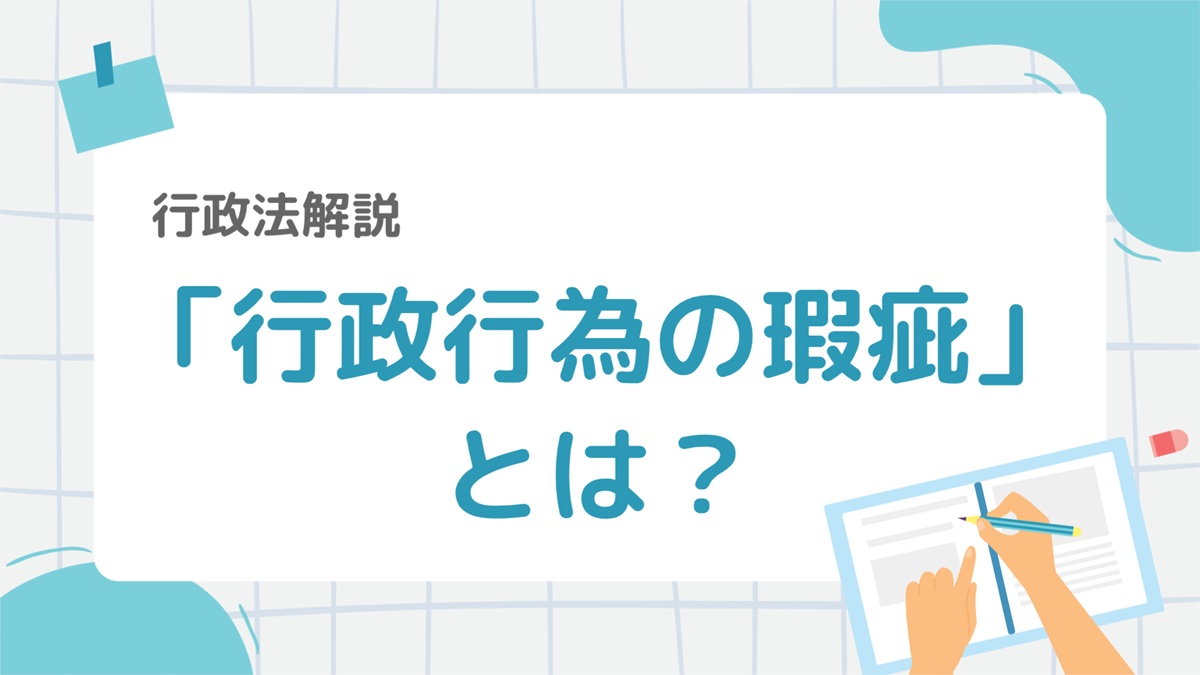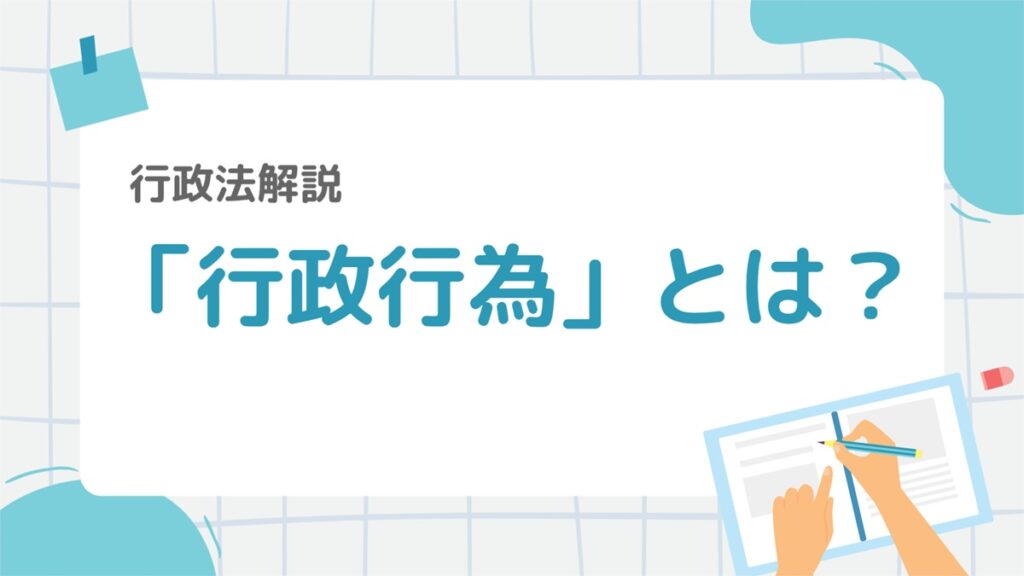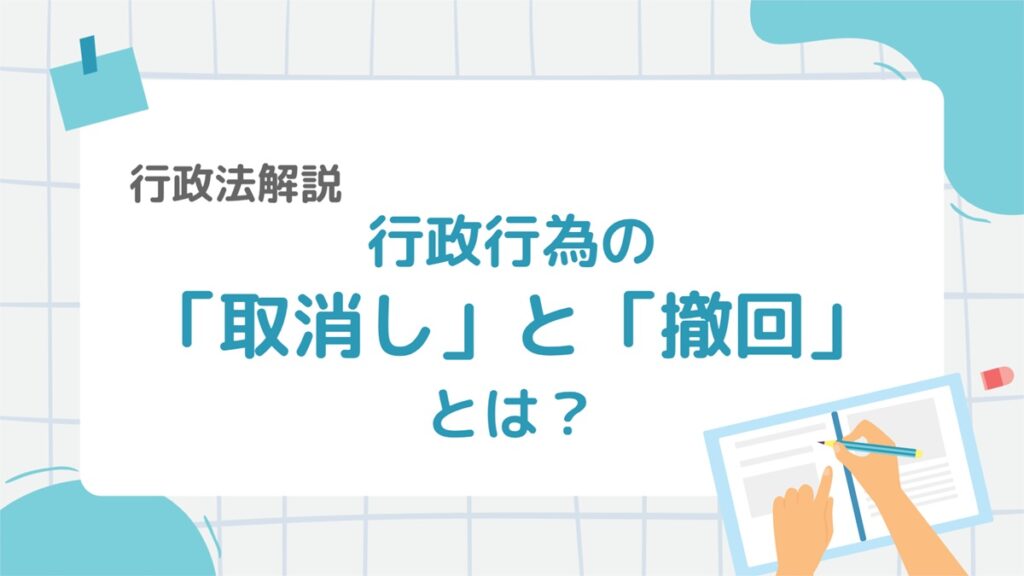- 「行政行為の瑕疵」って何を意味するのかがよくわからない
- 無効な行政行為と取り消し可能な行政行為の違いを知りたい
- 「違法性の承継」や「瑕疵の治癒」など似たような用語が混乱する
- 行政書士試験で問われやすいポイントを効率的に押さえたい
行政行為の瑕疵とは?
「行政行為の瑕疵(かし)」とは、行政行為に法律違反(違法)や不当な点があることを指します。
大きく分けて以下の2種類があります。
- 違法な行政行為:法律に違反しているもの
- 不当な行政行為:法律には違反しないが、公益に反して不適切なもの
行政行為に瑕疵があっても、すべてが無効になるわけではなく、取り消されるまでは有効としても差し支えのない程度ものものあります。
その瑕疵の内容によって、以下の2通りに分かれます。
(1)当然に無効となる行政行為
行政行為の瑕疵が重大かつ明白であるときに限り、その行政行為は当然に無効であると判断されています(最大判昭31.7.18)▶判例(最判昭36.3.7) ▶判例(最判昭48.4.26)
✅無効な行政行為には「公定力」や「不可争力」がないため、
・相手方は従う必要がない
・いつまでも争うことができる
(2)取り消されるまで有効とされる行政行為
瑕疵があっても、それが重大で明白でない場合は、原則として有効なままとされます。
取り消されない限り効力を持ち続けます。
---
config:
theme: neutral
---
flowchart LR
行政行為-->瑕疵あり("瑕疵あり<br>(違法・不当)")
瑕疵あり-->重大かつ明白な瑕疵(重大かつ明白な瑕疵<br>⇒当然に無効)
瑕疵あり-->重大かつ明白とはいえない瑕疵(重大かつ明白とはいえない瑕疵<br>⇒取り消されるまで有効)
行政行為-->瑕疵なし("瑕疵なし<br>(適法・妥当)")
違法性の承継
「違法性の承継」とは、前の行政行為(先行行為)に違法があった場合に、
それを前提に行われた次の行政行為(後行行為)にも違法性が引き継がれるという考え方です。
【原則】違法性の承継は認められない
行政行為はできるだけ早く法的に確定させ、安定させることが重要とされています。
そのため、原則として
「先行行為の違法性は後行行為に影響しない」=個別に判断する
という考えがとられています。
【例外】一連の手続きとみなされる場合
ただし、
- 先行行為と後行行為が連続した一体の手続きで
- 特定の法律効果の発生を目的としている場合は
例外的に違法性の承継が認められることがあります。▶判例
🔍最重要判例:最判平21.12.17(安全認定と違法性の承継)
瑕疵の治癒・違法行為の転換とは?
瑕疵の治癒とは?
最初は違法や不備があった行政行為でも、あとから事情が変わったことで、事後的にその瑕疵がなくなった(解消)とみなされることがあります。これを「瑕疵の治癒」といいます。▶判例
違法行為の転換とは?
一見違法な行政行為でも、別の行政行為として内容を見すことで適法な行政行為として読み替えることができる場合、そのまま適法な行政行為として維持することが可能です。
これが「違法行為の転換」です。
まとめ|行政行為の瑕疵は「無効か有効か」で大きく異なる!
行政行為に瑕疵があるかどうかは、
その後の効力や争い方に大きく影響します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 無効な行政行為 | 重大かつ明白な違法がある。従う必要なし。いつでも争える。 |
| 取り消し可能な行政行為 | 瑕疵があっても取り消されるまでは有効。 |
| 違法性の承継 | 原則なし。例外的に一体的な手続きなら認められる。 |
| 瑕疵の治癒 | 事情の変化などで違法性が後から解消されること。 |
| 違法行為の転換 | 違法な行政行為を別の適法な行政行為として読み替えること。 |