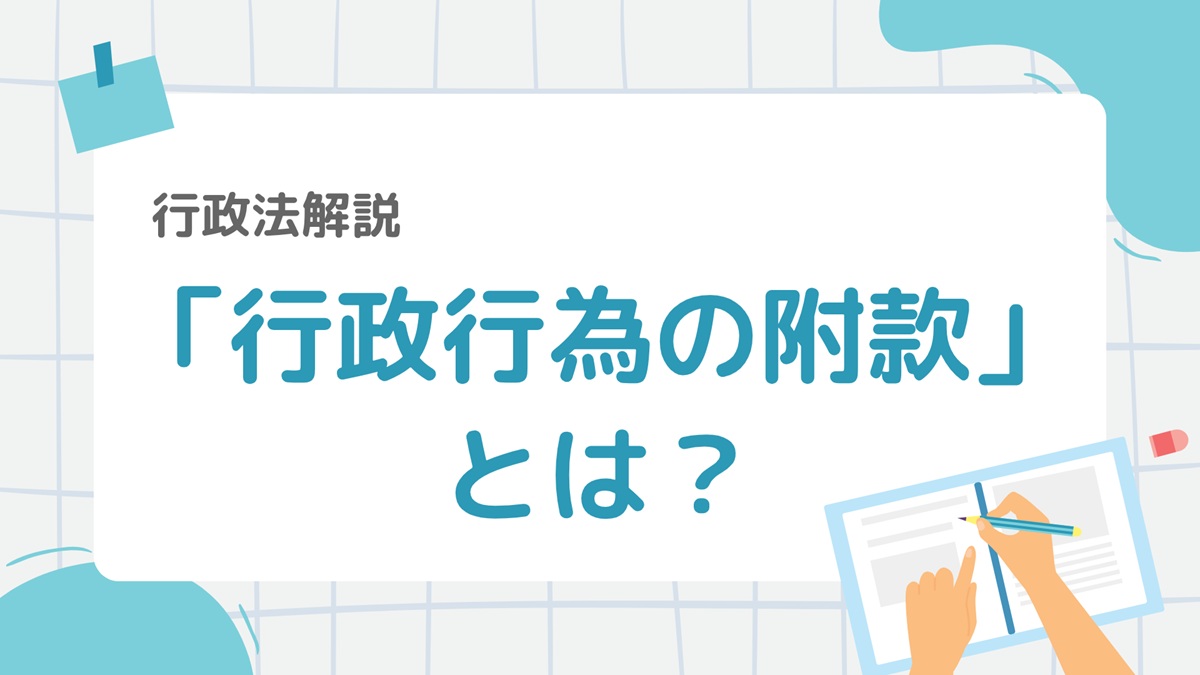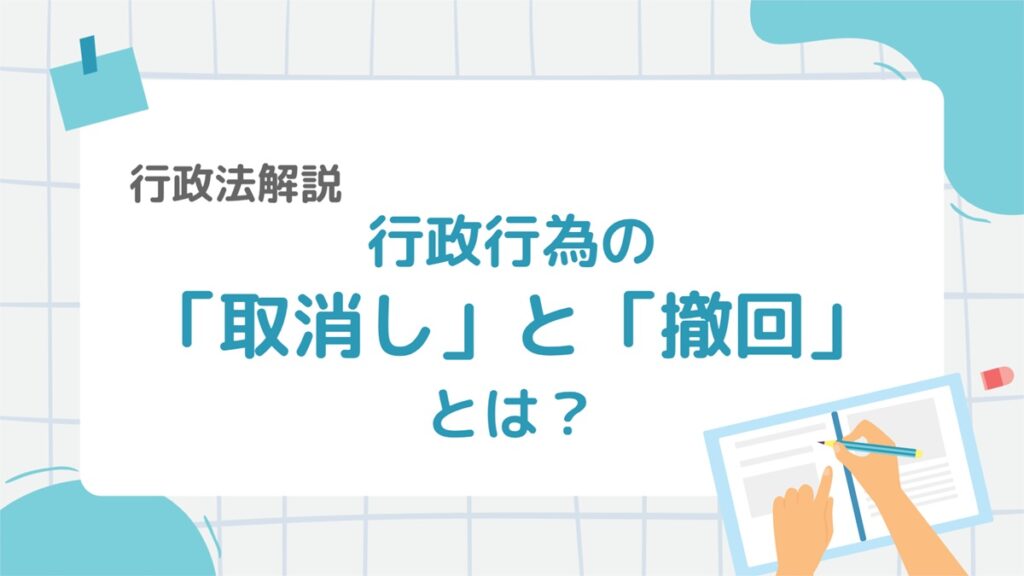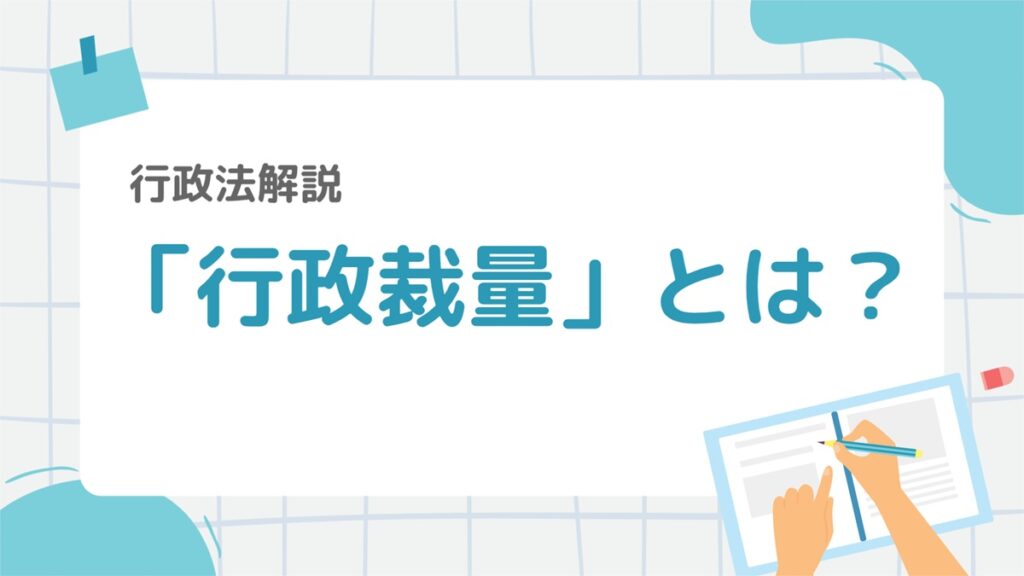この記事はこんな人におすすめ
- 行政書士試験の行政法で「附款」が何かイマイチ理解できない
- 「条件」「期限」「負担」などの違いを具体例で覚えたい
- 附款の限界や瑕疵について、判例や制度の趣旨も踏まえて押さえたい
そんな方に向けて、「行政行為の附款」について、覚えやすく丁寧に解説していきます!
目次
行政行為の附款とは?
「行政行為の附款」とは、行政行為に制限や条件を加える副次的な(従たる)意思表示のことを指します。
つまり、行政庁がある行政行為を行う際に、その効果を限定したり義務を課したりすることで、その内容をコントロールする仕組みです。1
附款の5つの種類【具体例付き】
行政行為の附款には、以下の5つのタイプ(条件・期限・負担・撤回権の留保・法律効果の一部除外)があります。例とともに整理しましょう。
| 意味 | 具体例 | |
| 条件2 | 行政行為の効果を発生するかどうかが不確実な将来の事実にかからせるもの | 道路工事が終了するまで通行止めとすること |
| 期限 | 行政行為の効果を発生することが確実な将来の事実にかからせるもの | 運転免許の「〇年〇月〇日まで有効」などの有効期限 |
| 負担 | 許可・認可などの受益的行政行為につけられるもので、相手方に特別の義務を命ずるもの3 | 道路の占有許可に付された占有料の納付、運転免許に付された眼鏡使用の義務付け |
| 撤回権の留保 | 行政行為をするにあたって、将来撤回することがある旨をあらかじめ確認しておくもの | 飲食店の営業許可にあたって「食中毒を起こした場合は営業許可を撤回する」旨を確認すること |
| 法律効果の一部除外 | 法律が認める効果の一部を行政庁の意思で排除するもの | 公務員に出張を命じつつ、旅費を支給しないとすること |
附款を付すことができる行政行為・できない行政行為
附款を付けられる場合
附款は、許可・認可などの法律行為的行政行為に対して付けることができます。法律が明示的に認めている場合以外でも可能で、これは、行政庁にある程度の裁量(裁量権)があるからです。
附款を付けられない場合
一方、確認・公証などの準法律行為的行政行為には、附款を付けることはできません。
これらは形式的・客観的な判断に基づくため、行政庁の裁量が入り込む余地がないからです。
附款を付けるときのルール(限界)
ただし、附款の付加には以下の原則に基づく制限があります。
- 目的拘束の原理
行政行為の本体の目的と関係のない目的で附款を付すことは許されません。 - 比例原則
附款によって、法の目的に照らして過大な義務を課すことは認められません。 - 平等原則
行政行為の相手方を不平等に扱うような附款は許されません。
附款の瑕疵(かし)とその影響
附款に違法や不当な点(瑕疵)がある場合、それが行政行為本体と「分けられるかどうか」によって、扱いが異なります。
✅附款が「可分」の場合
附款のみに不服がある者は、行政行為の一部の取消しを求める訴訟を提起して附款のみの取消しを求めることができます。この場合、附款が裁判で取り消されれば、附款の無い行政行為のみが有効に残ることになります。
✅附款が「不可分」の場合
附款と行政行為本体と不可分一体であれば、附款の取消しは行政行為全体の取消しとなります。そのため、附款のみの取消しを求めることは許されず、本体たる行政行為の取消訴訟を提起しなければならない。
まとめ
- 附款とは、行政行為に付けられる従たる条件や制限のこと
- 種類は「条件」「期限」「負担」「撤回権の留保」「法律効果の一部除外」の5つ
- 許可・認可などには付けられるが、確認・公証には付けられない
- 附款には目的・比例・平等の原則が適用される
- 附款に瑕疵がある場合、「可分か不可分か」により扱いが異なる