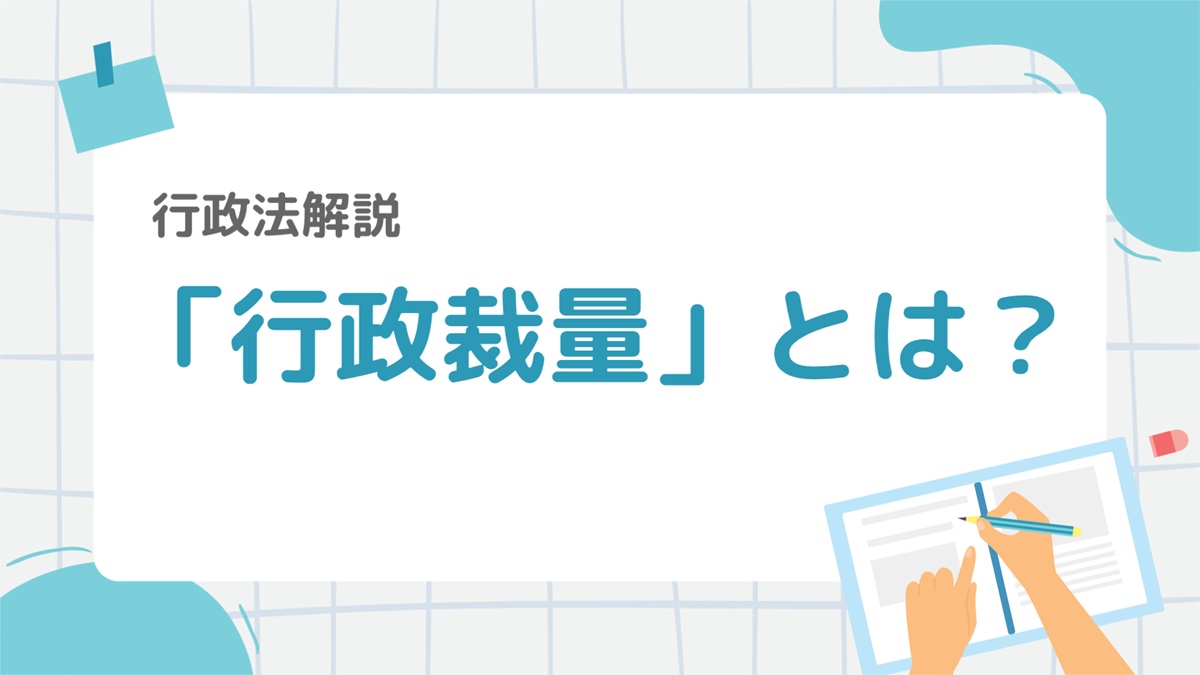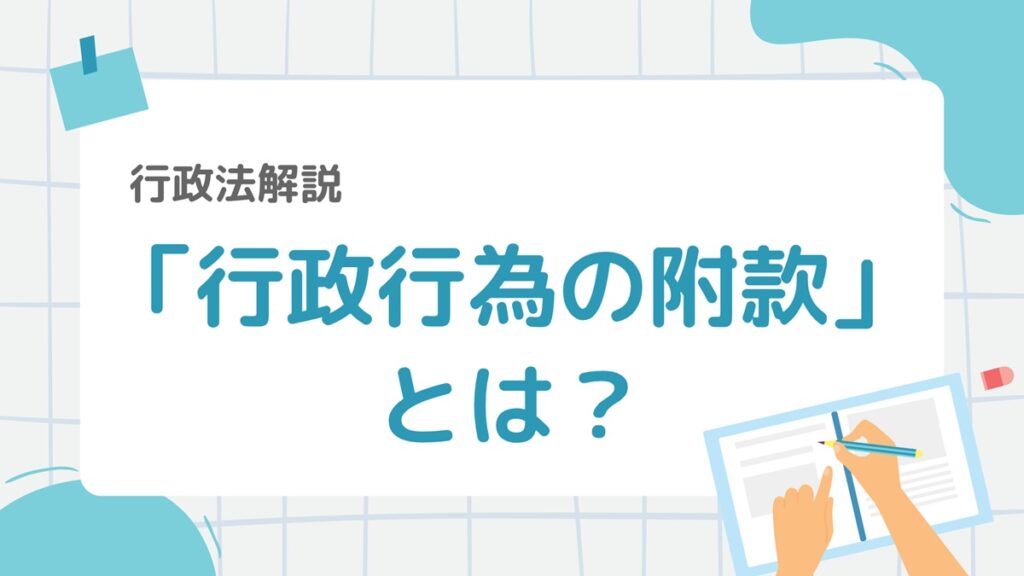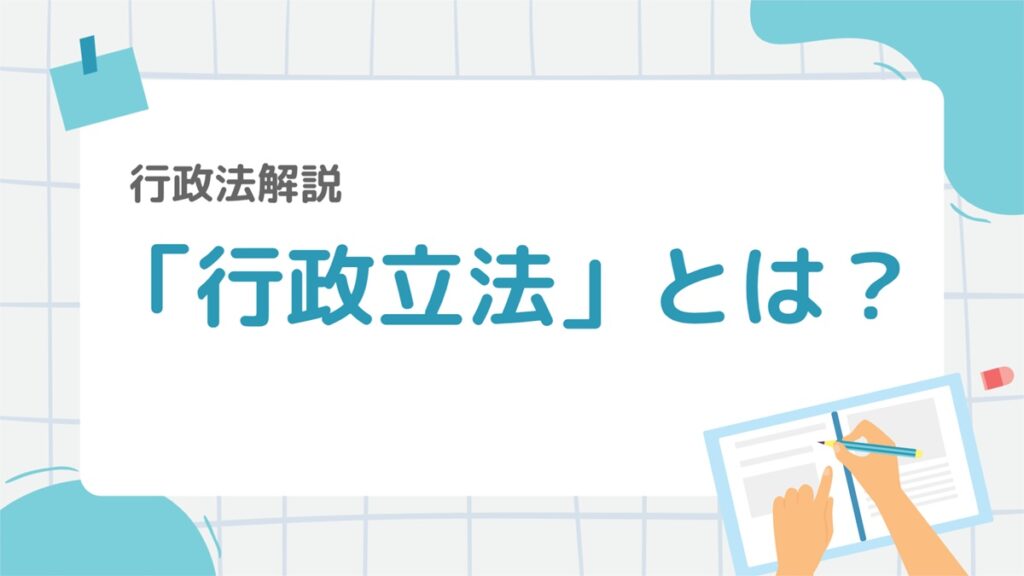- 行政書士試験で「行政裁量」が出てきて困っている人
- 「要件裁量」と「効果裁量」の違いが分からない人
- 裁量があるといっても、どこまで許されるのか知りたい人
- 判例や行政事件訴訟法との関係を理解したい人
行政裁量とは?
行政にも“自由な判断”が認められる場面がある
本来、行政が国民に対して何か行う場合には、法律にしっかりと根拠がある必要があります。これを「法律による行政の原理法律の留保の原則」や「法律の留保の原則」といいます。
つまり、「法律でちゃんと決めておいてね!」というルールがあるということです。
ですが、現実にはすべてを細かく法律に書いておくのは難しいんです。たとえば、急に予想外のトラブルが起きたとき、いちいち国会で法律を作っていたら、対応が遅れてしまいますよね。
そこで、行政機関がその場の事情に応じて、ある程度自由に判断できる場面が必要になります。この“行政が自由に判断できる余地”のことを「行政裁量(ぎょうせいさいりょう)」といいます。
行政裁量の種類:「要件裁量」と「効果裁量」
行政裁量には、以下の2つの種類があります。
✅ 要件裁量とは?
例:国家公務員法82条1項3号
「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」には、「懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる」
と規定していまうが、の「非行のあった場合」という部分があいまいですよね。どういう行為が「非行」にあたるかを判断するのは行政機関。これが要件裁量です。▶判例
✅ 効果裁量とは?
次に、「じゃあ実際にどんな処分にするのか?」という部分も、行政が選ぶことができます。
たとえば、処分の種類には「免職」「停職」「減給」「戒告」などがありますが、この中からどれを選ぶかは行政の判断に任されています。これが効果裁量です。
| 認められる | 認められない | |
| 要件裁量 | ①法務大臣による在留期間の更新事由の有無の判断(最大判昭53.10.4) ②高等学校用の教科用図書の検定における合否の判定等の判断(最判平5.3.16、最判平9.8.29) | 農地委員会による農地に関する賃借権の設定・承諾の有無の判断(最判昭31.4.13) |
| 効果裁量 | 国家公務員法に基づく懲戒処分の決定(最判昭52.12.20) | 土地収用法による保証金の額の決定(最判平9.1.28) |
🔍重要判例:最判昭52.12.20(神戸税関事件)
🔍重要判例:最判平10.4.10(再入国不許可処分と要件裁量)
裁量だからって、何でもアリじゃない!司法審査が入ることも
行政裁量はある程度自由な判断が認められていますが、やりすぎてしまった場合や、法律の趣旨を無視しているような場合には、権力分立の観点からも裁判所がその行政処分を取り消すことができます。(行政事件訴訟法30条)。
これを「裁量権の逸脱・濫用(らんよう)」といい、行政事件訴訟法30条で定められています。
では、どんなときに「逸脱・濫用」と判断されるのでしょうか?いくつかの基準があります。1
裁量の逸脱・濫用をチェックするポイント
- 重大な事実誤認
行政作用は正しい事実認定を前提として行われるべきであり、重大な事実誤認があれば、その行政作用は違法となる
👉そもそも事実関係の認定が間違っていたらNG! - 目的違反
法律の趣旨・目的と異なる目的に基づいて行政作用がなされた場合、その行政作用は違法となる
👉法律の目的とは違う目的で処分していたらNG! - 信義則違反
信義誠実の原則(信義則)に反する行政作用は違法となる
👉相手の信頼を裏切るような行為はNG! - 比例原則違反
比例原則に反する行政作用は違法となる2
👉軽い違反に対して重すぎる処分をするのはNG! - 平等原則違反
平等原則に反する行政作用は違法となる
👉一方だけ厳しく処分するのはNG!
裁量の「判断過程」もチェックされる
「判断過程審査」という考え方も重視されています。つまり「どんな手順で判断に至ったのか?」というプロセスも見られるようになっているんです。
ここでは以下のようなチェックポイントがあります。
- 他事考慮(たじこうりょ)
行政作用をなすにあたり、考慮すべきでない事項を考慮した場合、その行政作用は違法となる
👉 関係ない事情を持ち出して判断していたらNG! - 要考慮事項の考慮不尽
行政作用をなすにあたり、考慮すべき事項を考慮しなかった場合、その行政作用は違法となる
👉 本来考えないといけないことを無視していたらNG!
🔍重要判例:最判平4.10.29(伊方原発訴訟)
🔍重要判例:最判平8.3.8(剣道実技拒否事件)
🔍重要判例:最判平18.11.2(小田急高架訴訟本案判決)
まとめ
行政裁量は、行政がその場に応じて判断できる“自由な部分”のこと。でも、それはあくまで「法律の目的に沿って」「適切に判断する」ことが前提です。
裁量があるからといって好き勝手できるわけではありません。行き過ぎた行政処分には、裁判所がストップをかけることもあります。
行政書士試験では、「行政裁量がどこまで認められるか」や「裁量権の逸脱・濫用」のチェック基準がよく問われます。しっかり押さえておきましょう!