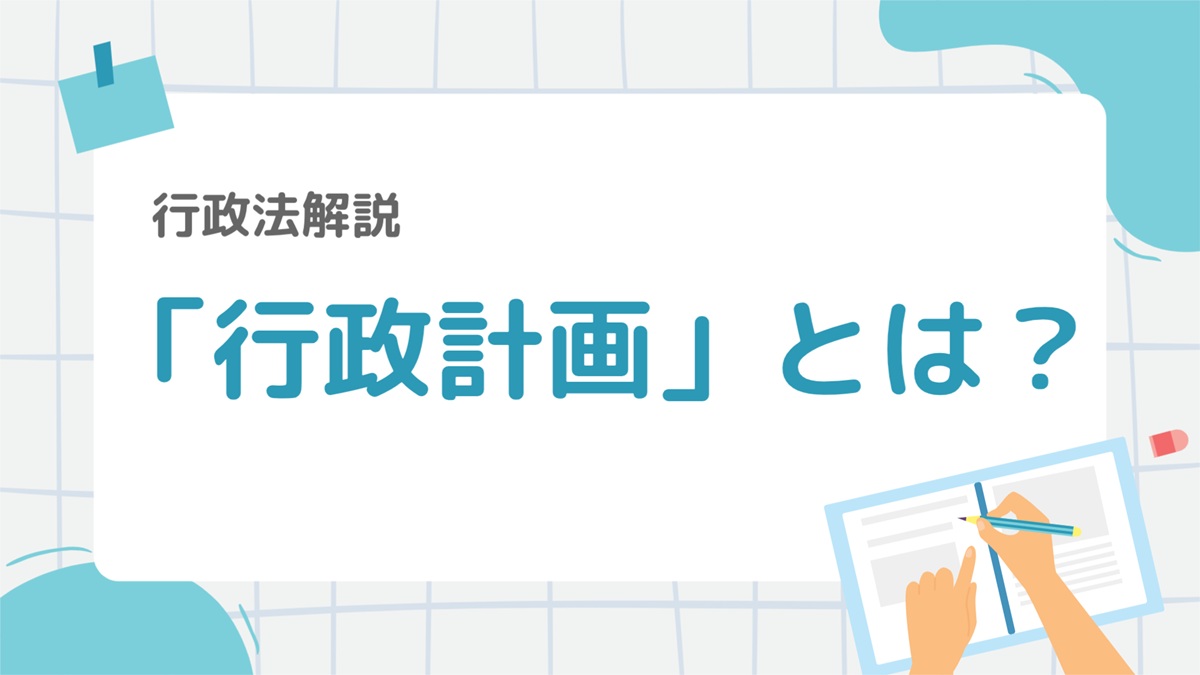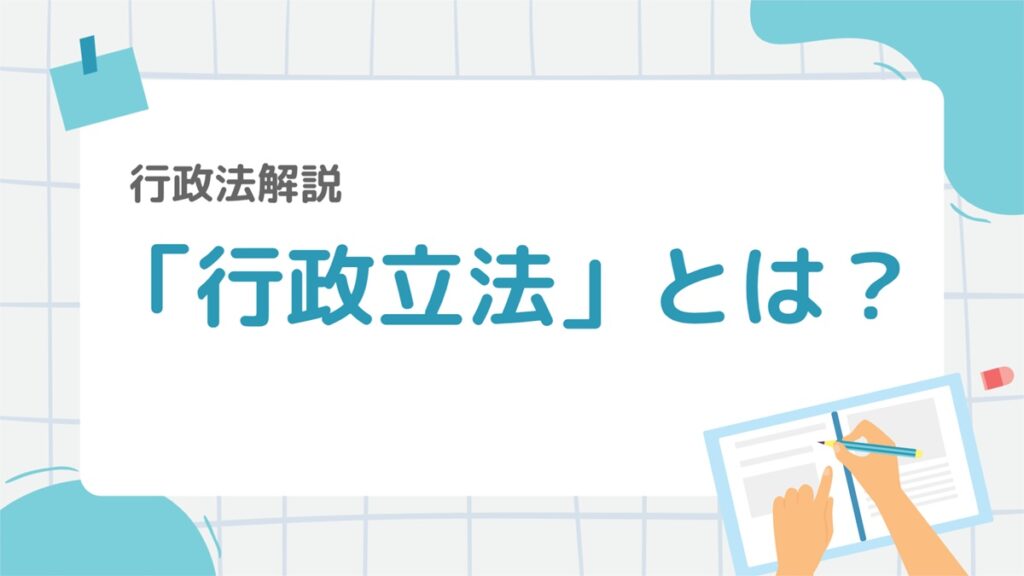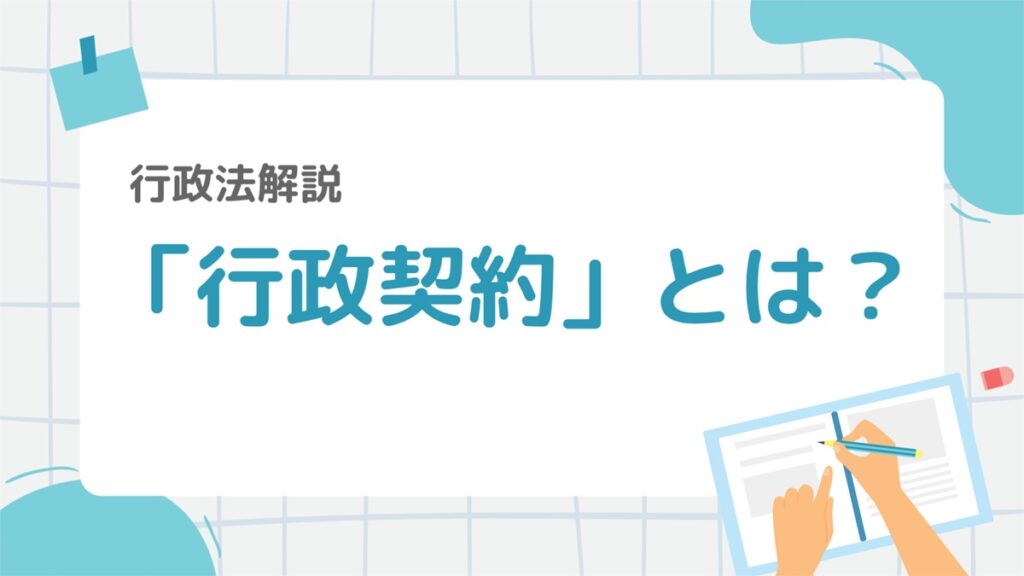- 行政書士試験の行政法分野を学習中の方
- 「行政計画」の意味や法的性質についてよく分からないと感じている方
- 都市計画や交通政策など、行政計画が法的にどう扱われるかを知りたい方
- 行政計画に対して訴訟ができるかどうかを具体的に理解したい方
📝 行政計画とは?【まずは定義を押さえよう】

行政計画とは、”国や地方公共団体などの行政機関が将来的な目標を達成するために作成する「行動方針」“のことです。
たとえば──
- 地域の道路や鉄道を整備する「交通インフラ整備5か年計画」
- 少子高齢化に対応する「高齢者福祉推進計画」
といった、将来を見据えて行政がどんな政策を進めるかを示す“設計図”です。
言い換えるなら、行政計画は「行政の未来に向けた行動指針」といえるでしょう。1
行政計画に対する規制
📜 行政計画には法律の根拠が必要?
行政計画はあくまで「プラン」であり、必ずしも法律の根拠が必要なわけではありません。自由に策定できるようにも思えます。
しかし、その計画が国民の権利や義務に影響を与える場合、つまり何らかの制限を加える効果があるときは、法律による根拠が求められるとされています。
たとえば、都市計画などで建築の制限がかかるような場合には、法律に基づく行政計画でなければならないというわけです。
⚙ 行政計画の策定手続きには決まりがある?
実は、行政手続法には「行政計画をどう作るか」という手続きに関する一般的なルールは定められていません。
つまり、行政計画の作成方法は統一されておらず、個別の法律(都市計画法など)で具体的な手続きが定められていることがあるという状態です。
したがって、行政計画の策定にあたっては、それぞれの分野ごとの法律を確認する必要があります。
例:
環境基本計画 ⇒ 環境基本法
都市計画 ⇒ 都市計画法
行政計画に対する救済
行政計画に不服があるときは訴訟を起こせる?
行政計画そのものに対して「取消訴訟」2を起こせるかどうかは、行政庁の行為に処分性(行政事件訴訟法3条2項)があるかどうかで判断されます。
従来は、行政計画はまだ“行政処分”に至る前の段階の行為なので、「処分性がない=取消訴訟はできない」とされてきました。
ですが、最近の最高裁判所の判例では、実質的に個人の権利を制限するような具体的な計画については、処分性を認めて訴訟を起こすことができるとする傾向が強まっています。
行政計画が変更されたときの責任「計画担保責任」とは?
行政計画は長期的な目標を含むことが多く、民間事業者などがその計画を信頼して投資や事業活動を行うケースもあります。
ところが、行政が途中で計画を変更・中止した場合、そうした事業者が損害を被ることもあり得ます。
このような事態を避けるため、行政には、計画を安易に変更しないようにする「計画担保責任」が求められます。計画を変更・中止する際には、
- 必要に応じて代償措置を講じる
- 元の計画をできる限り尊重する
といった対応が期待されています。
✅ まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 行政計画とは | 行政の将来目標を実現するための行動方針 |
| 法律の根拠 | 原則不要。ただし国民の権利義務に影響する場合は必要 |
| 手続きのルール | 行政手続法には一般規定なし。個別法で定められる |
| 訴訟の可否 | 処分性があれば取消訴訟が可能 |
| 計画担保責任 | 行政が安易に計画変更しないようにする責任 |
行政計画は、行政が将来の目標に向けて作る「行動計画」です。一見すると法的拘束力のないプランのようですが、内容や影響によっては法律の根拠が必要になったり、訴訟の対象になったりする重要な制度です。
行政書士試験でも、計画の法的性質や、処分性・担保責任といった周辺知識が問われることがあるので、しっかり理解しておきましょう!