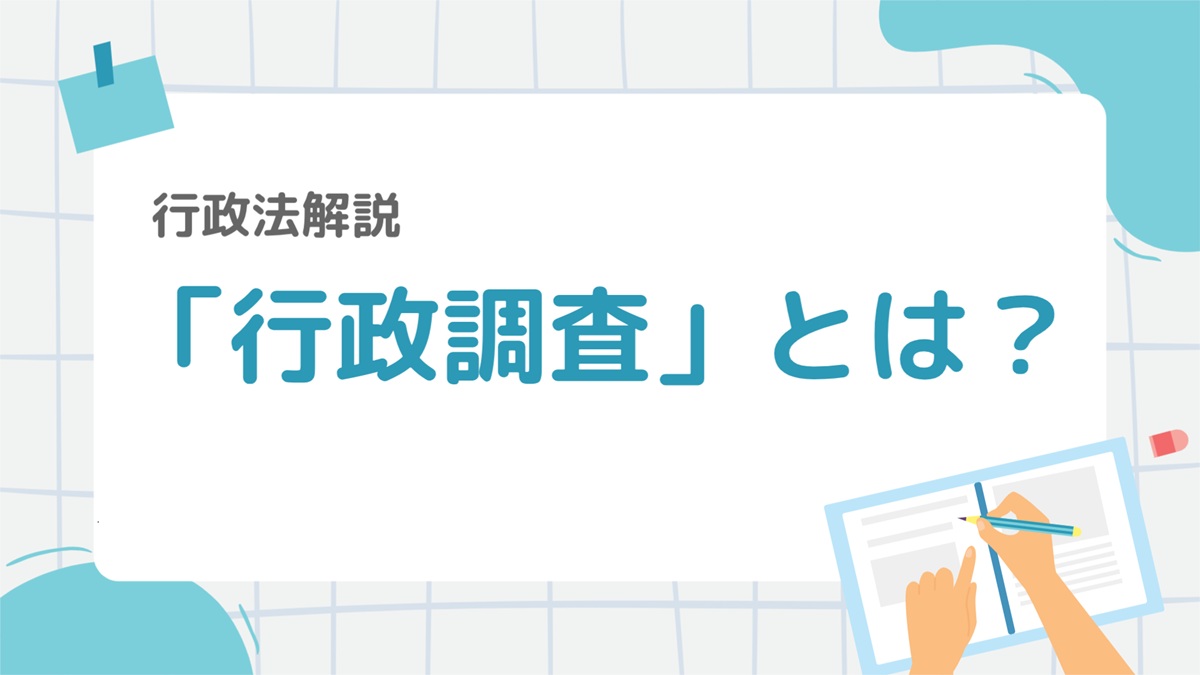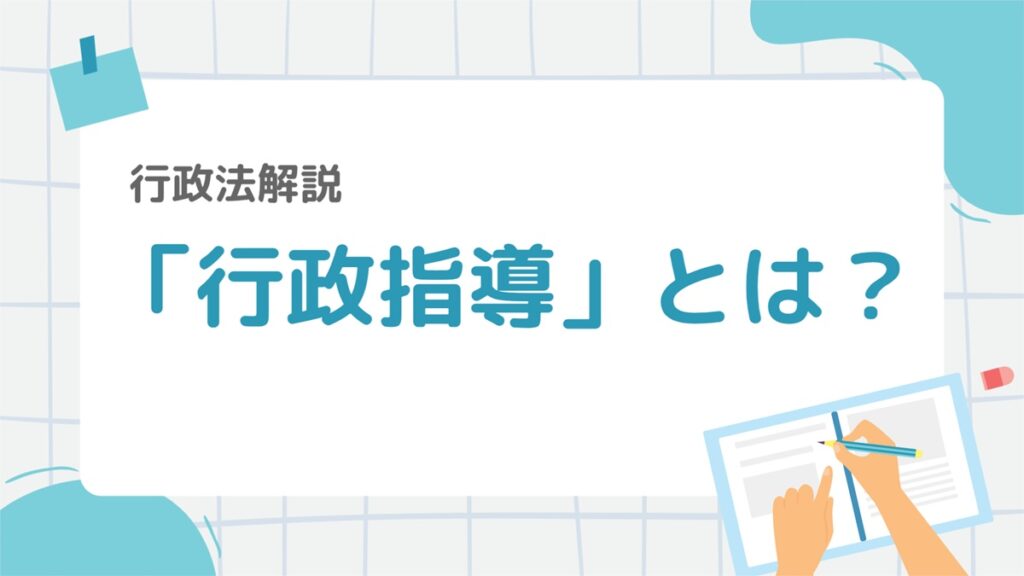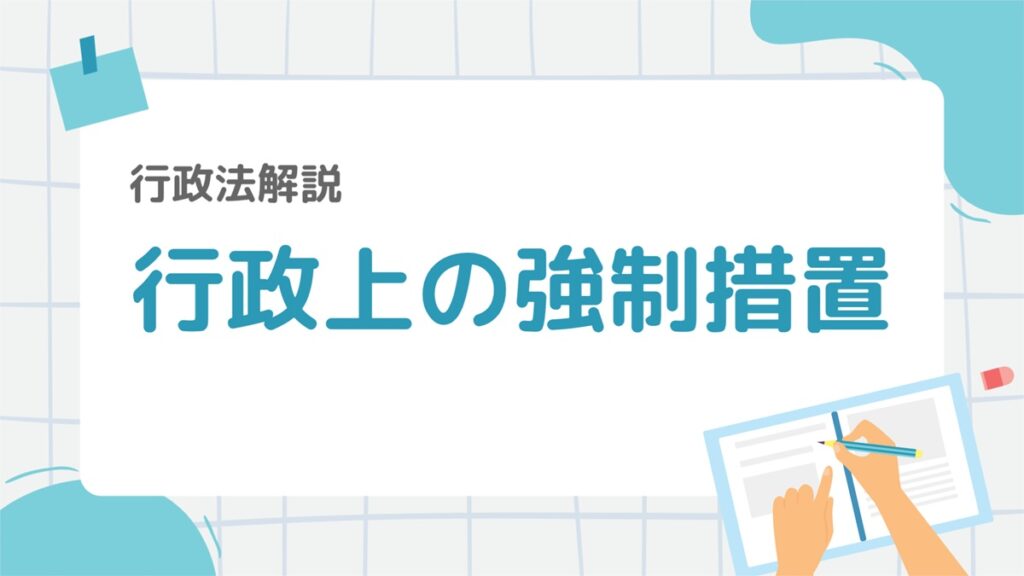行政調査とは?
行政調査とは、行政機関がその目的(法律の施行、適正な行政運営など)を達成するために、必要な情報を集める活動のことです。
たとえば、食品の衛生状態を確認したり、税務調査をしたりといった活動がこれにあたります。
行政調査は、行政作用の前提となる情報収集行為であり、その性質上、正確で客観的なデータを集めることが求められます。
行政調査の3つの分類
行政調査は、相手方への強制の度合いによって、次の3つに分けられます。
| 意味 | 具体例 | 法的根拠の有無 | |
| 任意調査 | 相手方の承諾を受けて行う調査 | 職務質問(警察官職務執行法)など ▶判例① ▶判例② | 不要 |
| 間接強制調査 | 刑罰等の制裁によって間接的な強制力を伴う調査 | 保健所職員による立入検査(食品衛生法)など | 必要 |
| 直接強制調査 (犯則調査) | 直接的・物理的な行政力を行使して行う調査 | 捜索・差押え(国税犯則取締法)など | 必要 +令状が必要な場合もあり |
なお、行政調査の実効性を確保するために、調査に応じなかった者に刑罰を科す場合は、調査自体の根拠規定とは別に、刑罰を科すことにつき法律に明文の根拠規定が必要です。

行政調査と犯罪捜査の違い
行政調査と混同しやすいのが犯罪捜査です。両者は似ているようで、目的や実施方法、必要な手続がまったく異なります。
犯罪捜査とは、犯罪の発見や犯人の特定、そして刑罰を科すことを目的として行われる捜査活動です。主に警察官や検察官によって実施されます。
犯罪捜査では、証拠の押収や住居への立ち入りといった、強制的な捜査手段を用いることがあります。しかし、これらの強制手段を行使するには、”裁判官が発する令状(捜索令状や差押令状など)”が必要となります。これを「令状主義」といいます。
一方で、行政調査は、行政目的を達成するために必要な情報を収集する活動であり、行政庁の職員によって実施されます。行政調査では、原則として令状は不要とされています(任意調査・間接強制調査の場合)。
しかし、令状が必要な”直接強制調査(犯則調査)”を除けば、行政調査は通常、刑罰を科すことを目的としていないため、犯罪捜査とは明確に区別されています。▶判例
ここで問題となるのが、行政調査を「犯罪捜査の手段」として用いることです。これを許してしまうと、本来、裁判官の令状がなければできないはずの捜査行為を、令状なしで実施できてしまうことになります。
このような手法は、令状主義の回避(潜脱)にあたり、憲法違反となるおそれがあるため、行政調査を犯罪捜査の目的で利用することは許されないというのが判例・学説の一般的な立場です。
| 行う者 | 令状の要否 | |
| 任意調査・間接強制捜査 | 一般の行政庁の職員 | 不要 |
| 直接強制調査(犯則調査) | 特別な行政庁の職員1 | 必要 |
| 犯罪捜査 | 警察官・検察官 | 必要 |
行政調査の手続はどうなっている?
意外なことに、行政調査全般に適用される一般的な手続ルールは存在しません。
また、行政手続法も3条1項14号により、行政調査については適用除外とされています。
そのため、行政調査における手続の正当性は、個別の法律や判例に基づいて判断されるのが現状です。
まとめ:行政調査の基本をおさえよう
- 行政調査は、行政目的のための情報収集活動
- 強制の程度に応じて「任意調査」「間接強制調査」「直接強制調査」に分かれる
- 犯罪捜査との違いを明確にすることが重要(令状主義との関係)
- 法律の根拠が必要かどうかは、調査の強制性により異なる
- 手続には共通ルールがなく、個別法や判例に基づく
- 具体例:国税査察官など ↩︎