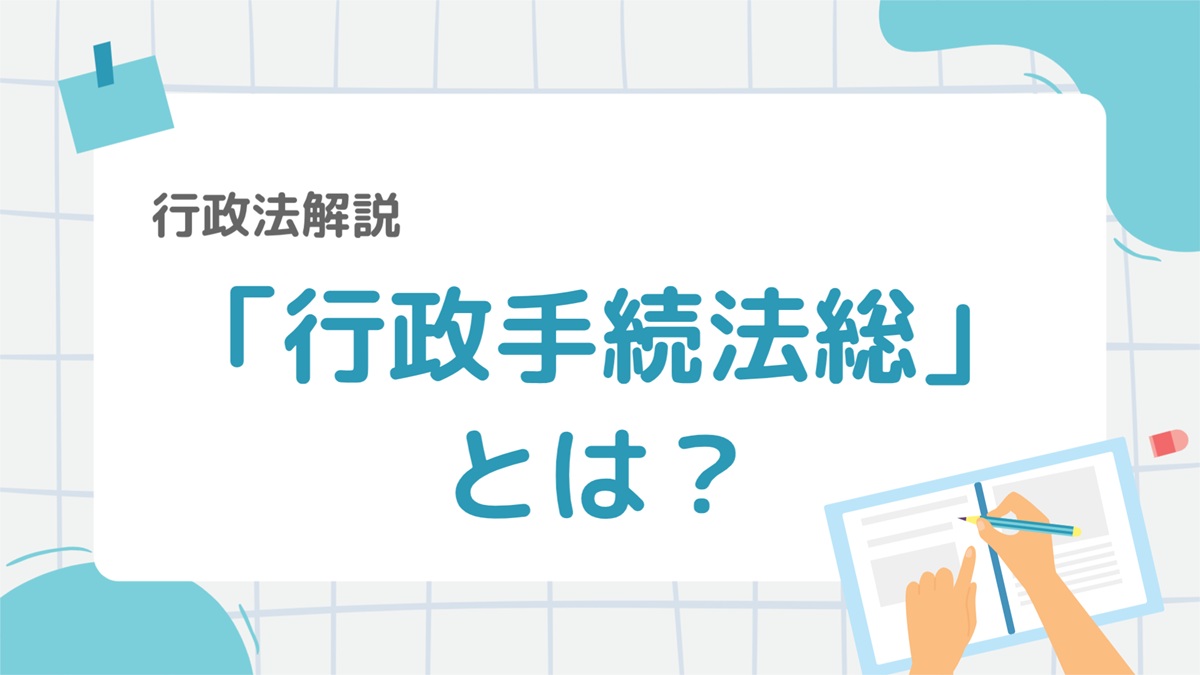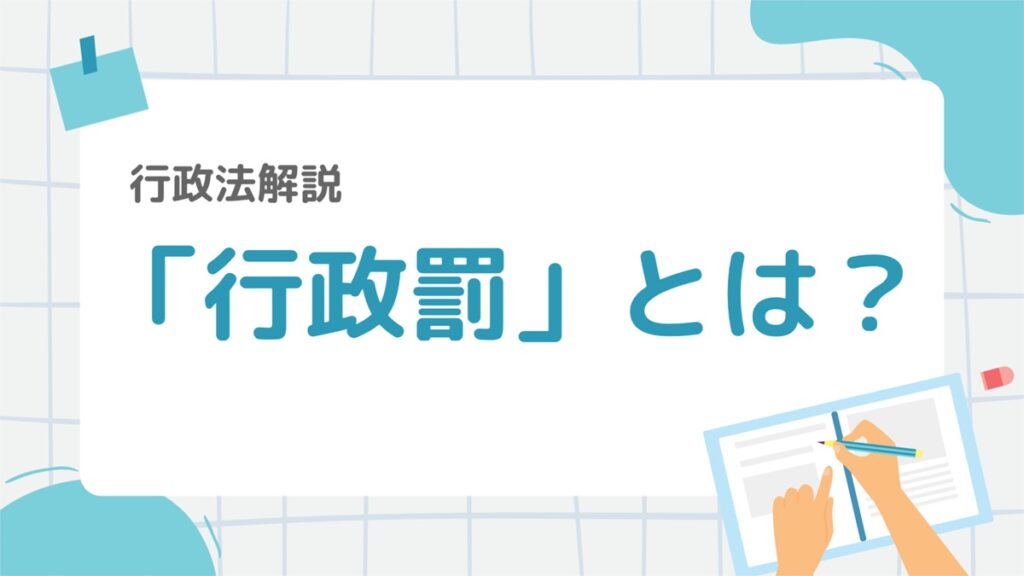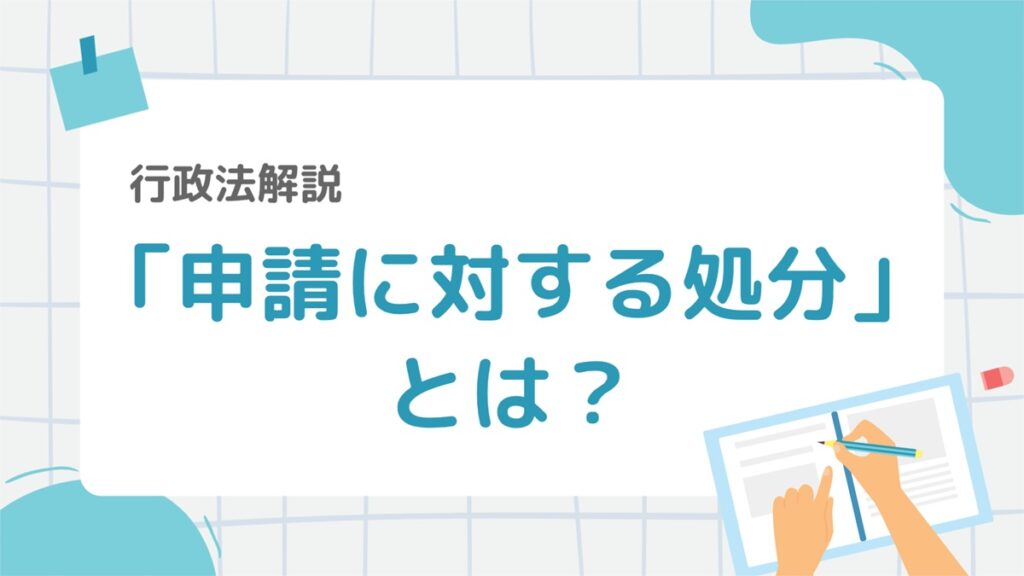はじめに|行政手続法とは?
行政手続法とは、「行政が国民に処分などを行う際のルールを定めた法律」です。
たとえば、国や自治体がある人に不利益な処分を出す場合、いきなり何の説明もなく命令されては困りますよね。そんなときに必要なのが「手続きのルール」です。
行政手続法は、行政の暴走を防ぎ、公正な行政を実現するための仕組みです。
行政手続法が必要とされる理由
行政作用によって不利益を受けた場合、行政不服審査法や行政事件訴訟法などによって「あとから」争うことができる。
しかし、次のようなケースでは、事後的な救済では手遅れになることもあります。
- 生活や営業に重大な影響を及ぼす場合(飲食店の営業不許可処分など)
- 建物の撤去命令など、元に戻せない処分
そこで、最初から行政が適正に行動するようにルールを設けるのが行政手続法の役割です。
行政手続法の目的【1条】
行政手続法の目的は、以下の通りです(法第1条1項)。
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
行政手続法1条1項
✅ポイント整理
- 行政の透明性・公正性を高める
- 国民が権利利益を保護するする
- 対象となる行政行為に共通のルールを設ける
なお、行政手続法は「一般法」です。特別な手続が別の法律で定められている場合は、そちらが優先されます(1条2項)。
行政手続法の対象となる行為
行政手続法は、すべての行政行為を対象としているわけではありません。対象は次の4つに限られます。
✅行政手続法の対象となる4つの行為
※ 処分は、「申請に対する処分」と「不利益処分」に分かれ、それぞれに手続きルールが設けられています。
✅対象となる行為の体型
---
config:
theme: neutral
---
flowchart LR
行政手続法の対象(行政手続法の対象)-->処分("処分<br>(行政行為)")
処分-->申請に対する処分
処分-->不利益処分
行政手続法の対象-->行政指導("行政指導")
行政手続法の対象-->届出("届出")
行政手続法の対象-->命令等の制定("命令等の制定<br>(行政立法)")
命令等の制定-->法律に基づく("法律に基づく<br>命令・規則")
命令等の制定-->審査基準(審査基準)
命令等の制定-->処分基準(処分基準)
命令等の制定-->行政指導指針(行政指導指針)
click 申請に対する処分 "https://gs.kabudata-dll.com/gh6/"
style 申請に対する処分 color:#1176d4
click 不利益処分 "https://gs.kabudata-dll.com/gh7-1/"
style 不利益処分 color:#1176d4
click 行政指導 "https://gs.kabudata-dll.com/gh8/"
style 行政指導 color:#1176d4
click 届出 "https://gs.kabudata-dll.com/gh9/"
style 届出 color:#1176d4
click 命令等の制定 "https://gs.kabudata-dll.com/gh10/"
style 命令等の制定 color:#1176d4行政手続法の適用除外
行政手続法は万能ではなく、性質上、手続きが適用されない行為(適用除外)もあります。
行政手続法の適用になじまない行為の適用除外
行政手続法の対象となる処分・行政指導・届出・命令等の制定であっても、性質上、適用になじまないものがあり、行政手続法の対象から除外されます(3条1項)。
適用除外となる行為は次のようなものがあります。
慎重な審議を重ねた上でなされるものであり、さらに行政手続法の定める手続を執っても無駄なもの
- 国会の両院・一院または議会の議決によってされる処分
- 裁判所・裁判官の裁判により、または裁判の執行としてされる処分
- 国会の両院・一院または議会の議決を経て、またはこれらの同意・承認を得た上でされるべき処分
- 検査官会議で決すべき処分および会計検査の際にされる行政指導
行政手続法よりも慎重な手続で処理されるもの
- 刑事事件に関する法令に基づき、検察官等がする処分・行政指導
- 国税・地方税の犯則事件に関する法令に基づき、国税庁長官等がする処分・行政指導
- 金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づき、証券取引等監視委員会等がする処分・行政指導
処分の性質上、行政手続法になじまないもの
- 学校等において、教育等の目的を達成するために、学生等に対してされる処分・行政指導
- 刑務所等において、収容の目的を達成するためにされる処分・行政指導
- 公務員又は公務員であった者に対してその職務・身分に関してされる処分・行政指導
- 外国人の出入国、難民の認定、補完的保護対象者の認定1、帰化に関する処分・行政指導
- 専ら人の学識技能に関する試験・検定の結果についての処分
- 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(双方を名あて人とするものに限る)・行政指導
- 公益に関わる事象が発生しまたは発生する可能性のある環境において、警察官等によってされる処分・行政指導
- 職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分・行政指導
- 審査請求・再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決・決定その他の処分
- 意見陳述のための手続において、法令に基づいてされる処分・行政指導
地方公共団体の機関の行為に対する適用除外
地方公共団体の機関の行為も、行政手続法による全国一律の規制をかけるよりも、地域ごとの事情に応じた柔軟な対応が求められることもあり、以下の表の通り適用除外とされる場合があります。2
〇:行政手続法の適用あり、×:行政手続法の適用なし
国の機関等に対する行為の適用除外
行政手続法の目的は「国民の権利利益の保護」です。そのため、国の機関が他の行政機関から処分を受ける場合は、基本的に適用除外とされます。
ただし、次のような場合は除きます。
- 国の機関が「一般企業と同じ立場」で処分を受けるとき
(例:国の機関がバス事業を行っていて、その営業許可を受けるような場合)
このようなケースでは、行政手続法が適用されます。
そこで、国の機関等に対する処分は、当該国の機関等がその固有の資格2においてその処分の名あて人となるものに限り、適用除外としています(4条1項)。3
〇:行政手続法の適用あり、×:行政手続法の適用なし
特殊法人等に対する処分の適用除外
特殊法人・認可法人4・指定法人5など、国と密接な関係にある団体については、一定の処分が適用除外となることがあります(4条2項・3項)。
まとめ|行政手続法は「行政の透明性」を支える大切な法律
行政手続法は、行政が国民に対して行う処分などについて、事前に手続きのルールを明確にし、公正・透明な行政を実現するための法律です。
行政書士試験でも出題頻度が高いため、次の3点は必ず押さえておきましょう。
- 行政手続法の目的
- 対象となる4つの行政行為
- 適用除外となる行為のパターン
「事後救済」ではなく「事前に行政をチェックする仕組み」であることが、この法律の最大の特徴です!
- 用語:紛争避難民など、難民条約上の難民ではないものの、難民に準じて保護すべき外国人のこと ↩︎
- 参考:地方公共団体は、適用除外とされた処分・行政指導・届出・命令等の制定に関する手続について、行政手続法の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない(46条)。 ↩︎
- 用語:一般国民と異なる立場のこと ↩︎
- 具体例:地方公共団体を名あて人とする地方公共団体の組合の設置許可処分(地方自治法284条2項・3項) ↩︎
- 認可法人:民間の関係者が発起人となって自主的に設立する法人で、業務の公共性などの理由によって、設立については特別の法律に基づき主務大臣の認可が要件となっている法人 ↩︎
- 指定法人:特別の法律に基づき特定の行政事務を遂行するものとして行政庁より指定された民法上の法人であって、行政処分権限を付与されたもの ↩︎