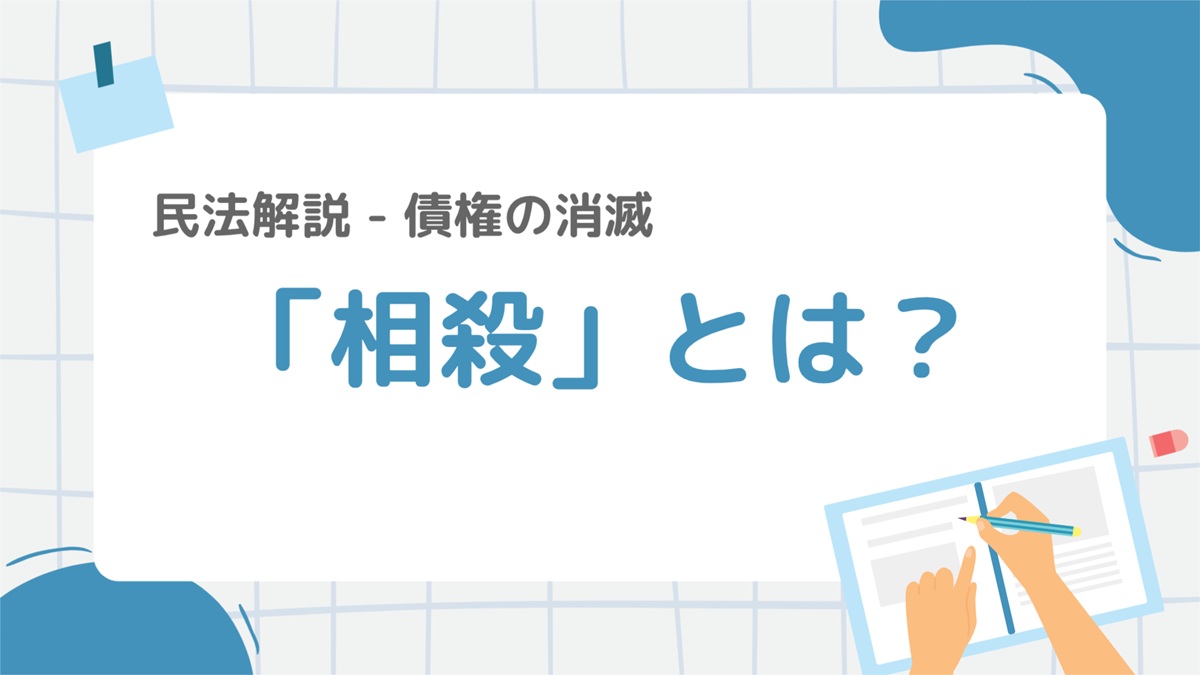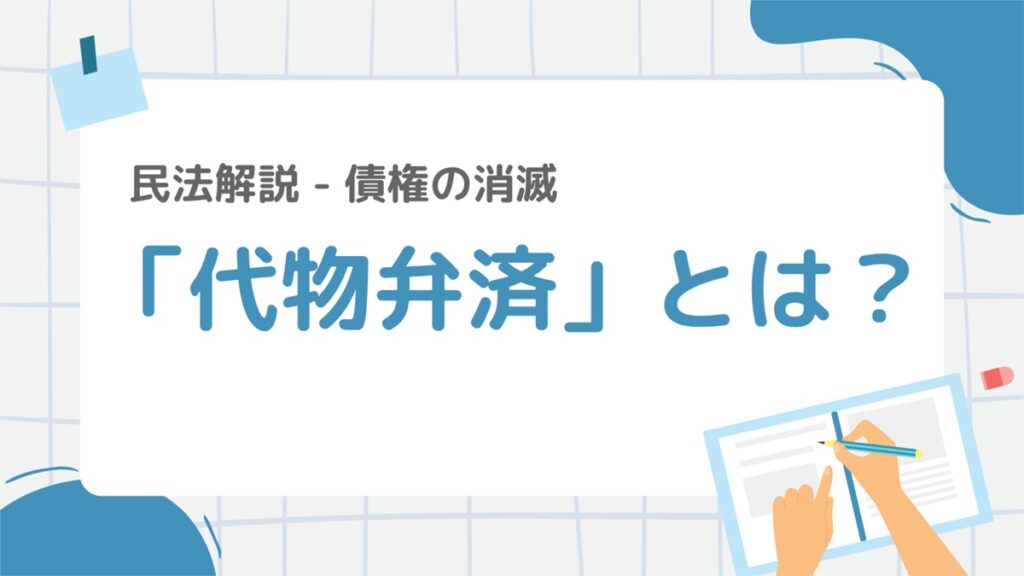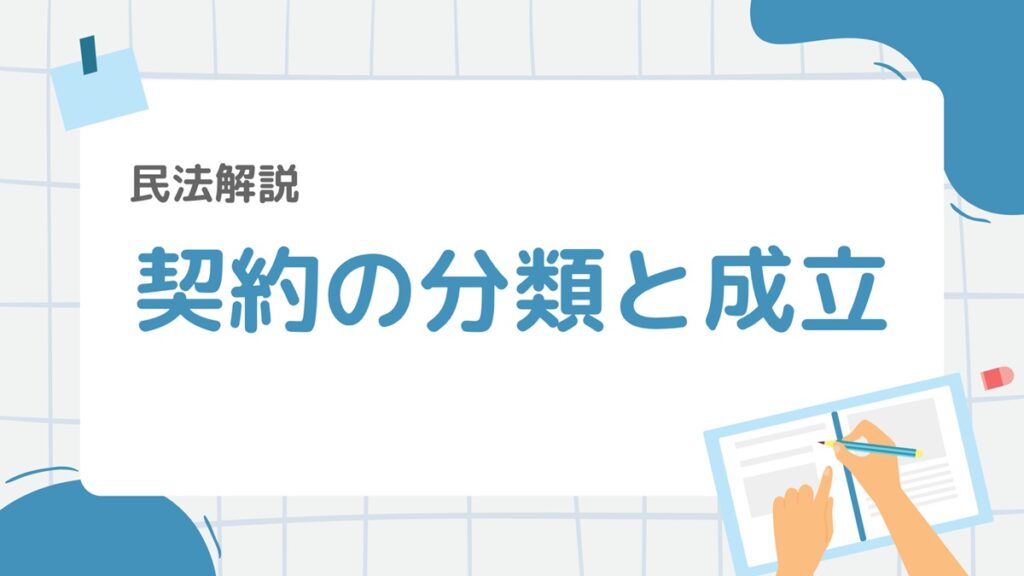【この記事はこんな人におすすめ】
- 「債権の消滅」の分野で得点アップを狙いたい人
- 「相殺」の要件や効果をスッキリ理解したい人
- 事例を交えてイメージしながら覚えたい人
- 行政書士試験の民法対策をしている人
債権の消滅原因のひとつに「相殺(そうさい)」があります。
この記事では、行政書士試験によく出る「相殺」について、事例や条文をもとに、わかりやすく整理して解説していきます!
目次
債権の消滅 – 相殺とは?
相殺とは、債権者と債務者がお互いに同じ種類の債務を負っているときに、一方が相殺の意思表示をすることで、互いの債務を対当額だけ消滅させることをいいます。
事例
---
config:
theme: neutral
---
flowchart LR
A("A<br>相殺の意思表示")
B("B<br> ")
A--"自働債権 100万円"-->B
B--"受働債権 100万円"-->A
- AはBに対して100万円の貸金債権を持っている
- BもAに対して100万円の貸金債権を持っている
この場合、Aが相殺の意思表示をすれば、お互いの債務が消滅します!
【用語ポイント】
相殺する側(A)⇒自働債権
相殺される側(B)⇒受働債権
相殺の要件(相殺適状)
相殺するには、「相殺適状」という条件がそろっている必要があります(民法505条)。
相殺適状態の要件
時効と相殺(民法508条)
時効によって消滅した債権でも、
- 時効完成前に相殺適状にあった場合
には、債権者は相殺を主張できます!(508条)
これは、すでに発生している「相殺の期待」を守るためです。
相殺が禁止される場合
相殺には禁止される場合もありますので注意しましょう。
- ①当事者間で相殺を禁止・制限する合意がある場合
- ②自働債権とする相殺が禁止される場合
-
以下のような抗弁権がついた債権を、自働債権として相殺することはできません(大判昭13.3.1、最判昭32.2.22)。
- ③受働債権とする相殺が禁止される場合
-
以下のような債権は、相殺される側に使えません。
相殺の方法(民法506条)
相殺は、一方が相手方に対して意思表示をするだけで成立します!
また、条件や期限を付けた相殺の意思表示は無効です(506条1項)。
相殺の効果
相殺が成立すると、互いの債務が対当額だけ消滅します(505条1項)。
この結果、わざわざ支払いや受け取りをする手間がなくなります!
なお、効果は相殺適状時に遡って生じます(505条2項)。
まとめ
「相殺」は、債権が同じ種類で対等にある場合に、一方的な意思表示だけで債務を消滅させることができる便利な制度です。
試験では、「相殺できる場合」と「相殺が禁止される場合」の区別がよく問われるので、しっかり整理しておきましょう!
- 参考:受働債権の期限の利益は放棄することができる(136条2項本文)ので、自働債権が弁済期であれば相殺可能。 ↩︎
- 具体例:相互に労務を提供する債務の場合や、相互に騒音を出さないという場合のように、現実の履行がないと意味がない場合は相殺できない。 ↩︎
- 重要判例:趣旨として、不法行為の被害者に現実の弁済による損害の補填をうけさせるとともに、不法行為の誘発を防止する点にあり、悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権は自働債権とする相殺は可能(最判昭42.11.30) ↩︎
- 参考:自働債権が差押後に取得され、かつ、差押後の原因に基づいて生じたものでなければ、両債権の弁済期の前後を問わず、相殺することができる(511条1項・2項) ↩︎