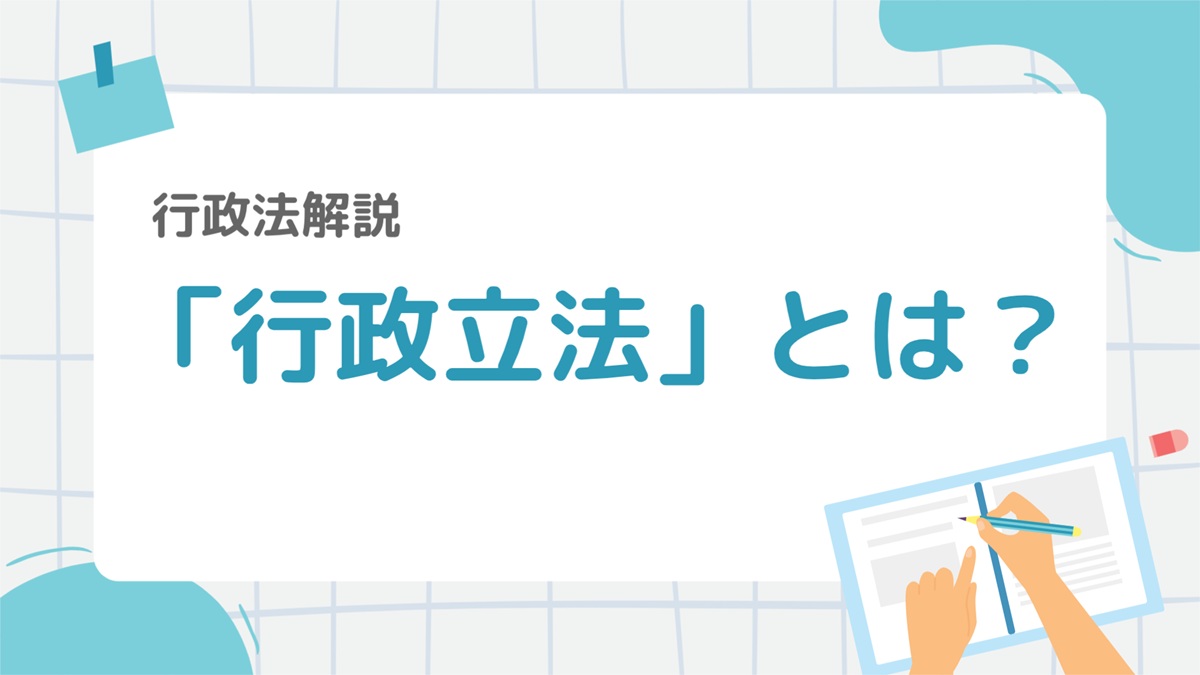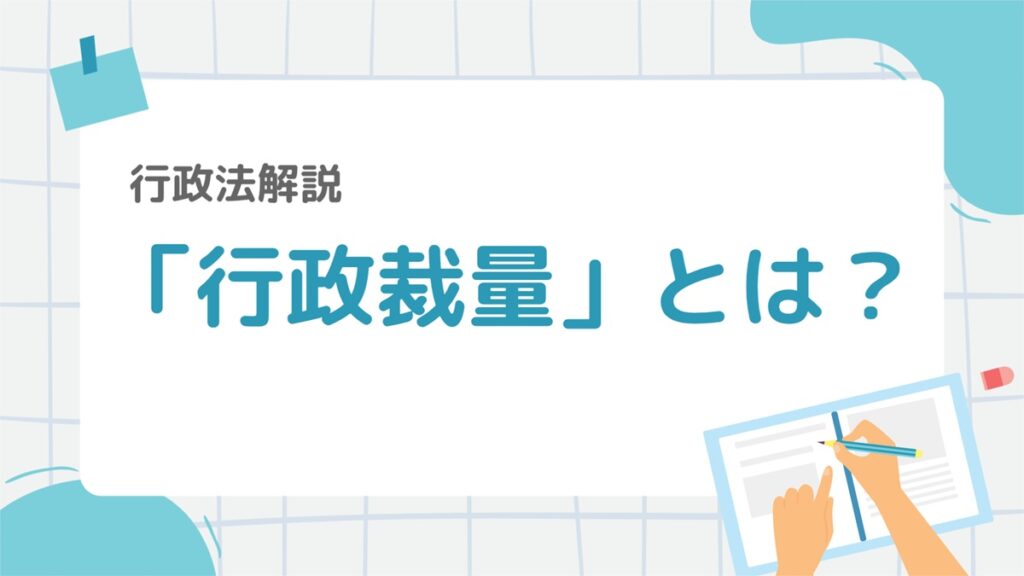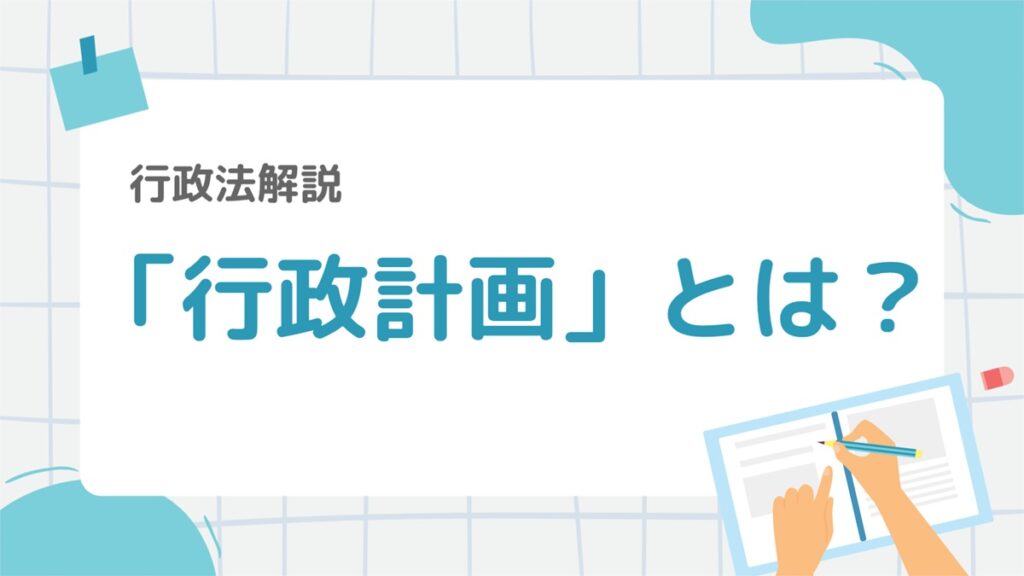- 行政書士試験の行政法で「行政立法」が苦手な方
- 法規命令と行政規則の違いがわからず混乱している方
- 試験対策として、行政立法の全体像を一気に整理したい方
行政立法とは?まずは基本の意味から
「行政立法」とは、行政機関が作成するルールのうち、法的な効力を持つものをいいます。
通常、法律(国のルール)は国会で作られますが、すべてを国会が細かく定めるのは現実的ではありません。たとえば、法律で「◯◯は許可が必要」とだけ書かれていても、具体的な手続や基準までは記されていないことがよくあります。
そこで、行政機関にある程度の「ルール作りの権限」が与えられ、その結果として作られるのが行政立法です。1
行政立法の2つのタイプ
行政立法は、次の2種類に大きく分けられます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 法規命令 | 国民の権利や義務に直接関わるルール |
| 行政規則 | 行政機関内部で使われるルール(国民には直接影響なし) |
法規命令とは?〜国民に直接影響する命令〜
法規命令とは、国民の権利や義務に直接関係するルールのことです。
行政機関が発する内容ですが、法律と同じように国民を拘束する効力があります。
発する行政機関によって呼び方が異なります。
| 名称 | 発する機関 | 根拠法令 |
| 政令 | 内閣が発する法規命令 | 憲法73条6号 |
| 内閣府令 | 内閣総理大臣が発する法規命令 | 内閣府設置法7条3項 |
| 省令 | 各省大臣が発する法規命令 | 国家行政組織法12条1項 |
| 規則 | 各庁の長や各委員会が発する法規命令 | 国家行政組織法13条1項 |
法規命令の2つのタイプ
法規命令は、行政法学上、委任命令と執行命令の2つに分類されます。
- ① 委任命令(いにんめいれい)
-
意味:法律の「委任(任せること)」に基づいて、新たに国民の権利や義務の内容を定める命令
必要なもの:必ず個別の法律の根拠が必要2
ポイント:法律の委任の範囲を超えて命令を出した場合は、その命令は無効になります。▶判例
- ② 執行命令(しっこうめいれい)
-
意味:すでにある法律を実施するための具体的な手続きや細かい内容を定める命令
必要なもの:個別の法法律の根拠は不要。憲法73条6号や国家行政組織法12条1項などの一般的な授権があればOK
ポイント:新たな権利や義務は発生しません。
- 委任命令では、必ず個別の法律の委任が必要です。
- 委任の範囲を超えて命令を出した場合、その命令は無効になります。
- 執行命令では、新たな権利・義務は発生しません。
行政規則とは?〜内部向けのルール〜
「行政規則」は、行政機関の内部的なルールであり、国民に直接影響を与えるものではありません。
以下のような名前で呼ばれます。
| 訓令(くんれい) | 上級行政機関が下級行政機関の権限行使を指揮するために発する命令 |
| 通達(つうたつ) | 訓令のうち文書で行われるもの |
| 告示(こくじ) | 行政機関が必要な情報を公に知らせるもの3 |
行政規則の4つの種類(行政法学上の分類)
これらの行政規則は、行政法学上、解釈基準、裁量基準、給付基準、行政指導指針(指導要綱と呼ばれる場合もある)の4種類に分類されます。
行政規則のポイント
- 国民の権利や義務に影響を与えないので、法律の根拠は不要です。
- 公表の義務もありません(ただし、実務上は公表されることが多いです)。
- 裁判での基準(裁判規範)にはならないため、行政規則に違反した処分でも、すぐに違法とは限りません。5
✅まとめ:行政立法は2種類、違いを押さえよう!
--- config: theme: neutral --- flowchart LR 行政立法-->法規命令(【法規命令】<br>・委任命令<br>・執行命令) 行政立法-->行政規則(【行政規則】<br>・解釈基準<br>・裁量基準<br>・給付基準<br>・行政指導指針_指導要綱)
| 分類 | 内容 | 国民の権利義務への影響 | 法律の根拠の要否 |
| 法規命令 | 国民に直接適用される命令 | あり | 必要 (執行命令は一般的根拠でOK) |
| 行政規則 | 行政内部のルール | なし | 不要 |
- 行政立法=行政機関が作る法的効力のあるルール
- 法規命令は国民に直接影響。委任命令・執行命令の違いに注意
- 行政規則は内部ルール。裁判規範にはならない
行政書士試験では、法規命令と行政規則の違い、委任命令と執行命令の根拠要件の違いがよく問われます。繰り返し確認して、しっかり理解しましょう!
- 参考:行政立法については、行政行為と異なり、公定力・不可争力などの効力は認められない ↩︎
- 参考:法律の委任があれば、行政立法でも罰則を設けることもできる。これは、指令・省令のみならず、規則であっても同様 ↩︎
- 参考:告示は、法規命令としての性格を有することもある。例えば文部科学大臣が告示する学習指導要領など(最判平2.1.18) ↩︎
- 具体例:地方行員に対する懲戒処分について、「正当な理由なく10日以内の間、勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。」といった基準など ↩︎
- 参考:行政規則に違反する処分が行われた場合、当該行政規則の範囲内で処分が行われた者との間で不平等を生じ、平等原則に違反するものとして違法とされる余地がある ↩︎