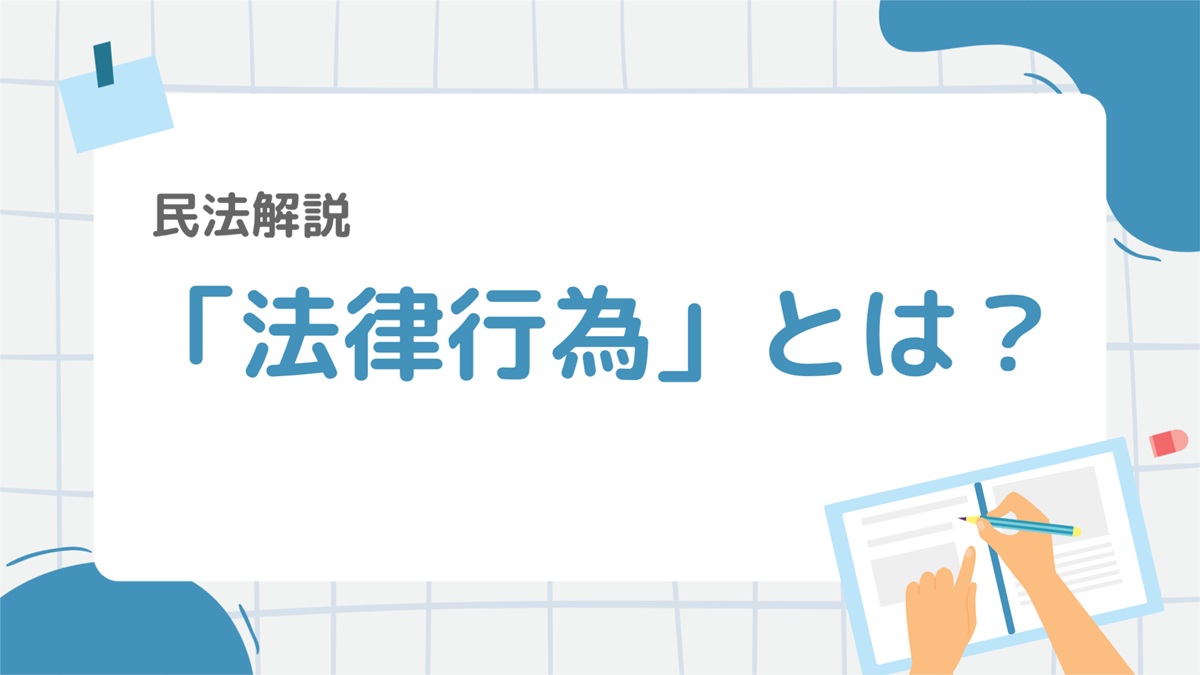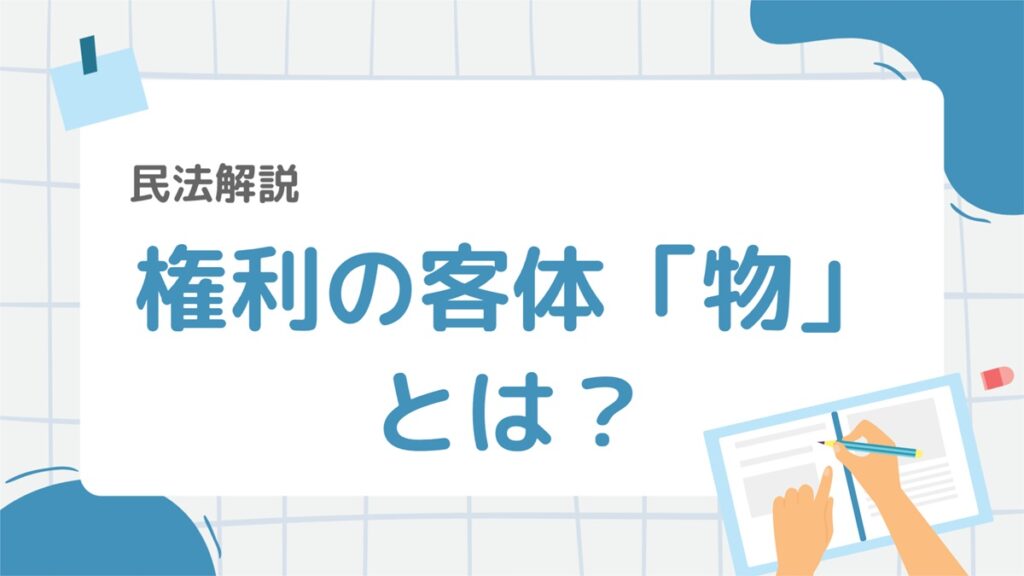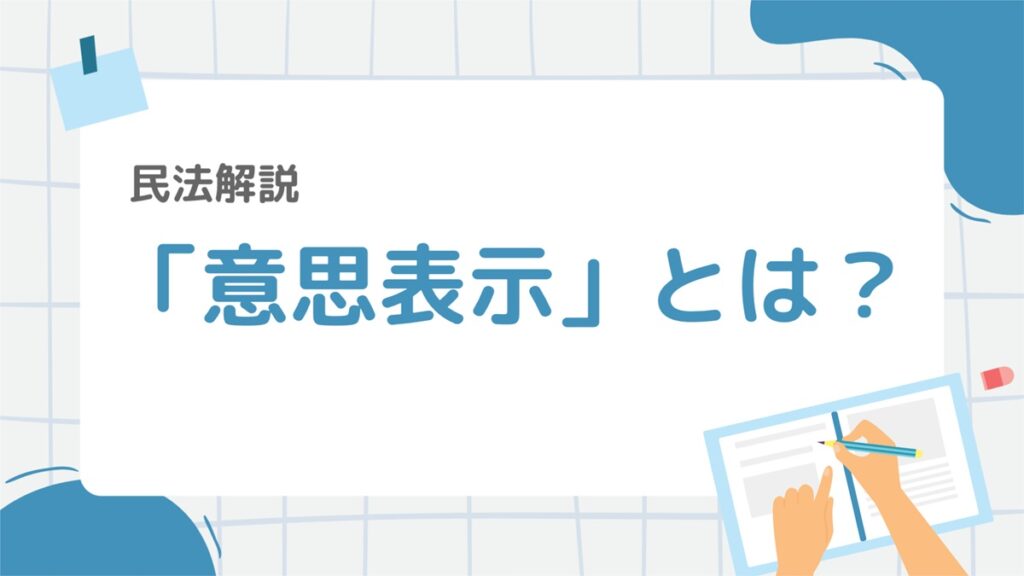この記事はこんな人におすすめ
- 民法の基本概念「法律行為」の種類を理解したい方
- 「準法律行為」やその具体例をわかりやすく知りたい方
- 行政書士試験で問われる「無効となる法律行為の要件(公序良俗・強行規定違反)」を整理したい方
目次
法律行為とは?
「法律行為」とは、ある意思表示によって、法律上の権利や義務が発生・変更・消滅する行為のことです。つまり、当事者の意思が法律効果を生むという点が最大の特徴です。
この法律行為は、成立のしかたによって次の3つに分類されます。
- 単独行為
効力を発生させようとする物の単独の意思で第三者にも効力を及ぼすような法律行為
例:取消(95条1項)・相殺(505条)・契約の解除(540条1項)・遺言 - 契約
2人の人間の意思の合致による法律行為
例:売買(555条)・賃貸借(601条) - 合同行為
多数の者が一定の目的のためになす意思の合致による法律行為
例:会社などの団体を設立する行為👉【参考】会社法:株式会社設立の手続
準法律行為
「準法律行為」とは、法律行為のように意思表示を行う点は似ていますが、その意思表示自体が法律効果を直接発生させるわけではない行為です。次の2種類に分類されます。
- 意思の通知
意思を伝えることを目的とするが、その意思だけで特定の効果を生じさせるわけではない行為
例1:時効の完成猶予のための催告(150条)
例2:債務の履行の催告(541条) - 観念の通知
特定の事実を伝えることで、法律によって認められた効果が生じる行為
例1:時効の更新事由となる債務の承認(152条1項)
例2:債権譲渡の通知(467条)
法律行為の有効要件
法律行為は、成立するだけでは足りず、法律的に「有効」であることが必要です。以下のような場合、法律行為は無効とされます。